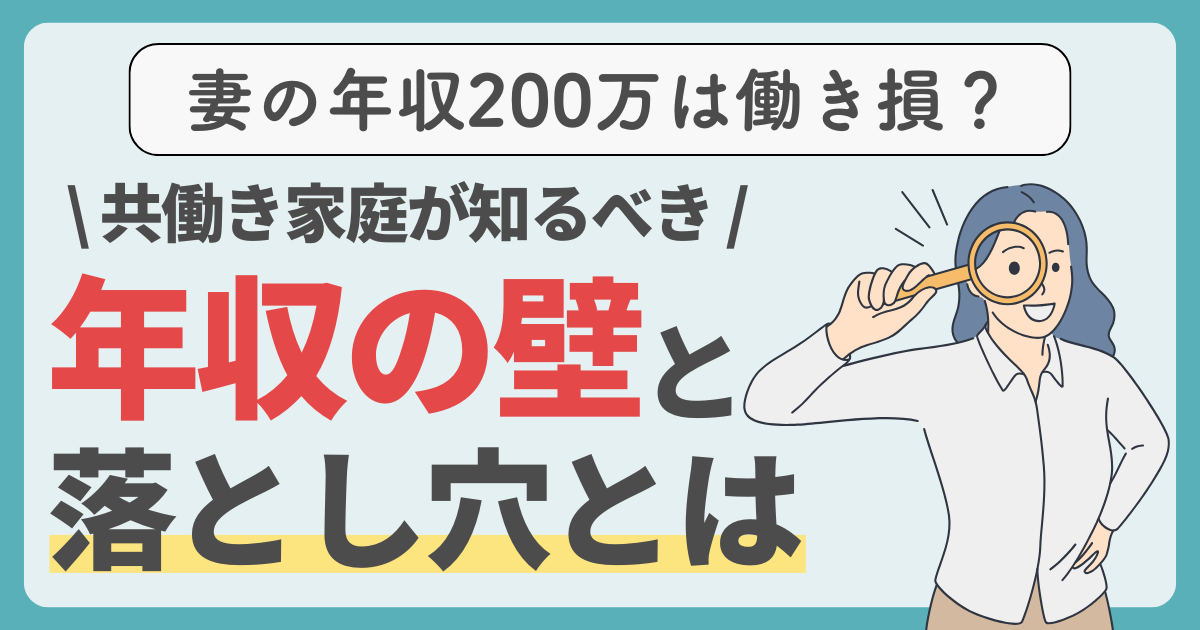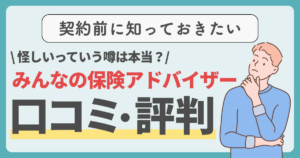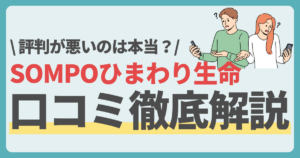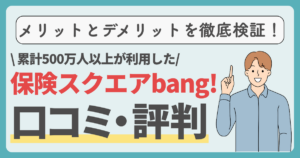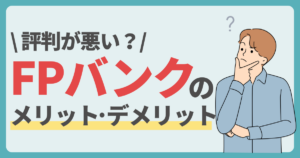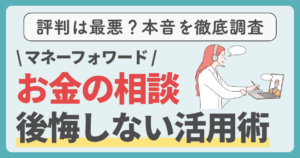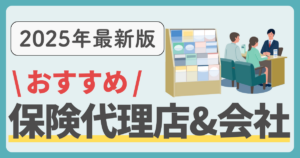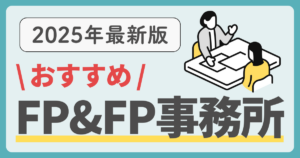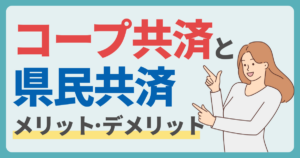「もう少し家計に余裕がほしい」と共働きで収入アップを目指す中で、「年収の壁」を意識して働き方を調整している方は多いのではないでしょうか。
特に、妻の年収が200万円というラインは、税金や社会保険の扶養から外れるため、「かえって手取りが減って働き損になるのでは?」と不安に感じやすい金額です。
しかし、仕組みを正しく理解すれば、年収200万円は決して「損」ではありません。むしろ、将来的なメリットも大きい働き方です。
この記事では、複雑な「年収の壁」の最新情報をわかりやすく解説し、妻の年収が200万円の場合に家計がどう変わるのか、そして損をせずに世帯収入を最大化するための具体的な方法を徹底的にご紹介します。
- 妻の年収200万円が「働き損」と言われる本当の理由
- 2025年最新版「年収の壁」の仕組みと今後の変更点
- 年収200万円で超える壁と、税金・社会保険料の具体的な変化
- 損をしないための働き方や、家計を助ける制度・税金対策
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
【結論】共働きで妻の年収200万は「必ずしも損ではない」

妻の年収が200万円に達すると、税金や社会保険の扶養から外れるため、世帯の手取りが一時的に伸び悩むことがあります。
この現象が「働き損」と言われる主な理由です。
しかし、目先の金額だけで判断するのは早計です。長い目で見れば、社会保険への加入は将来の年金受給額の増加や、万が一の際の保障を手厚くするなど、多くのメリットをもたらします。
ここでは、なぜ「損」と感じるのか、そしてそれが必ずしも「損」ではない理由を詳しく解説します。
妻の年収200万は扶養を外れるラインだが“働き損”とは限らない
年収200万円は、税制上・社会保険上の扶養から外れる分岐点、いわゆる「年収の壁」をすべて超える収入ラインです。具体的には、以下の壁が関係します。
- 123万円の壁:所得税がかかり始めるライン
- 130万円の壁:社会保険の扶養から外れるライン
- 160万円の壁:配偶者特別控除が満額受けられる上限ライン
- 201.6万円の壁:配偶者特別控除が完全になくなるライン
これらの壁を超えることで、これまで受けていた税金の優遇がなくなり、新たに社会保険料の負担が発生します。
その結果、「収入は増えたのに手取りが減った」という状況が生まれ、「働き損」と感じやすくなるのです。
しかし、これはあくまで一時的な現象であり、世帯収入の増加や将来受けられる保障の充実といったプラス面を考慮すれば、一概に「損」とは言えません。
共働きと「年収の壁」最新まとめ
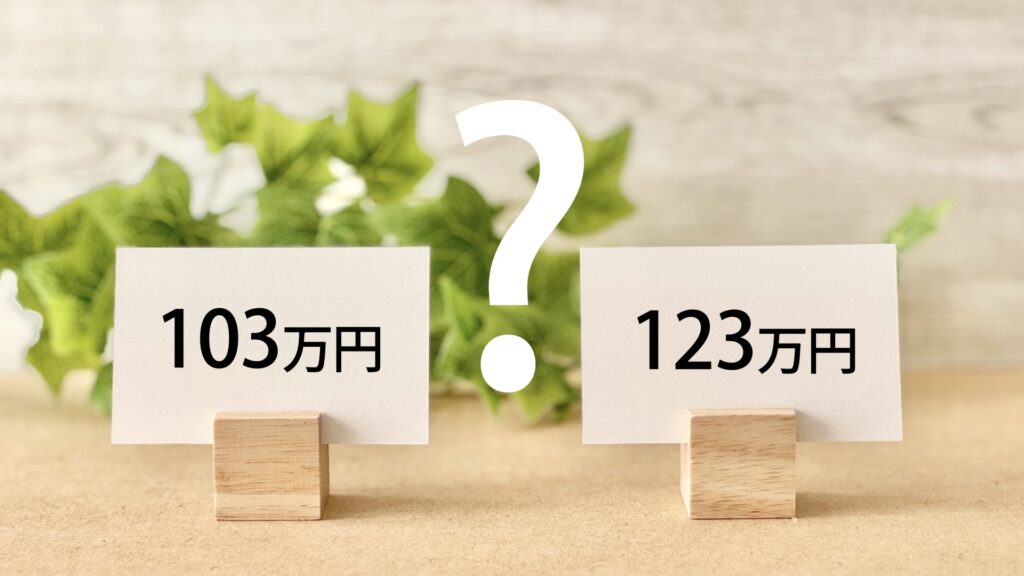
「年収の壁」は、税金や社会保険料の負担が変わる収入の境界線ですが、制度は今、大きな転換期を迎えています。
2025年の年金制度改正により、特に社会保険の壁は将来的な撤廃が決定しました。
ここでは、2025年現在の制度と、確定している未来の変更点を合わせて解説します。
【税制】扶養控除の壁は103万円→123万円に引き上げ
これまで「103万円の壁」として知られていた、妻自身に所得税がかかり始めるラインが、2025年分(令和7年分)の所得税から123万円に引き上げられました。
これは、基礎控除と給与所得控除の金額がそれぞれ引き上げられたことによるものです。
これにより、これまで103万円を意識して労働時間を調整していた方も、新たに20万円多く働けるようになり、より柔軟な働き方が可能になります。(参考:首相官邸「年収の壁対策」)
配偶者控除】満額対象は150万円→160万円に拡大
夫(主たる生計者)の税負担に関わる「配偶者特別控除」も改正されました。
控除額が満額の38万円となる妻の年収上限が、従来の150万円から160万円に拡大されています。
これにより、妻の年収が150万円を超えても、160万円までであれば夫の税負担は変わらず、世帯の手取り収入を増やしやすくなりました。 (参考:厚生労働省「『配偶者手当』の在り方の検討をお願いします」 ※令和7年度税制改正の内容として記載)
【社会保険】106万円の壁は対象拡大・将来的に撤廃予定
勤務先の条件によっては年収約106万円で社会保険への加入が必要となる「106万円の壁」。この壁は、2024年10月に対象企業が「従業員数51人以上」に拡大されました。
さらに重要な動きとして、2025年の年金制度改正法により、この「106万円」という賃金要件と企業規模要件は、将来的に撤廃されることが決定しています。
今後は年収額ではなく、労働時間(週20時間以上など)が社会保険加入の主な基準となり、「106万円の壁」という概念自体がなくなっていく見込みです。
【130万円の壁】扶養から外れる基準は依然として存在
「106万円の壁」の対象とならない事業所で働く方が意識する「130万円の壁」は、2025年時点でも社会保険の扶養から外れる基準として存在しています。
繁忙期などの一時的な収入増であれば、事業主の証明により引き続き扶養に入れる特例措置も継続されていますが、恒常的に年収130万円を超える場合は、自身で国民健康保険・国民年金に加入する原則は変わりません。
ただし、前述の通り社会保険の適用が拡大していく流れの中で、この壁の役割も将来的には変わっていくと考えられます。
妻の年収200万円はどの壁を超える?
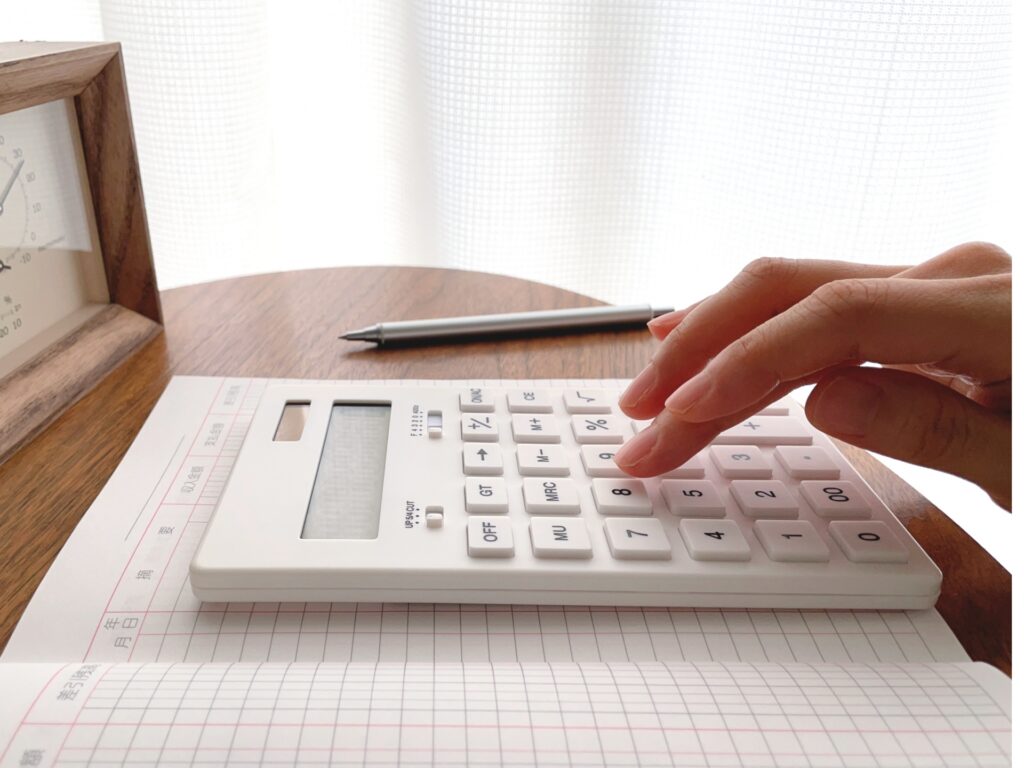
前の章で解説した通り、「年収の壁」には税制と社会保険で複数の基準があります。
結論から言うと、妻の年収200万円は、これら全ての壁を上回る収入です。
扶養から完全に外れ、一人の納税者・社会保険加入者として扱われることになります。
ここでは、具体的に家計にどのような変化が起きるのか、税金と社会保険の側面から詳しく見ていきましょう。
税制面|200万円は控除の対象外だが、課税額はどう変わる?
年収200万円は、2025年から引き上げられた「123万円の壁」と「160万円の壁」をいずれも超えています。
- 妻自身への影響:年収123万円を超えるため、妻自身に所得税と住民税が課税されます。概算ですが、年収200万円の場合、所得税と住民税を合わせて年間8万円〜10万円程度の納税額になるのが一般的です。
- 夫への影響:妻の年収が160万円を超えると、夫が受けられる「配偶者特別控除」の額は段階的に減少し、201.6万円を超えると控除額はゼロになります。
年収200万円の時点では、夫は3万円の配偶者特別控除を受けられますが、もし妻の年収が202万円になると、この控除はなくなります。 (参考:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」)
社会保険|200万円なら保険加入が必須で手取りに影響
年収200万円は「106万円の壁」「130万円の壁」を大幅に超えているため、夫の社会保険の扶養から外れ、妻自身が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することが必須となります。
これが手取り額に最も大きな影響を与えます。標準的な保険料率で計算すると、年収200万円の場合、妻が支払う社会保険料は年間で約30万円にもなります。
毎月の給与から約2.5万円が天引きされる計算になり、「収入は増えたのに手取りが少ない」と感じる最大の要因となります。
しかし、これは単なる支出ではなく、将来の年金や手厚い医療保障への「投資」であるという側面も忘れてはなりません。 (参考:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表」 ※毎年更新されます)
200万と201万の違いとは?境界で損得が変わるケース
年収200万円を超えたあたりで意識されるのが「201.6万円の壁」です。
これは、夫が受けられる配偶者特別控除が「3万円」から「0円」になる最終ラインです。
- 妻の年収201万円の場合:配偶者特別控除(3万円)の対象になる。
- 妻の年収202万円の場合:配偶者特別控除の対象外(0円)になる。
この壁を1万円超えることで、夫の課税所得が3万円増えるため、夫の税率が10%なら約3,000円、20%なら約6,000円、夫の税金(所得税・住民税)が年間で増加します。
ただし、この段階では妻の収入が1万円増えるのに対し、世帯の税負担増は数千円程度にとどまります。
130万円前後で見られるような「収入が増えたのに手取りが減る」という逆転現象はまず起こりません。
このレベルになると、働いた分だけ世帯収入は着実に増えていくと言えます。
妻の年収200万円で「損」と感じやすいケース

年収200万円は、長い目で見れば世帯収入を増やし、将来の安心にも繋がる働き方です。
しかし、家計の状況によっては、扶養から外れることで一時的に「損」だと感じてしまう場面も確かに存在します。
特に、これまで受けていた恩恵がなくなることによる心理的な影響は大きいでしょう。
ここでは、そうした「損」と感じやすい具体的なケースを3つ解説します。
扶養から外れることで控除が使えなくなる
最も直接的な影響は、夫の税金計算に適用されていた「配偶者特別控除」が大幅に減る、もしくなくなることです。
妻の年収が201.6万円を超えた瞬間に、夫は最大38万円(※)あった所得控除がゼロになります。
これにより夫の課税所得が増え、所得税や住民税が年間で数万円単位で増加する可能性があります。
世帯全体の収入は増えているにもかかわらず、夫の給与から天引きされる税額が増えるため、「妻が働き始めたせいで自分の税金が上がった」と感じ、損をしたような気持ちになりやすいのです。 (※控除額は夫の所得によって異なります。)
社会保険料の自己負担が増える
家計へのインパクトが最も大きいのが、妻自身が社会保険料を支払う義務が生じることです。
前述の通り、年収200万円の場合は年間約30万円もの社会保険料が給与から天引きされます。
これまで扶養の範囲内であれば、保険料の負担なく国民年金(3号被保険者)や夫の健康保険に加入できていたため、この負担増は非常に大きく感じられます。
月々の手取り額が思ったように伸びない最大の理由であり、短期的な視点で見ると「これだけ働いたのに、手元に残るのはこれだけか」という徒労感、つまり「働き損」という感覚に直結しやすいポイントです。
児童手当や住民税非課税世帯の条件から外れる
世帯収入の増加は、所得に応じて給付額が変わる公的制度の対象から外れてしまうリスクも伴います。
- 児童手当の所得制限
児童手当には所得制限があり、主たる生計者(通常は収入の多い親)の年収が一定額を超えると、手当が減額されたり、支給されなくなったりします。
妻が収入を増やすことで世帯収入全体が底上げされ、結果的に夫の年収が所得制限のラインを超えてしまうと、手当が受けられなくなり「損」と感じる一因になります。
- 住民税非課税世帯の優遇措置
世帯全員の住民税が非課税になる「住民税非課税世帯」は、臨時給付金の対象になったり、国民健康保険料が減免されたりと、様々な優遇措置を受けられます。
妻の年収が200万円あると、この非課税世帯に該当することはまずありません。もし以前は非課税世帯としての恩恵を受けていた場合、その権利を失うことも「損」と感じる要因になります。
妻の年収200万円は「損ではない」ケースもある

前の章で解説したような短期的な負担増や手取りの伸び悩みは、確かに「損」だと感じやすいポイントです。
しかし、それは物事の一面でしかありません。より長い視点で見れば、妻が年収200万円を稼ぐことには、その負担を上回る大きなメリットが存在します。
むしろ、将来の家計を安定させるための賢い選択と言えるでしょう。
厚生年金加入で将来の年金額アップ
最大のメリットは、将来受け取れる年金額が大幅に増えることです。
夫の扶養に入っている場合(国民年金第3号被保険者)、将来受け取れるのは基礎年金のみです。
一方、勤務先の社会保険に加入すると、その基礎年金に上乗せして厚生年金が支給されます。
簡単な試算ですが、年収200万円で10年間厚生年金に加入した場合、将来の年金額は年間約11万円上乗せされます。
20年間なら年間約22万円です。
これが生涯にわたって支給されるため、老後の生活の安定度が格段に向上します。自分の老後資金を自分で準備できることは、精神的な安心にも繋がります。(参考:日本年金機構 厚生年金保険の保険料)
自分の健康保険で保障が手厚くなる
扶養から外れ、自分自身の健康保険に加入することで、万が一の際の保障が格段に手厚くなります。
これは、夫の扶養に入っているだけでは得られない大きなメリットです。
- 傷病手当金:病気やケガで連続4日以上仕事ができない場合、給与の約3分の2に相当する額が最長1年6ヶ月にわたって支給されます。自分の収入が途絶えるリスクをカバーできる、共働き世帯の重要なお守りです。
- 出産手当金:出産のために産休を取得した場合、給与の約3分の2が支給されます。産休中の生活を経済的に支えてくれる、働く女性にとって心強い制度です。
これらの保障は、扶養されている立場では利用できません。
自分で保険料を支払うからこそ得られる、貴重なセーフティネットなのです。(参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」)
世帯全体の収入は増えるためライフプランが広がる
税金や社会保険料を支払ったとしても、世帯全体の手取り収入は確実に増加します。
妻の年収が200万円増えた場合、税金と社会保険料で約40万円が引かれたとしても、手元に残るお金は年間で約160万円も増える計算になります。月々に換算すれば13万円以上です。
この増えた収入は、家計に大きな余裕をもたらします。
- 住宅ローンの繰り上げ返済
- 子どもの教育資金の積立(NISAの活用など)
- 老後資金の準備(iDeCoの活用など)
- 家族旅行や趣味への投資
このように、実現できるライフプランの選択肢が大きく広がり、より豊かで安心できる将来設計を描くことが可能になるのです。
共働きで損しない!妻の年収200万円の活かし方

妻の年収が200万円に達することは、長期的に見れば世帯にとって大きなプラスです。
その恩恵を最大限に引き出すためには、変化に対応した「家計の最適化」が欠かせません。
ただ漠然と働き始めるのではなく、少しの知識と工夫で手元に残るお金は大きく変わります。
ここでは、今日から実践できる5つの具体的なアクションをご紹介します。
① 最新の「年収の壁」を意識して働き方を調整する
年収200万円は全ての壁を超えていますが、最新の制度変更を把握しておくことが重要です。
特に、「106万円の壁」が将来的に撤廃される流れは、今後の働き方や同僚の環境にも影響します。
また、夫の配偶者特別控除がなくなる「201.6万円の壁」も意識しておくと、年末調整などで慌てずに済みます。
「壁を恐れて働かない」のではなく、「壁を理解して賢く働く」という視点を持ち、常に最新の情報を確認する習慣をつけましょう。
② 社会保険料を補助する制度や助成金を使う
政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として、「社会保険適用促進手当」という制度があります。(参考:厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ)
これは、従業員が新たに社会保険に加入する際の負担を軽減するために、企業が支給する手当のことです。
この手当は、社会保険料の計算対象外となるため、実質的な手取り額を増やす効果があります(最大2年間)。
ご自身の勤務先がこの制度を導入しているか、一度、人事や総務の担当者に確認してみることをお勧めします。
③ iDeCo・ふるさと納税など税制優遇をフル活用
妻自身が所得税・住民税を納めるようになるということは、税制優遇制度(所得控除)をフル活用できるということです。
これは大きなメリットなので、必ず活用しましょう。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):自分で掛金を拠出して運用し、老後資金を作る制度です。
掛金の全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税を大きく節約できます。例えば毎月2万円を拠出すれば、年間24万円が課税所得から差し引かれ、税負担が軽くなります。
- ふるさと納税:応援したい自治体に寄付ができる制度です。
寄付額のうち2,000円を超える部分が、翌年の住民税などから控除されます。返礼品がもらえるだけでなく、本来納めるべき税金の使い道を指定できる、賢い節税策です。
④ 収入と支出のシミュレーションで家計を可視化
扶養から外れると、妻の手取り額や夫の税金が変わり、世帯全体の収入と支出のバランスが変化します。
この変化を正確に把握するために、一度しっかりと家計のシミュレーションを行いましょう。
妻の給与明細や夫の源泉徴収票をもとに、「世帯の総収入(手取り)がいくら増え、社会保険料や税金の負担がいくら増えるのか」を数字で可視化します。
これにより、漠然とした「損した気分」がなくなり、新しい収入に合わせて貯蓄計画やお金の使い方を具体的に見直すことができます。
⑤ 将来を見据えてFP相談サービス『マネドア』で長期設計を立てる

共働きで世帯収入が増えたタイミングは、家計全体の長期的なプランを見直す絶好の機会です。
しかし、「どこで、誰に相談すればいいかわからない」「相談料が高そう」といった不安から、一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめなのが、無料のオンラインFP相談サービス「マネドア」です。
「マネドア」では、家計の見直しや資産形成、教育資金や老後資金の準備など、お金に関する悩みを専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に何度でも無料で相談できます。
すべてオンラインで完結するため、仕事や家事で忙しい共働き夫婦でも、自宅から好きな時間に気軽に利用できるのが大きな魅力です。
「年収の壁」を越え、家計が大きく変わる今だからこそ、お金のプロの視点を借りて、ご家庭に合った最適なプランを設計してみてはいかがでしょうか。
共働き家族に関するよくある質問

最後に、共働きで妻が収入を増やす際に多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
- 200万円と130万円ならどっちが有利?
-
世帯収入と将来の安心を重視するなら、年収200万円が有利です。
短期的な手取り額だけを見ると、社会保険料の負担がない年収130万円未満の働き方に魅力を感じるかもしれません。
しかし、年収200万円を目指すことで、世帯の手取り収入は年間160万円以上も増えます。
さらに、将来受け取れる厚生年金や、病気やケガで働けなくなった際の傷病手当金など、130万円未満の働き方では得られない大きなメリットがあります。
住宅の購入や子どもの教育、そして自分たちの老後を考えた場合、目先の負担増を乗り越えて年収200万円を目指す方が、ライフプランの選択肢を大きく広げる賢い選択かもしれません。
- 2025年改正で200万円の扱いは変わった?
-
直接的な扱いは変わりませんが、200万円を目指す環境は以前より有利になりました。
年収200万円の方は、2025年の改正前から税金・社会保険の扶養の対象外であったため、その立場に直接的な変更はありません。しかし、重要なのはその周辺の環境です。
- 税制の壁の引き上げ:所得税の壁が103万円から123万円に、配偶者特別控除の満額対象が150万円から160万円に引き上げられました。
これにより、扶養から外れて収入を増やしていく過程での税負担が緩和され、200万円という収入レベルへ、よりスムーズに移行できるようになりました。
- 社会保険の壁の撤廃:将来的には「106万円の壁」自体がなくなる方向です。
これは、国全体として「年収を気にせず働ける社会」を目指している証拠であり、年収200万円を目指す働き方が、今後ますますスタンダードになっていくことを示しています。
つまり、改正によって、より多くの人が「年収の壁」を気にせず、安心して200万円の収入を目指せる環境が整ったと言えます。
- 税制の壁の引き上げ:所得税の壁が103万円から123万円に、配偶者特別控除の満額対象が150万円から160万円に引き上げられました。
家計の不安はプロに相談!無料FP相談サービス「マネドア」で解決

ここまで、共働き家庭における「年収の壁」と、妻の年収200万円が家計に与える影響について解説してきました。
制度は年々複雑に変化しており、「私たちの家庭にとって、一番良い働き方やお金の管理方法はなんだろう?」と、不安や疑問を感じる方も少なくないでしょう。
そんな漠然とした家計の不安は、一人で抱え込まずに、お金のプロに相談するのが解決への一番の近道です。
無料FP相談サービス「マネドア」なら、そんなあなたの悩みに専門家が的確に答えてくれます。
- 扶養から外れた後の、最適な家計の管理方法
- iDeCoやNISAなど、税制優遇を活かした効率的な資産形成
- 教育資金や住宅ローン、老後資金まで含めた長期的なライフプランニング
- 世帯収入が増えた今だからこそ必要な保険の見直し
など、お金に関するあらゆる相談が可能です。
相談は何度でも無料で、すべてオンラインで完結します。
妻の年収200万円というメリットを最大限に活かし、安心で豊かな未来を築くために、まずは気軽にプロの力を借りてみてはいかがでしょうか。