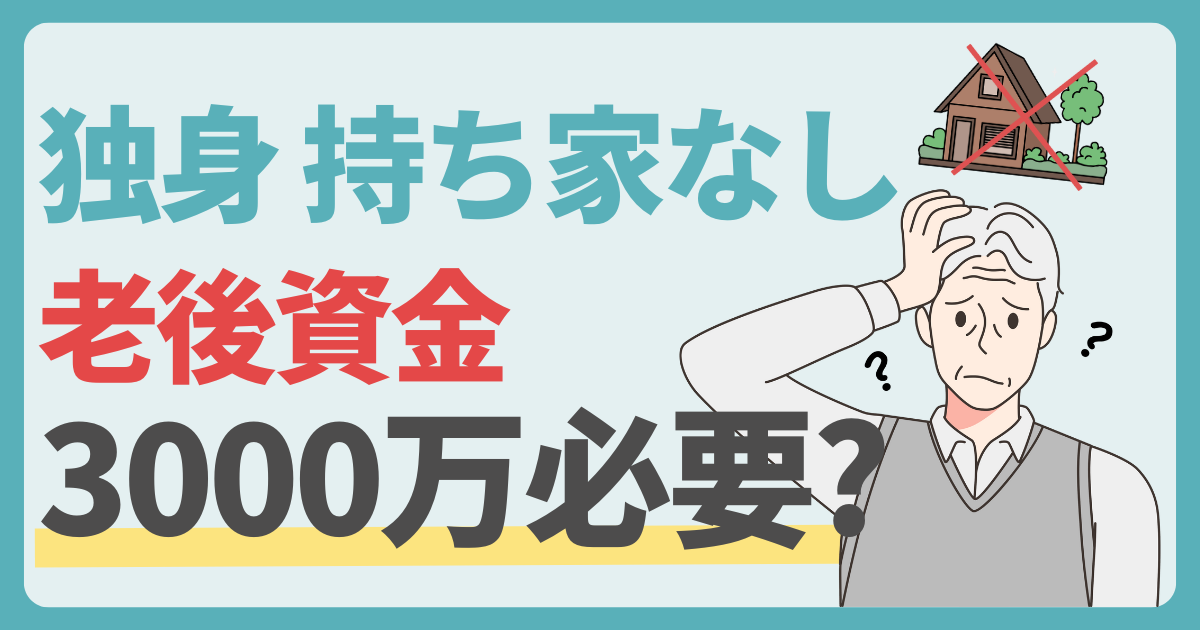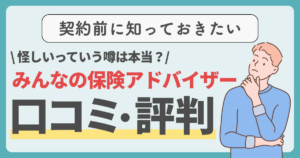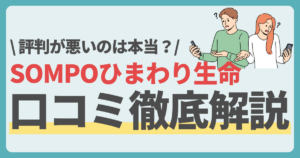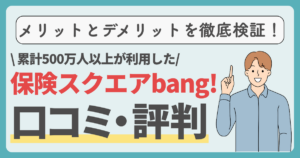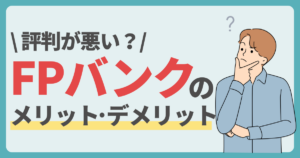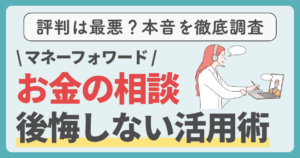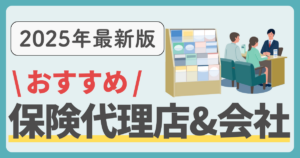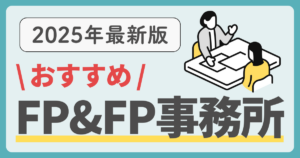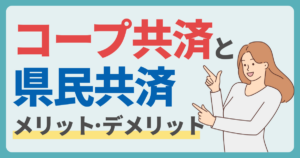「老後に3000万円必要って聞くけど、独身で賃貸暮らしだともっとかかるの?」
「持ち家がないまま年金生活に入ったら不安でしかない…」
そう感じる独身の方は少なくありません。
実際、家賃や医療費などの固定費を払い続ける生活は、想像以上にハードルが高くなります。
この記事では、「独身×賃貸暮らし」の視点から、老後の生活費や年金、必要な貯蓄額をわかりやすく解説。
持ち家との生涯コストの違いにも触れながら、現実的な対策もあわせて紹介していきます。
- 独身・賃貸暮らしの老後に必要な資金はどれくらいか?
- 生活費・年金のリアルな数字とシミュレーション
- 持ち家ありとの違いによる、生涯コストの差
- 老後の不安を軽減するために「今からできること」
- 専門家に相談する際のポイントやおすすめサービス
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
【結論】独身・賃貸派の老後に必要な資金額と年金受給額のリアル

独身で持ち家がない場合、老後の生活には「住居費」という大きな支出が一生ついて回ります。
この住居費の有無が、必要な老後資金に大きな差を生みます。
たとえば、一般的な高齢者の生活費は月14〜16万円と言われていますが、ここに家賃として月6〜8万円が加われば、最低でも毎月20万円以上の支出が想定されます。(総務省統計局 家計調査(家計収支編)より)
つまり、単純計算でも年間240万円、20年間で4,800万円という金額になります。
もちろん、ここには医療費や介護費などの変動費も加わりますし、インフレや住居更新料などの想定外の出費も考慮すべきです。
その一方で、受け取れる年金額は限られており、年金だけで安心して暮らすのは難しいのが実情です。
このあと、具体的な生活費や年金受給額の目安を見ていきましょう。
【生活レベル別】65歳以降の毎月の生活費シミュレーション
独身・持ち家なしで迎える老後は、「どんな生活レベルを目指すか」によって必要な生活費が大きく変わります。
ここでは総務省の家計調査や老後生活の実例を参考に、3つのパターンでシミュレーションしてみましょう。
| 生活レベル | 月額支出(目安) | 主な内訳 |
| 節約生活 | 約16万円 | 家賃(5万円)、食費、光熱費、医療費など最低限 |
| 平均的な暮らし | 約22万円 | 家賃(7万円)、交際費、趣味、交通費など含む |
| ゆとりある生活 | 約28万円 | 家賃(8万円〜)、旅行、レジャー、民間介護費用含む |
たとえば「節約生活」では、都心から少し離れた地域で家賃を抑え、出費を最小限にした暮らしを想定しています。(公益財団法人 生命保険文化センター「生活基盤の安定を図る生活設計」より)
一方、「ゆとりある生活」では、趣味や外食、民間サービスなどにお金をかけた生活スタイルとなります。
今後の年金額や貯蓄と照らし合わせながら、「自分はどのくらいの生活を希望しているのか?」を考えることが老後資金計画の第一歩です。
国民年金・厚生年金、あなたはいくらもらえる?
老後資金を考えるうえで、まず把握すべきなのが「自分がもらえる年金額」です。
日本の公的年金制度には、自営業やフリーランスが加入する「国民年金」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」の2種類があります。
2025年時点での受給額の目安は以下の通りです。(令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況より)
| 年金の種類 | 平均月額(目安) | 備考 |
| 国民年金のみ | 約5万5,000円 | 40年間きっちり収めた場合の想定額 |
| 厚生年金あり | 約14万5,000円 | 平均的な収入で40年就業した場合の想定額 |
たとえばフリーランスなどで国民年金のみの場合、家賃や生活費を年金でまかなうのはかなり厳しい現実があります。
一方、厚生年金に加入していた人でも、都内の賃貸住宅で暮らし続けるとなると、生活に余裕があるとは言えません。
この年金額と、先ほどの生活費シミュレーションを照らし合わせると、「毎月数万円〜十数万円の赤字」が発生する人も少なくないのです。
したがって、「年金だけでは足りない分」をどう準備するかが、老後資金計画のカギになります。
持ち家ありとの生涯コスト差は「家賃分」だけではない
「老後に持ち家があるかどうか」で、かかる生活費は大きく変わります。
賃貸派の場合、老後も家賃を支払い続ける必要があり、これが最大のコスト差に見えますが、実はそれだけではありません。
まず、65歳以降に20年間賃貸で暮らした場合の家賃総額を試算すると、月8万円の家賃でも1,920万円、月10万円なら2,400万円にものぼります。
一方で持ち家の場合、ローンを完済していれば家賃こそかかりませんが、修繕費・固定資産税・管理費などで月1〜2万円程度の出費は続きます。さらに築年数が古くなるほど、リフォームや建て替えの必要が出ることも。
加えて、賃貸は引越しができる柔軟性がありますが、高齢になると入居のハードルが上がるリスクもあります。
「更新時に退去を求められる」「高齢者不可の物件が増える」など、住まいの確保が不安定になる可能性もあるのです。
つまり、老後の住まいにかかるお金と安心感は「単なる家賃」だけで比較できるものではありません。
自分にとってどの住まい方がリスクを抑えられるか、早いうちから考えておくことが大切です。
独身で持ち家なしだと老後に不安を感じるのはなぜ?
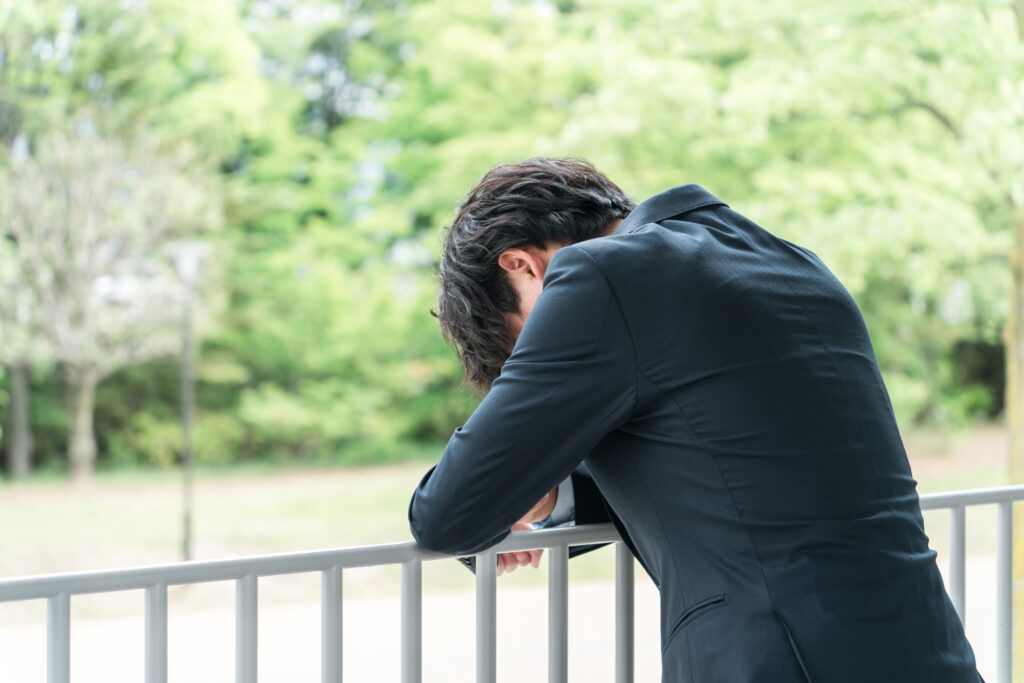
年齢を重ねるごとに「このまま一人で老後を迎えて大丈夫だろうか」と不安を抱く独身の方は少なくありません。
特に賃貸暮らしの場合、家賃や介護の問題、生活費の見通しなど、不確定な支出が多くなりやすいため、不安の種は尽きません。
ここでは「なぜ独身で持ち家がないと老後が不安になりやすいのか?」を、具体的な視点から整理していきます。
不安の正体を知ることで、今からできる対策も見えてくるはずです。
住む場所・介護・生活費など将来が見えないコストが多い
独身で持ち家がない場合、「この先、どこで、どう暮らしていくのか」が明確に見えづらいのが最大の不安要因です。
賃貸暮らしだと、高齢になったときに「物件を借りられるか」「家賃を払い続けられるか」といった住居の問題が現実的なリスクになります。
さらに、介護が必要になった場合の施設入居費や在宅介護費用も、具体的な金額が読みにくいもの。
生活費自体も、物価の上昇や医療費の増加によって、想定より大きく膨らむ可能性があります。
持ち家があれば「住まいに関する支出」はある程度限定されますが、賃貸の場合はずっと固定費が続く上に、環境の変化に大きく影響されるのです。
こうした「将来が見通せないコストの多さ」が、老後不安をさらに強めています。
頼れる家族がいないと何が起きる?
独身で老後を迎える場合、介護や急病などの場面で「誰に頼るか」が現実的な課題になります。
たとえば、突然の入院が必要になったとき、手続きをしてくれる家族がいないと、入院そのものがスムーズに進まないケースもあります。
さらに、介護が必要になった場合も「誰が手配するか」「どこに入るか」「どこまで支援を受けられるか」などの判断を一人で背負うことになります。
加えて、認知機能が低下した場合など、判断能力が不十分になったときの財産管理や意思表示についても、後見人制度などの備えが必要です。
また、孤独死や事故などへの漠然とした不安を抱えやすいのも事実。
だからこそ、家族がいない前提で「第三者に頼る体制」や「公的サービスの活用」を想定しておくことが、独身の老後では特に重要になります。
「備えがない」ことが不安を増やす最大の要因
老後に対する不安の正体は、必ずしも「お金が足りないこと」だけではありません。
実際には、「自分がどれくらい必要で、何を準備すべきかがわからない」状態こそが、不安の元になっているケースが多いのです。
特に独身で持ち家がない場合、「家賃は払い続けられるか」「病気や介護にどこまで対応できるか」といった生活の基盤が不透明になりがちです。
この“不透明さ”こそが、漠然とした不安を引き起こします。
しかし、将来に向けて想定される支出を把握し、備えの道筋を立てておくだけでも、気持ちは大きく変わります。
現実を知ることで初めて、「今できること」が見えてくるのです。
「備えがないから不安」ではなく、「備えるから安心」へと意識を切り替えることが、老後の安心感につながります。
持ち家なし独身の老後、最大のリスクは「住まい」の問題

「お金さえあれば、老後も何とかなる」と思いがちですが、独身・賃貸暮らしの方にとって一番のリスクは「住まい」です。
年を重ねるにつれて住宅選びの選択肢は狭まり、「今のように気軽に借りられない」という現実が待ち受けています。
老後生活の安定には、継続して安心できる「住まい」の確保が欠かせません。
ここからは、賃貸暮らしだからこそ直面しやすい課題と、その対策を見ていきましょう
高齢になると賃貸契約が難しくなる「賃貸難民」問題
高齢者になると、健康面や収入面を理由に、賃貸契約を断られるケースが増えてきます。
オーナー側としては「家賃を滞納されないか」「孤独死などトラブルが起きないか」などを懸念し、貸し渋る傾向があるのです。
その結果、「住みたい場所に住めない」「更新を断られる」といった“賃貸難民”状態に陥ることも。
これは独身で家族の支援が得られない人ほど深刻です。
今のうちから将来も借りられる物件の種類や条件を知っておくことが、安心な老後への第一歩となります。
保証人がいない…どう乗り越える?
高齢者が賃貸を借りる際、ほぼ必ず求められるのが「連帯保証人」です。
しかし、独身者には頼れる家族や親戚がいないケースも多く、「保証人がいないから借りられない」という壁に直面することもあります。
その場合、選択肢となるのが「保証会社の利用」や「自治体・社会福祉協議会の保証支援制度」。
また、自治体によっては高齢者の住まい支援に積極的なエリアもあります。
将来困らないためにも、今のうちから「誰を頼るか」「どこを利用できるか」を具体的にリサーチしておくことが重要です。
選択肢を知っておこう!UR賃貸やサ高住という選択肢
高齢になっても住み続けられる「高齢者歓迎」の住まいとして、代表的なのがUR賃貸やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)です。
UR賃貸は保証人不要・礼金ゼロの物件もあり、年金収入でも入居しやすい制度設計。
サ高住は介護施設ではないものの、見守りや生活支援サービスが付いており、「一人暮らしが不安だけど自立した生活は続けたい」方にぴったりです。
こうした“老後向け住宅”の存在を知っておくことで、「どこに住めるのか」という最大の不安が軽減されるでしょう。
【年代別】今日から始める!老後資金準備ロードマップ

「老後資金の準備」と言っても、年代によってできること・やるべきことはまったく異なります。
40代、50代、60代と、それぞれのライフステージに応じた具体的な対策を講じることで、持ち家がなくても安心できる老後を迎えることができます。
ここでは、年代別に「今やるべきこと」をわかりやすく解説していきます。
40代までにしておきたい「生活費の最適化と資産形成」
40代までに取り組みたいのは、「無理のない支出管理」と「コツコツとした資産形成」です。
この時期は収入が伸びやすい一方、住宅ローンなど支出も増えやすく、老後資金の準備が後回しになりがちです。
まず大切なのは、家計の見直しによって月数万円でも老後資金に回せる余剰をつくること。固定費(家賃、保険、通信費など)の見直しが効果的です。
加えて、iDeCoやNISAといった非課税制度を活用することで、効率よく資産を増やす仕組みづくりもしておきましょう。
この時期から積立をスタートしておけば、60代時点で大きな差になります。
「今が生活でいっぱいいっぱいだから」と諦めず、少額でも“未来の自分”への投資を意識することが大切です。
50代は「支出の見直しと住居戦略」がカギ
50代に差しかかると、老後の生活がぐっと現実味を帯びてきます。
このタイミングでの最大のポイントは「支出の整理」と「住まいの戦略」です。
まずは、住宅ローンなどの大きな支出が終わる(または終わりが見える)時期。
浮いたお金をそのまま生活費に使うのではなく、老後資金にスライドさせる意識が大切です。
また、賃貸暮らしの方は、老後の住まいをどうするかを真剣に考え始める時期でもあります。
高齢者歓迎の物件探し、家賃を抑えられる地域への引っ越し、UR賃貸やサービス付き高齢者住宅の情報収集など、今のうちから選択肢を広げておきましょう。
「今は大丈夫」ではなく、「将来困らないための準備」を始めることが、50代からの賢い対策です。
60代以降は「現金・年金・資産のバランス」を重視
60代以降はいよいよ老後本番。
「これまでに貯めた資産をどう取り崩していくか」「年金でどこまで賄えるか」という“出口戦略”が重要になります。
まず意識したいのは、現金(預貯金)・年金・投資資産のバランス。
生活費のすべてを年金でまかなえない場合、不足分をどこから補填するかが課題になります。
預貯金ばかりに頼ると寿命までに資金が尽きるリスクもあるため、資産運用や保険の見直しも含めた“長生きリスク”への備えが不可欠です。
また、高齢期に起こりやすい医療費の増加や介護への備えも重要なテーマ。
まとまった出費に耐えられるよう、数年分の生活費を流動性の高い形でキープしておくこともおすすめです。
今ある資産を「長く安心して使う」ために、定期的な見直しとシミュレーションを怠らないようにしましょう。
貯蓄が苦手でも大丈夫!老後資金を作るための具体的な5ステップ

「貯金が続かない…」「何から始めていいかわからない…」
そんな方でも、少しずつ老後資金を積み上げていく方法はあります。
ここでは、無理なく実践できる具体的な5つのステップをご紹介します。
STEP1|まずは家計簿アプリで「お金の流れ」を把握する
貯蓄の第一歩は、「何にいくら使っているか」を知ることから。
家計簿アプリを使えば、自動連携で日々の支出が可視化されます。
意外と使いすぎている項目や、改善できるポイントが見つかることも。
見える化するだけで、無駄遣いの意識も自然と変わります。
STEP2|スマホ・保険料など「固定費」の見直しから始める
支出の中でも、見直し効果が大きいのが固定費。
スマホ代、サブスク、保険料、光熱費などは、一度見直すだけで年間数万円の節約に。
特に保険は「なんとなく」で入っている人も多いため、定期的なチェックを。
STEP3|新NISAで「ほったらかし積立投資」の仕組みを作る
2024年から始まった新NISAは、老後資金づくりにも心強い制度。
毎月1万円からでも、長期で積み立てていけば大きな資産に育ちます。
インデックスファンドなど手間がかからない商品を選べば、忙しい人でも続けやすいのが魅力です。
STEP4|iDeCo(個人型確定拠出年金)で税金のメリットも得る
iDeCoは積立額が所得控除の対象になるため、節税効果もバッチリ。
老後資金を貯めながら、毎年の税金も減らせる一石二鳥の制度です。
ただし、60歳までは引き出せないため、無理のない範囲での活用を。
STEP5|お金のプロ(FP)に相談し、自分だけの計画を立てる

「自分にどれが合ってるかわからない…」そんなときは、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのが安心です。
収入・支出・希望する生活スタイルにあわせて、あなただけの老後資金プランを一緒に考えてもらえます。
なかでもおすすめなのが、中立な立場で相談に乗ってくれる【マネドア】です。
無料で何度でも相談でき、保険や投資商品の無理な勧誘も一切なし。
オンライン対応なので、忙しい方や遠方にお住まいの方でも気軽に利用できます。
「老後が不安だけど、何から始めればいいかわからない…」そんな方は、まずはマネドアで一歩を踏み出してみるのがおすすめです。
不安の正体を理解し、今日からできる一歩を踏み出そう

「持ち家がない」「独身で老後はひとり」 こうした状況に漠然と不安を抱えるのは、決して特別なことではありません。
その不安の正体を丁寧に見ていくと、実は「情報不足」や「準備の遅れ」から来ることがほとんどです。
生活費、住まい、年金…それぞれにかかる費用と制度を知り、自分のライフスタイルに合った備えを始めることで、将来の見通しはぐっとクリアになります。
老後資金づくりは、今の年齢に関係なく“今日”から始められます。
まずは家計の見直しや制度の確認、無料相談など、できることから少しずつ進めていきましょう。
不安を安心に変える一歩は、いつだって「気づいた今」がスタートラインです。