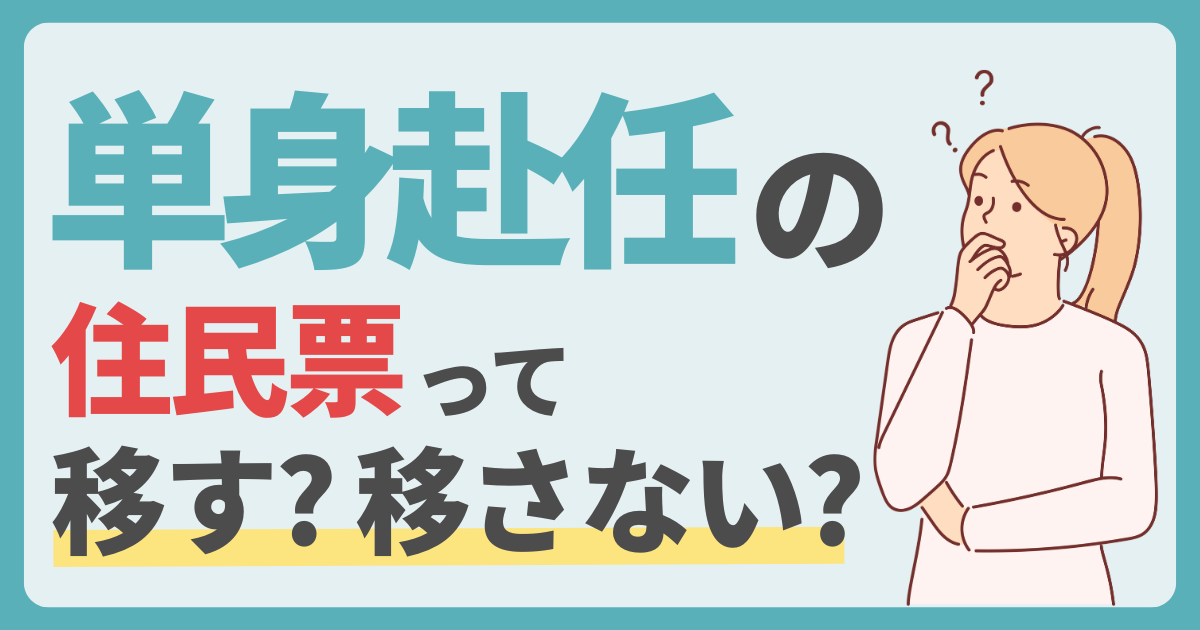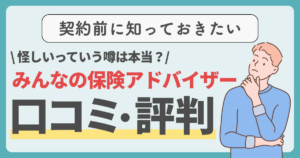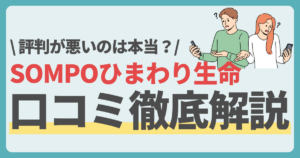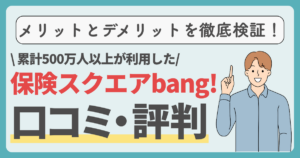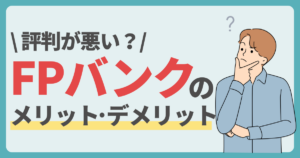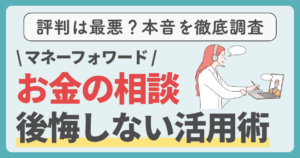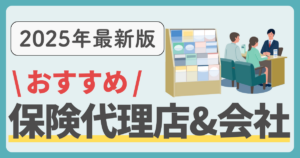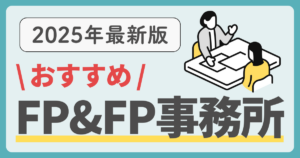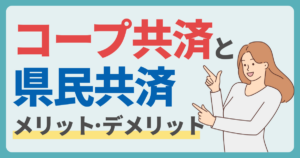「単身赴任が決まったけど、住民票って移したほうがいいの?」
そんな疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
住民票を移すかどうかは、住民税や各種控除、行政サービスに影響する大切な判断です。
にもかかわらず、「なんとなく面倒だから移さない」という人も多く、気づかないうちに損をしてしまうケースも…。
- 単身赴任時の住民票の基本ルールと移動判断のポイント
- 「移す」「移さない」それぞれのメリット・デメリット
- 損をしないための手続き・控除制度の注意点
- 迷ったときに相談すべき専門先とサポートの選び方
自分に合った判断ができるように、最新の制度も踏まえてわかりやすく解説していきます。
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
【結論】単身赴任の住民票、移すべき?

結論から言うと、原則として「実際に生活している場所」に住民票を移すべきとされています。
ただし、すべての単身赴任者が一律に移さなければならないというわけではなく、状況によって適切な判断は異なります。
たとえば、単身赴任が一時的なものであり、生活の本拠が家族のいる元の住所にある場合は、住民票を移さなくても問題ないことも。
一方で、単身赴任先で実質的な生活拠点が長期にわたり続くような場合は、住民票を移すことが求められます。
この章では、住民票の移動に関する法律的な考え方を踏まえながら、「移す or 移さない」の判断軸をわかりやすく整理していきます。
原則は「生活の本拠(拠点)」がある住所に移すのがルール
住民票をどこに置くべきかは、「住民基本台帳法」という法律で定められています。(住民基本台帳法 第22条より)
この法律によると、住民票は「生活の本拠」、つまり実際に生活の中心となっている場所に置く必要があります。
たとえば、単身赴任中に平日は勤務地のアパートで寝泊まりし、週末も月に1回程度しか自宅に戻らないというような場合は、赴任先が「生活の本拠」とみなされる可能性が高いです。
一方で、あくまで一時的な出向であり、家族のいる自宅に定期的に戻り、住民サービスも受けているといったケースでは、元の住所が生活の本拠とされることもあります。
「どちらに住民票を置くべきか」は、その人のライフスタイルや住まいの利用実態によって判断されるため、一概には決められません。
後のトラブルを防ぐためにも、「生活の本拠」がどちらかを冷静に見極めることが重要です。
あなたはどっち?「移すvs移さない」判断の分かれ目(赴任期間・家の状況など)
住民票を「移す」「移さない」の判断は、法律上の原則だけでなく、実際の生活状況や今後の予定にも大きく左右されます。
以下のようなポイントをチェックして、自分にとってどちらが妥当かを整理してみましょう。
| 判断ポイント | 住民票を移す方がよいケース | 住民票を移さない方がよいケース |
| 赴任期間の長さ | 1年以上の長期予定(会社からも明確に通知されている) | 数ヶ月〜1年未満の短期 |
| 家族の居住地 | 単身で完全に別居する(家族が本宅に残る) | 配偶者・子どもが本宅に居住し続けている |
| 生活の拠点(本拠) | 平日は常に赴任先に滞在/生活の中心が赴任先になる | 週末は本宅へ帰るなど、生活の中心が変わらない |
| 行政手続きのしやすさ | 転入届・国保加入・印鑑登録などを赴任先で済ませたい | 現住所で手続きを継続したい(免許・保険など) |
| 住宅ローン控除の継続 | 特になし(本宅を離れていても問題なし) | 本宅の住民票が条件になるため、移さない方が無難 |
| 選挙や地域サービス | 赴任先で受けたい(選挙投票、自治体健診など | 本宅での投票やサービス利用を続けたい |
「住民票を移さない」場合のメリット・デメリット一覧
単身赴任中でも住民票を本宅に置いたままにする選択は、比較的多くの人が取っている方法です。
理由はシンプルで、家族と同じ世帯に籍を置いていた方が手続きが楽で、税制上も有利になることが多いためです。
とはいえ、デメリットもゼロではありません。以下に、住民票を移さない場合の主なメリットとデメリットを一覧で整理しました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 家族と同一世帯を維持できる 住宅ローン控除など、居住要件がある制度に引き続き対応できる 扶養手当や家族向け制度をそのまま適用できる 転出・転入の手続きを省ける | 赴任先での行政サービスが難しい 選挙の投票などを赴任先で行えない可能性がある 実際の居住地と住民票の住所が異なるため、各種申請が煩雑になる 自治体の住民サービス(健診・予防接種等)を受けづらい |
結論としては、「短期赴任」「家族が本宅に居住」「税制メリットを優先したい」場合には、住民票を移さずに維持する方が合理的です。
一方、赴任先での手続きや生活が煩雑になる可能性もあるため、状況に応じて慎重に判断しましょう。
「住民票を移す」場合のメリット・デメリット一覧
単身赴任先に住民票を移すと、「実際に住んでいる場所と公的記録が一致する」ことから、各種手続きがスムーズになるという利点があります。
一方で、住宅ローン控除や扶養手当など、居住地に関わる制度上の不利が生じるケースもあるため、選択には注意が必要です。以下に主なメリット・デメリットをまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 赴任先での行政手続きが容易 選挙の投票が赴任先でできる 国民健康保険や介護保険などの加入・手続きがスムーズ 居住実態との整合性が取れてトラブルを避けやすい | 住宅ローン控除など「居住要件」のある制度が受けられなくなる可能性 家族と同一世帯でなくなる(扶養手当や配偶者控除等に影響する場合) 転出・転入の手続きが必要で、手間がかかる 赴任が短期の場合、再転居時に再度の住民票移動が発生する |
「住民票を移す」選択は、長期赴任で単身生活が明確に続く場合に向いています。
生活基盤が明確に赴任先に移ったと見なされるなら、各種手続きやトラブル回避のためにも住民票を移す方が合理的です。
ただし、制度上のデメリットがないか事前に確認しておくことが重要です。
一番知りたい!単身赴任中の住民税、3つの基本ルール

単身赴任中の住民票の扱いは悩ましいものですが、実は住民税に関しては「明確なルール」が定められています。
特に納税先の自治体や金額、重複して請求されるリスクなど、多くの方が不安に思う点を整理すれば、手続きや判断もスムーズになります。
ここでは、知っておくべき「住民税の3つの基本ルール」をわかりやすく解説します。
ルール①:納税先は「1月1日時点の住所地」で決まる
住民税の課税自治体は、「その年の1月1日時点で住民票があった市区町村」によって決まります。(総務省 地方税制度|個人住民税より)
これは全国共通のルールであり、たとえその後に引っ越しや単身赴任で別の自治体に移動しても、納税先は1月1日時点の自治体のままとなります。
たとえば、1月1日に東京都に住民票があれば、その年の住民税は東京都が課税主体となります。
4月に大阪へ単身赴任して住民票を移したとしても、当年の住民税は東京都へ納めることになります。
つまり、単身赴任の住民票を移すかどうかに関係なく、その年の住民税の納税先は「年始の住所」で固定されるという点を押さえておくと安心です。
ルール②:赴任時期によって納税先はこう変わる
住民税は「1月1日時点の住所地」で課税されるとお伝えしましたが、赴任のタイミングによって納税先がどう変わるか、具体例で見てみましょう。
| 赴任時期 | 住民票の移動 | その年の納税先 | 翌年の納税先(住民票がそのままの場合) |
| 1月以前に赴任 | 移動あり | 赴任先自治体 | 赴任先自治体 |
| 1月中に赴任 | 移動あり | 元の住所地 | 赴任先自治体 |
| 2月以降に赴任 | 移動あり | 元の住所地 | 赴任先自治体 |
| 4月に赴任(移動なし) | なし | 元の住所地 | 元の住所地(引き続き住民票があるため) |
このように、「いつ住民票を移動したか」によって、住民税の納税先が変わります。
特に1月中に引っ越す場合でも、住民票の異動が1月1日を過ぎていると、その年の住民税は元の自治体に納める必要があります。
単身赴任では「住民票はそのまま、実際の居住地だけ赴任先」というケースも多いため、課税自治体が変わらないまま数年間過ごすことも珍しくありません。
納税先を変更したい場合は、住民票の異動タイミングに注意が必要です。
ルール③:二重課税(二重請求)されることは絶対にない
単身赴任で「住民票を移していない」「実際の生活拠点は別にある」といったケースでは、「元の住所地と赴任先の両方から住民税を請求されるのでは?」と心配になる方も多いかもしれません。
しかし、安心してください。
住民税は「1月1日時点で住民票があった市区町村のみ」が課税できると法律で定められており、
二重課税(二重請求)は起こりません。
例えば、4月に転勤し、住民票を移さなかった場合でも、1月1日時点の元の住所地からのみ課税され、赴任先での課税はありません。
ただし、注意したいのは以下のようなケースです
- 住民票の異動手続きを怠り、自治体間で情報の行き違いが起こる
- 勤務先が異動先自治体に「特別徴収(給与天引き)」の届け出をしてしまう
こうした場合、一時的に二重請求のような通知が来ることもあります。
ですが、これは制度的なミスではなく、事務手続きの齟齬による誤りです。
このような場合は、早めに両自治体の税務課に連絡を取り、事情を説明すれば解決します。
「二重に税金を払わされたままになる」ということは制度上ありませんので、過剰に心配しすぎず、落ち着いて対応しましょう。
住民票の異動は必要?単身赴任の例外ルールとは?

「単身赴任って、住民票を移さなきゃいけないの?」
この疑問、実は多くの方が抱える悩みです。
住民基本台帳法では、「引越しから14日以内に住民票を異動すること」が原則とされていますが、単身赴任の場合は少し事情が異なります。
実は、家族がそのまま元の住所に住み続けているなど、“生活の本拠”が引き続き元の住所にあると判断される場合は、住民票を移さなくても問題ないケースが多いのです。
この章では、そんな「単身赴任における住民票の例外的な取り扱い」について、制度の根拠や役所とのやりとりの注意点を交えながらわかりやすく解説します。
法律上のルールと「正当な理由」がある場合の扱い
住民基本台帳法では、「転居後14日以内に住民票を異動すること」が定められています。(住民基本台帳法 第22条・第23条(転入届・転出届の期限規定)より)
これはあくまで“生活の本拠”が移った場合に適用される原則です。
しかし単身赴任のように、一時的に仕事の都合で住居を移すケースでは、「元の住所に家族が暮らし続け、生活の基盤が変わらない」と判断されれば、住民票を移さなくても法的な問題はないとされています。
役所ごとに判断が異なる場合もあるため、異動届を出さない場合には「単身赴任による一時的な転居であること」や「生活の拠点は変わっていない」ことを明確に伝えるとスムーズです。
住民票を移さずに暮らすことのメリットとリスク
単身赴任先で住民票を移さずに元の住所に置いたままにすることで、いくつかのメリットがあります。
たとえば、
- 家族と同じ世帯に属し続けることで手続きが簡単
- 子どもの学校や保育園の手続きがスムーズ
- 住宅ローン控除や扶養控除の継続に影響が出にくい
一方で、リスクや注意点も無視できません。
- 赴任先で住民票がないと行政サービスが受けにくい
- 本拠地を巡る判断により、税務署や役所とのやりとりが複雑になる可能性
- 緊急時の連絡先として不都合が生じることも
このように「メリットだけを見て決める」ことには注意が必要です。
どんなケースなら住民票を移すべき?
次のような状況に当てはまる場合、住民票を移すことを検討したほうが無難です。
- 赴任期間が長期にわたると見込まれる場合(2年以上など)
- 単身赴任先に完全に生活の拠点を移す場合
- 元の家に誰も住まなくなる場合
- 赴任先で行政手続きや公的サービスの利用が頻繁にある場合
これらに当てはまる方は、住民票を移しておくことで後々のトラブルを防げます。
特に税金・保険・選挙関連の通知を確実に受け取る必要がある人は、慎重な判断が求められます。
税金や控除への影響は?単身赴任で知っておきたい制度

単身赴任は、住民票や生活スタイルだけでなく「税金」や「控除制度」にも影響を及ぼすことがあります。
特に、住宅ローン控除・扶養控除・手当の課税といった制度は、住民票をどうするかによって適用の有無が変わることも。
正しく理解しておかないと、せっかく受けられるはずの控除が受けられなかったり、あとから追徴課税を受けてしまうこともあるので注意が必要です。
ここでは、見落とされがちな税金と控除のポイントを整理して解説します。
住宅ローン控除は引き続き受けられるの?
原則として、住宅ローン控除は「居住の用に供していること」が要件です。
つまり、「実際に住んでいること」が必要になります。
しかし単身赴任の場合、家族がローンの対象となる住宅に住み続けていて、本人がやむを得ず一時的に他の場所で生活している場合は、「居住の継続性がある」とみなされて控除対象が維持されるケースが多いです。(国税庁 No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等より)
ただし、これは税務署の個別判断に委ねられることもあるため、念のため確定申告時に「単身赴任であること」を明記し、家族が住んでいる証明書類(住民票や水道光熱費の明細など)を用意しておくと安心です。
配偶者控除や扶養控除は変わらない?
単身赴任によって夫婦別居になっても、配偶者控除や扶養控除は「生計を一にしている」ことが確認できれば継続可能です。(国税庁 No.1180 扶養控除より)
たとえば、生活費を仕送りしていたり、家族名義の口座から家計を管理しているなど、経済的に一体となっている実態があれば、たとえ別居していても「生計を同じくしている」とみなされます。
ただし、控除対象者の所得条件(配偶者控除なら年収103万円以下など)を満たす必要はありますので、所得状況とあわせてしっかり確認しておきましょう。
単身赴任手当や帰省手当の課税扱いについて
企業から支給される「単身赴任手当」「帰省旅費手当」などは、課税対象になるものと非課税のものが混在しています。
- 【課税対象】単身赴任手当(給与とみなされるため、所得税・住民税の課税対象)
- 【非課税対象】月1回の帰省旅費(合理的な範囲内であれば非課税扱い)
特に注意したいのは、会社の制度によっては手当の名目があいまいで、課税・非課税の判断が難しい場合がある点です。
不安がある場合は、会社の人事・総務部に確認しておくと安心ですし、確定申告で誤った申告を防ぐことにもつながります。
健康保険や児童手当はどうなる?家族への影響は?

単身赴任で本人だけが住民票を異動させる場合、家族に関わる公的制度にも影響が及ぶことがあります。
たとえば、健康保険証の発行先、児童手当の受給者、住民票上の世帯主や続柄の変化など細かい手続きが意外と多く発生します。
知らずに放置すると、医療機関で保険証が使えなかったり、児童手当が受け取れなかったりといったトラブルにもつながりかねません。
ここでは、家族の生活に影響を与えやすいポイントを事前にチェックしておきましょう。
健康保険証・国民年金の住所は変更が必要?
会社員であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているケースが多く、住所変更の手続きは会社経由で行うのが基本です。
一方、国民健康保険や国民年金に加入している家族がいる場合は、住民票の移動とあわせて住所変更の届け出が必要になります。
特に注意したいのが、健康保険証の送付先や有効範囲です。
本人が別居することによって、家族の医療機関での受診時にトラブルが起きないよう、必要に応じて保険証の再発行や送付先の確認をしておきましょう。
児童手当の手続きに影響はある?
児童手当は、原則として「受給者(主に所得が高い方の親)の住民票がある市区町村」から支給されます。
そのため、受給者本人が単身赴任などで他の市区町村へ住民票を移す場合は、赴任先の市区町村で新たに児童手当を申請する手続きが必要です。元の市区町村での受給資格は、転出日をもって消滅します。(こども家庭庁 児童手当Q&Aより)
この新しい申請は、転出予定日から15日以内に行う必要があります。手続きが遅れると、手当を受けられない月が発生する場合がありますので注意が必要です。
手続きに不備があると支給が一時的に止まる可能性もあるため、事前に引越し元と引越し先の両方の自治体に確認しておくと安心です。
世帯主変更や住民票分離の注意点
単身赴任で住民票を異動させると、住民票の「世帯主」や「続柄」の変更が必要になることがあります。
たとえば、夫が単身赴任して別住所に移ると、元の住所に残る家族(妻や子ども)は自動的に「世帯主不在」となるため、妻を新たな世帯主として登録する必要が出てきます。
また、住民票を分けることで、扶養関係や自治体独自の制度(保育料や医療費助成など)に影響が出るケースも。
特に、児童手当や保育園の入園申請などで「同一世帯であること」が条件とされている場合は、世帯分離により条件を満たさなくなる恐れがあります。
こうした変化に伴う手続きを正しく行うことで、家族が受け取れる行政サービスを確保し、トラブルを防ぐことができます。
【重要】住民票を移す場合の手続き完全マニュアル

単身赴任にともない住民票を異動させる場合、事前・事後でしっかりとした手続きが必要です。
「時間がないから後回し…」と放置してしまうと、役所での申請が二度手間になったり、行政サービスの不備に繋がるおそれも。
ここでは、住民票を移す際に必要な流れをSTEP形式でわかりやすく解説します。
出発前〜新生活スタートまで、抜け漏れなくチェックしておきましょう。
STEP1:【引越し前】転出届を出す
まず、現在住んでいる自治体に「転出届」を提出します。
これは、住民票を新住所へ異動する意思を自治体に伝える重要な手続きです。
| 提出先 | 現在の市区町村役所 |
| 提出期限 | 引越し予定日の14日前から可能 |
| 必要なもの | 本人確認書類、マイナンバーカード、印鑑(自治体による) |
転出届の提出後、「転出証明書」が発行されます。この証明書は、次のステップである転入手続きに必要となるため、必ず保管しておきましょう。
STEP2:【引越し後】転入届を出す
新居に引越した後は、新しい自治体で「転入届」を提出します。
この手続きにより、正式に住民票が新住所へ異動されます。
| 提出先 | 新居の市区町村役所 |
| 提出期限 | 引越し予定日の14日前から可能 |
| 必要なもの | 転出証明書、本人確認書類、マイナンバーカードなど |
この転入手続きを忘れると、住民票上「住所不定」になるリスクもあるため、速やかに済ませましょう。
転入届の提出と同時に、印鑑登録やマイナンバーの住所変更なども行えます。
STEP3:【忘れずに】関連手続きの住所変更リスト
住民票の異動だけでなく、関連する各種制度・サービスの住所変更も忘れずに行いましょう。
以下のような手続きは、自治体とは別窓口となることが多いため、チェックリスト形式で確認しておくと便利です。
| 手続き対象 | 手続き方法 |
| 健康保険証 | 勤務先 or 市区町村で住所変更を届け出 |
| 運転免許証 | 警察署または運転免許センターで記載変更 |
| 銀行口座 | 郵送またはオンラインで手続き可能 |
| 郵便物の転送 | 郵便局にて「転居届」を提出 |
| マイナンバーカード | 転入届時に自動で住所変更される |
また、扶養や児童手当などに関する自治体独自の制度を利用している場合、別途申請が必要になるケースもあるため、忘れずに確認しましょう。
単身赴任の不安を専門家に相談する選択肢も

住民票の異動や税金・保険の手続き、控除の取り扱いなど、単身赴任には「家を離れる不安」だけでなく、制度面の悩みや負担がつきものです。
特に、家計や手当、控除の制度が絡む内容は、自分だけで判断しようとするとミスにつながることも。
そんなときこそ、制度に詳しい専門家のサポートを活用することで、不安を軽減できます。
家計の二重負担をどう乗り切る?
単身赴任になると、生活費が二重にかかるケースがほとんどです。
たとえば、家族のもとに家賃・光熱費・食費がかかる一方で、自分の赴任先にも同様の生活費が発生する。
さらに交通費や帰省費用なども積み重なるため、想定以上に負担が膨らむこともあります。
こうした状況に備えて、家計の見直し・節約方法・制度の活用策を事前に整理することが大切です。
必要であれば、FP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家に「二重生活の家計シミュレーション」を依頼するのも一つの方法です。
控除・手当・保険制度の活用に不安がある方へ
単身赴任では、「配偶者控除や扶養控除が使えるのか」「住宅ローン控除に影響はないか」など、税金面での疑問が多く寄せられます。
また、児童手当や健康保険の手続きにも注意が必要です。
こうした制度は「細かい条件の違い」で適用・非適用が分かれることも多く、自分で判断するのは難しいケースが少なくありません。
迷ったときは、早めに専門家に相談し、損や漏れのない手続きを進めるのが賢明です。
無料で相談できるサービス「マネドア」も検討してみよう

「専門家に相談したいけど、お金がかかりそうで不安…」
そんな方には、無料で何度でもFP相談ができる『マネドア』がおすすめです。
マネドアでは、住宅費・保険・税金・扶養など幅広いテーマについて、完全中立の立場でサポートしてくれるファイナンシャルプランナーとオンラインで相談が可能。
予約もスマホで簡単に行え、土日や夜間も対応しているため、仕事が忙しい単身赴任中の方にもぴったりです。
「正しい手続きをしたいけど不安」「損しない制度活用を知りたい」といった場合は、ぜひ一度試してみてください。