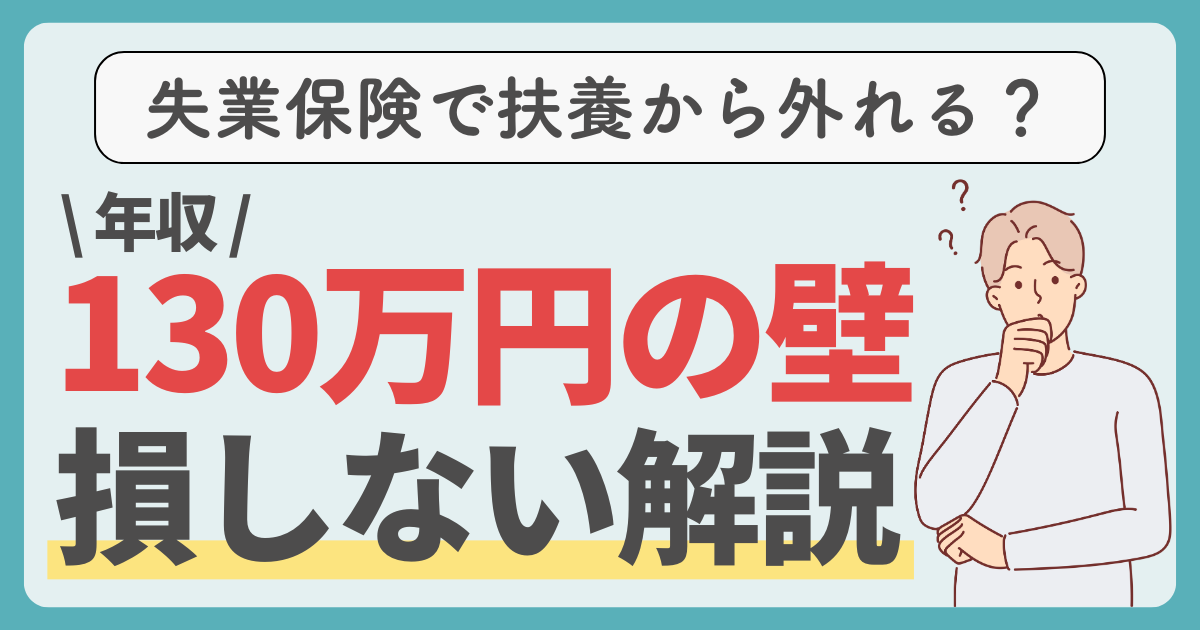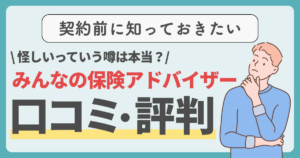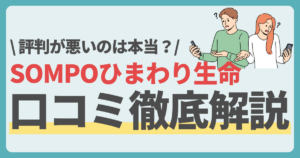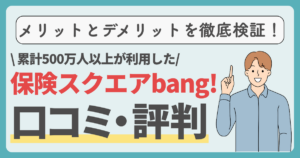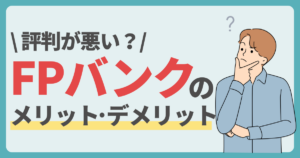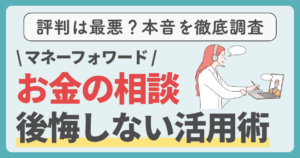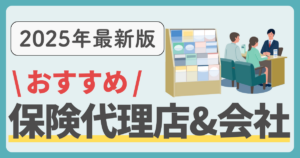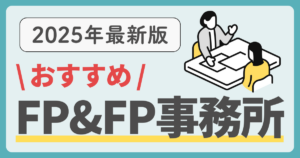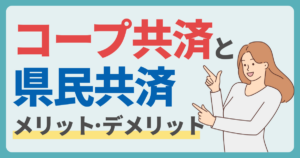「失業保険をもらったら、配偶者の扶養から外れちゃうの?」
そんな不安を感じている方は少なくありません。
健康保険や税金の制度は複雑で、間違った判断をすると思わぬ負担が発生することも。
とくに、失業中に配偶者の健康保険に入っていたり、税金面で扶養に入っている方にとっては、失業保険の受給がどんな影響を与えるのか知っておくことが大切です。
- 失業保険を受け取ると扶養から外れるケースとは?
- 健康保険と税制上、それぞれの扶養で何が変わるのか
- 扶養を外れた場合のデメリットや注意点
- 扶養内にとどまるための対策と制度の活用方法
- 不安がある人におすすめの無料相談サービス
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
【結論Q&A】失業保険と扶養、みんなの疑問にまずお答え!
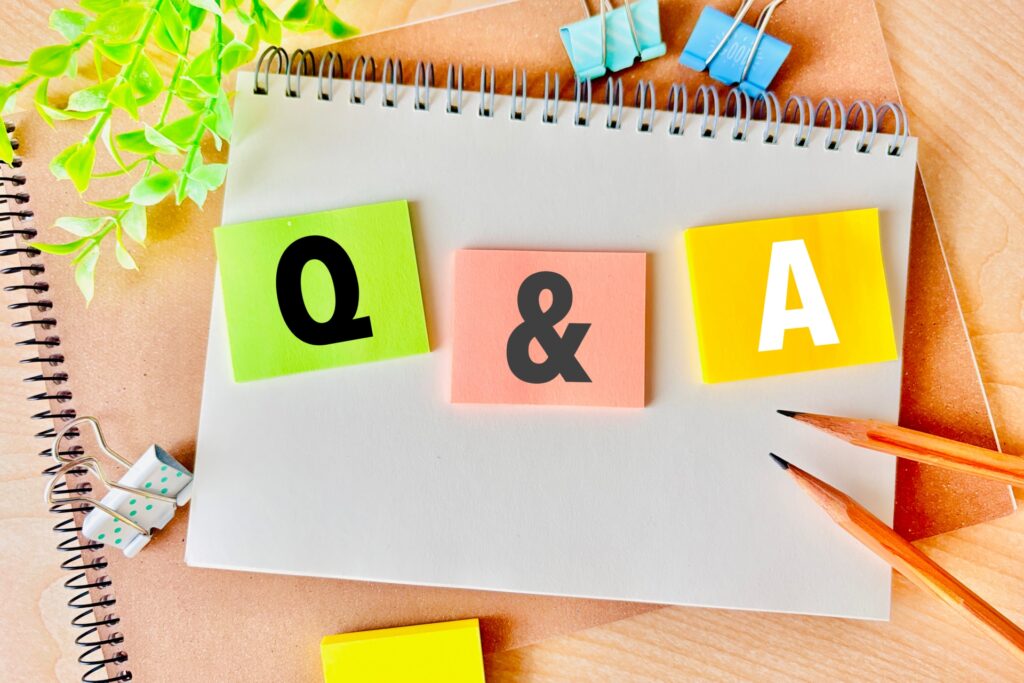
失業保険と扶養制度の関係は、思ったよりも複雑です。
「失業したら自動的に扶養を外れるの?」「保険と税金、どっちに影響が出るの?」といった疑問を抱える方は多く、ネット上の情報も断片的で混乱しがちです。
まずは、よくある3つの質問にお答えしながら、制度の全体像をイメージしていきましょう。
Q. 失業保険をもらうと、扶養から外れる?
健康保険の「被扶養者」の条件に影響が出る可能性があります。
健康保険においては、被保険者(たとえば配偶者)の扶養に入っている場合、失業保険の「基本手当日額 × 30日分」が月額108,333円を超えると、扶養の認定基準を満たさないと判断されることがあります。(日本年金機構より)
そのため、失業保険をもらっている期間中、一時的に扶養から外れ、自分で国民健康保険などに加入する必要が出てくるケースもあります。
Q. 税金の扶養はどうなるの?
税制上の「扶養控除」は、失業保険の金額次第で維持できる可能性もあります。
所得税や住民税の扶養控除においては、失業保険の給付は「雑所得」としてカウントされるため、その合計額が年間48万円を超えるかどうかが判断基準になります。
たとえば、失業保険の受給額が少ない、または支給期間が短ければ、控除対象配偶者のまま扱われる可能性もあるため、健康保険の扶養よりもやや条件は緩やかです。
Q. 扶養から外れると、どうなるの?
保険料の自己負担や税金面での控除喪失など、家計への影響が出てくる可能性があります。
健康保険の扶養から外れると、自分で保険料を支払う必要があるため、国民健康保険や任意継続被保険者制度への切り替え手続きが必要です。
また、税制上の扶養控除から外れることで、配偶者の所得税や住民税の負担が増えることもあります。
このように、扶養から外れることで発生する金銭的・手続き的な負担を事前に理解しておくことが大切です。
失業保険と扶養の関係とは?
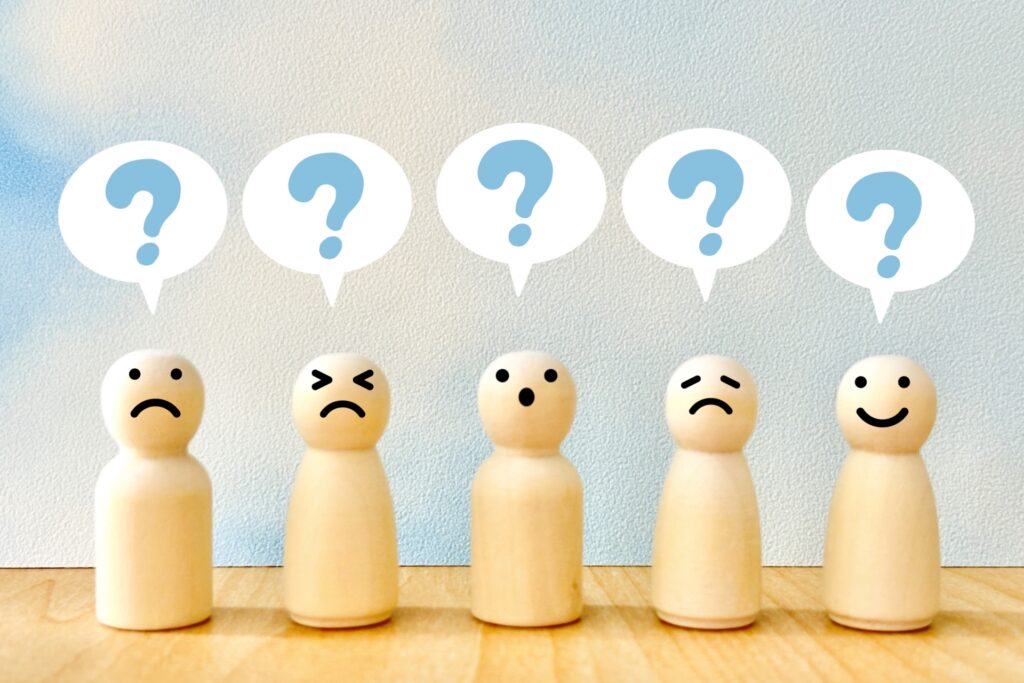
失業中に「配偶者の扶養に入っている」という人は少なくありません。
しかし、失業保険を受給することによって「扶養から外れるのでは?」と心配になるケースも。
そもそも「扶養」とは何を指し、どんな制度上の意味があるのでしょうか?
まずは、健康保険と税金、それぞれの観点から「扶養」の仕組みを整理しておきましょう。
そもそも「扶養」とは何を指すの?
「扶養」とは、経済的に家族のサポートを受けて生活している状態を指し、主に健康保険と税金(所得税・住民税)の2つの制度に関わります。
ただし、両者で「扶養」の定義や条件が異なるため、「どちらの扶養から外れるのか?」「どちらには影響がないのか?」を混同しやすい点に注意が必要です。
この章ではまず、「健康保険上の扶養」と「税制上の扶養控除」がそれぞれどのような仕組みなのかを見ていきましょう。
健康保険における「扶養」とは?
健康保険における「扶養」とは、被保険者(たとえば会社員の配偶者など)が保険料を負担することで、配偶者や子どもなどが保険料を払わずに健康保険に加入できる仕組みです。
被扶養者として認められるには、以下のような条件があります。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)
- 被保険者の収入の1/2未満であること
- 同居・仕送りなどの条件もチェックされる
失業保険を受け取ると、この「年間収入130万円未満」という基準を超えることがあり、扶養から外れて自分で保険料を払う必要が出てくる場合があります。(全国健康保険協会(協会けんぽ)「被扶養者とは?」より)
税制上の「扶養控除」とは?
税制における「扶養」とは、納税者が生計をともにする家族を扶養している場合に所得税・住民税の軽減が受けられる制度です。
具体的には、以下の条件を満たすと、配偶者や子ども・親などを扶養家族として「扶養控除」の対象にできます。
- 扶養される人の年収が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)
- 納税者と生計を一にしていること
- 他の人の扶養に入っていないこと
失業保険を受給すると、この「年収48万円(給与換算103万円)」の基準を超える可能性があり、所得控除の対象外になる=納税額が増えることがあるため注意が必要です。(国税庁 No.1180 扶養控除より)
失業保険をもらうと扶養から外れるの?
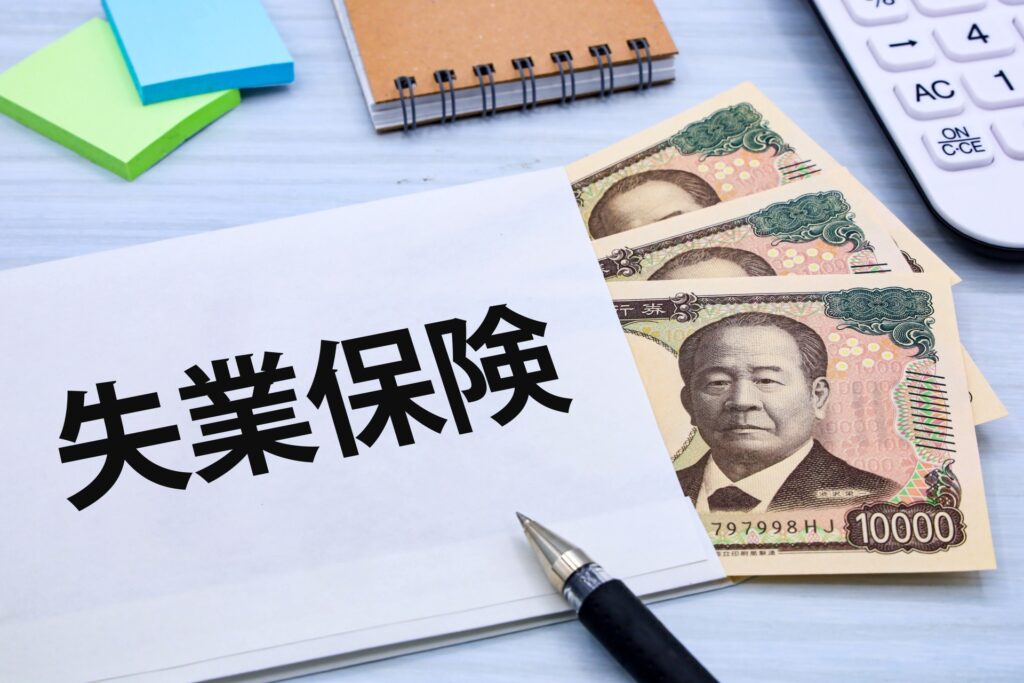
「失業保険を受け取ったら、配偶者の扶養から外れるって本当?」
そんな不安を抱える方は多いものです。
実は、扶養から外れるかどうかはもらう金額や受給期間、扶養の種類(健康保険 or 税制)によって変わってきます。
ここでは、どのような条件で「扶養の範囲内」にとどまれるのか、また外れる可能性があるケースについて詳しく見ていきましょう。
パターン①|健康保険の扶養から外れるパターン
失業保険の基本手当を受け取ると、その金額によっては年間収入130万円未満という扶養条件を超えることがあります。
特に、1日あたりの失業手当が3,612円以上(年換算で約130万円)となる場合は、扶養から外れるケースが多くなります。
また、受給期間が長期にわたると「将来的に年間収入が130万円を超える見込み」と判断され、扶養資格が外れる可能性があります。
この場合は国民健康保険に加入し、保険料を自己負担する必要があります。
パターン②|税制上の扶養に影響するパターン
税制上の扶養においては、失業保険の受給額が年間48万円(給与収入のみなら103万円)を超えると、扶養控除の対象外になります。
たとえば、失業手当の総額が50万円に達した場合、配偶者や親の扶養控除から外れてしまうため、所得税・住民税の負担が増える可能性があります。
ただし、失業保険は「非課税所得」に分類されるため、受給額がそのまま課税対象になるわけではありません。(国税庁 No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係より)
収入全体のバランスやその他の控除との関係も踏まえた判断が必要です。
雇用保険の基本手当と扶養の境界ライン
失業手当(雇用保険の基本手当)は、日額×支給日数で計算される給付金です。
この日額が健康保険・税制上の「扶養の基準額」を超えるかどうかが、扶養内にとどまれるかの分かれ道となります。
目安としては以下の通りです
- 健康保険の扶養基準:1日あたり3,612円未満(年換算で130万円未満)
- 税制上の扶養基準:年間48万円(給与収入なら103万円)以下
ただし、支給日数が短ければ扶養範囲に収まる場合もあるため、「1日あたりの金額×支給日数」で合計を確認することが重要です。
「扶養にとどまりたい」と考えている方は、受給額の見込みを事前に確認しておくと安心です。
どこに影響が出る?扶養を外れたときのデメリット
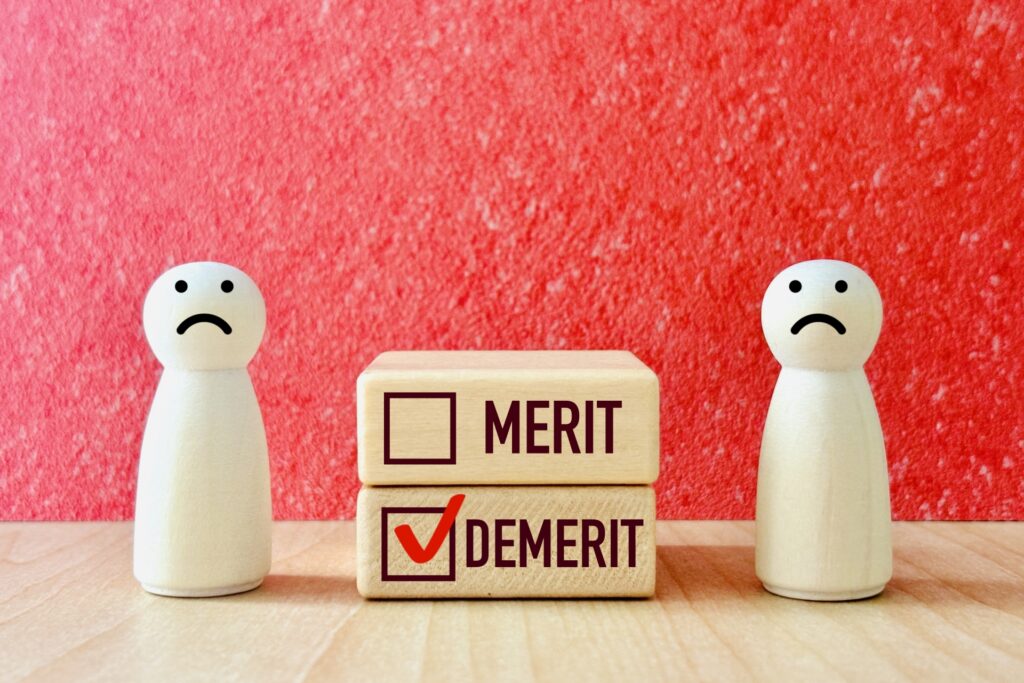
「扶養から外れたら、具体的にどんな負担が増えるの?」
そう疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
扶養から外れると、健康保険や税金の面で家計への影響が大きくなるケースもあります。
ここでは、実際にどんなデメリットがあるのか、注意しておきたいポイントを確認していきましょう。
社会保険料の自己負担が発生する
失業保険の受給により扶養から外れると、自分自身で健康保険と年金の保険料を支払う必要があります。
たとえば、配偶者の健康保険の被扶養者でいられなくなった場合には、国民健康保険への加入や任意継続被保険者の手続きが必要になります。
この保険料は地域や所得によって異なりますが、月に2〜4万円程度になることもあり、失業中の家計には大きな負担です。
さらに、国民年金の保険料も合わせて支払う必要があるため、トータルでは月5万円前後の出費になることも珍しくありません。
「扶養から外れる=家計負担が急増する」可能性がある点は、あらかじめ把握しておきたいところです。
配偶者控除が受けられなくなる可能性も
失業保険を受給して収入が一定額を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になる場合があります。
配偶者控除は、配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与のみなら103万円以下)であれば、世帯主の所得税・住民税を軽減できる制度です。
しかし、失業手当がこれらの基準を超えると、控除が適用されず税額が増える可能性が出てきます。
たとえ非課税の失業給付であっても、収入の合計として扶養判定の対象になる場合があるため、要注意です。
家計全体での税負担を減らすためにも、年末調整や確定申告の時期には、収入と控除の状況をしっかり確認しておきましょう。
手続きの手間や切り替えのタイミングに注意
扶養から外れる場合には、保険や税金に関するさまざまな手続きが必要になります。
たとえば、健康保険を自分で加入し直す際には、国民健康保険への加入届や任意継続の申請、年金制度の切り替えなどが発生します。
こうした手続きには期限が設けられていることも多く、うっかりすると未加入の期間が生じてしまう可能性もあります。
さらに、税制上の扶養を外れた場合も、年末調整や確定申告で正しい申告を行う必要があります。
収入が増える一方で、事務的な対応の負担や情報の整理も求められるため、早めにスケジュールを確認しておくことが大切です。
失業保険と扶養どちらが得?
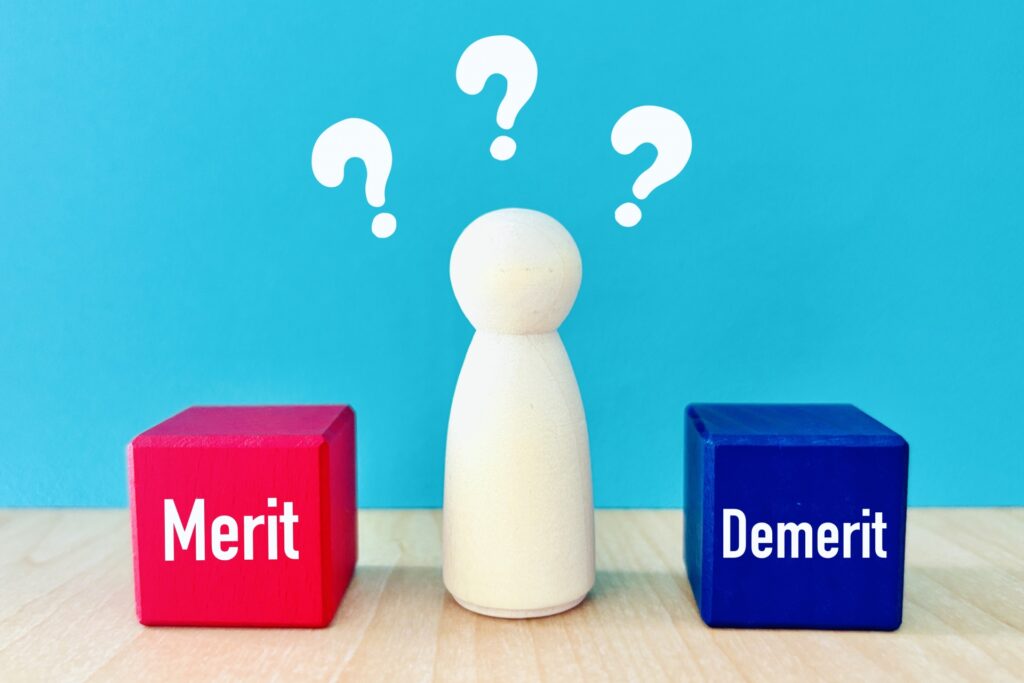
「失業保険をもらいたいけれど、扶養から外れたくない」
「保険料や税金の負担が増えるなら、もらわない方がいいのかも…」
そんな悩みを持つ方は少なくありません。
実際、扶養にとどまるメリットもあれば、失業保険を受け取るメリットもあり、家庭の状況によって判断は変わってきます。
ここでは、「結局どちらが得なのか?」を考えるうえで、押さえておきたい損得のポイントを整理していきます。
一時的に「損して得とる」ケースも?受給額と扶養恩恵の比較
失業保険をもらったことで一時的に扶養を外れ、保険料や税金の負担が発生することもあります。
しかし、それをもって「損」と判断するのは早計です。
なぜなら、失業保険の受給額が扶養にとどまることで得られる恩恵を上回ることもあるからです。
たとえば、失業手当が月10万円・半年間支給される場合、計60万円の受給。
一方、扶養にとどまっていても、国民年金や健康保険の負担を免れる分の金額は年20万〜30万円程度のケースも多く、手当の方が金額的に上回る場合もあります。
「目先の支出増」だけでなく、受給額・期間と扶養維持によるメリットをトータルで比べることが大切です。
一時的に扶養から外れても、結果として得られるものが多ければ“賢い選択”といえるでしょう。
健康保険・税制・再就職の見通しによって判断が変わる
「失業保険をもらう or 扶養にとどまる」という選択は、一律に正解があるわけではありません。
なぜなら、判断には複数の観点を総合的に見る必要があるからです。
たとえば、健康保険では、扶養を外れることで国民健康保険に加入し保険料を自己負担することになります。
一方、税制では配偶者控除や扶養控除の対象外となり、世帯全体の税負担が増える可能性も。
さらに、再就職の見込みが近い場合には、短期間だけ扶養を外れても手当の方が有利になるケースもあります。
逆に長期離職が予想される場合は、扶養内にとどまるメリットが大きくなることも。
このように、健康保険・税金・再就職の見通しを踏まえて、家庭の状況ごとに柔軟に判断することが重要です。
迷ったら「損得」だけでなく、制度変更の負担や安心感も考えて
失業保険を受け取るか、扶養にとどまるかという判断を下す際に、金額だけで比較してしまいがちですが、実はそれだけでは見落としてしまうリスクがあります。
たとえば、扶養を外れて国民年金や健康保険に切り替える場合、役所での手続きや保険料の納付など、制度変更の負担が生じます。
また、「あとで扶養に戻すにはどうすればいいのか」「受給が終わったあとの対応は?」といった、不安や手間が精神的なストレスになるケースも少なくありません。
制度の変更には、“見えにくい負担”や“安心感の差”がついてまわるということを意識しましょう。
たとえ金額面では少しの差でも、安心して過ごせる選択が、その後の生活の安定につながることもあります。
失業中でも扶養内にとどまるための対策

「できるだけ扶養のままでいたい…」
そう考える方も多いのではないでしょうか。
健康保険料の自己負担がなく、税制上もメリットがある扶養制度は、生活を支える大切な仕組みのひとつです。
しかし、失業保険を受け取ると扶養から外れる可能性があるため、何も知らずに手続きを進めると、思わぬ負担が発生することも。
ここでは、失業中であっても、扶養の範囲内にとどまるためにできる対策を具体的に解説します。
ポイントを押さえておけば、制度を上手に活用しながら無理なく生活を続けることができます。
収入・給付額の上限を理解する
扶養にとどまるためには、健康保険や税制で定められた“収入の上限”を超えないことが大前提です。
たとえば、健康保険の扶養では「年間130万円未満(または月額108,334円未満)」が基準とされることが一般的です(※)。
この金額には、雇用保険の基本手当(失業保険)も含まれるため、受給額が多いと扶養から外れる可能性があります。
また、税制上の扶養控除では、「年間103万円以内」がひとつの目安です。
こちらは給与所得に対する基準であり、失業保険の受給そのものは影響しませんが、アルバイトなどを再開した場合は注意が必要です。
つまり、失業保険+その他の収入の合計がどれだけになるかを事前に把握することが、扶養内にとどまるための第一歩です。
※健康保険の基準は加入している保険者によって異なる場合があります。
受給のタイミング・延長の選択肢を検討する
失業保険(雇用保険の基本手当)は、すぐに受給を開始しなければならないわけではありません。
実は、条件によっては「受給開始の時期を遅らせる」ことも可能です。
たとえば、離職後すぐに失業手当を申請せず、受給の延長申請を行うことで、最大で3年まで受給期間を先延ばしにできます。
これは、妊娠・出産・病気・介護などの理由がある場合に認められており、受給開始を後回しにすることで、その間は扶養内にとどまり続けるという選択ができるのです。
また、「扶養の範囲を超えないように、アルバイトなどの収入と失業手当の受給を調整する」など、タイミングの工夫も有効です。
ただし、延長には一定の申請期限や条件があるため、ハローワークへの早めの相談がおすすめです。
制度を理解しておくことで、ライフスタイルに合わせた柔軟な選択ができるようになります。
保険者に確認することが大切
扶養の判定基準や必要な手続きは、加入している健康保険の「保険者(組合や協会けんぽなど)」によって異なる場合があります。
そのため、「ネットで調べた情報」や「友人の話」だけで判断するのは危険です。
たとえば、同じ年収でも、ある保険者では扶養のままでいられる一方、別の保険者では外れると判断されるケースもあります。
また、失業保険を受け取る場合の取り扱いについても、「一時的な収入とみなすか」「継続的な収入とみなすか」といった判断が異なることもあるのです。
失業保険の受給前後には、必ず自分の保険証に記載された保険者へ直接問い合わせを行いましょう。
「この条件で扶養のままでいられるのか」「手続きに必要な書類は何か」などを確認することで、余計なトラブルや手戻りを防ぐことができます。
制度は複雑ですが、疑問点を一つずつクリアにしておくことが、安心につながります。
失業保険と扶養に関するよくある質問

失業保険と扶養の関係は、実際に当事者になってみないとイメージしづらいもの。
さらに、「人によって判断が変わる」という曖昧さもあり、不安を感じる方も多いはずです。
ここでは、特に相談の多い質問をピックアップし、基本的な考え方や注意点をわかりやすくまとめました。
実際の手続きや判断の参考にしてみてください。
Q. 失業手当を貰うだけで扶養から外れる?
失業保険(雇用保険の基本手当)を受給すると、必ず扶養から外れるとは限りません。
ポイントは、「受給額」と「受給期間中の扱い」が、扶養の基準にどう影響するかです。
たとえば、健康保険における扶養は「年間収入130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)」が目安とされており、失業手当の1日あたりの給付額が3,612円以上だと、扶養から外れる可能性が高くなります。
これはあくまで一般的な目安で、加入している健康保険組合や協会けんぽによっても判断基準は異なります。
また、失業手当は「一時的な収入」とみなされるため、税制上の扶養(配偶者控除など)にはすぐに影響しないケースもあります。
しかし、健康保険上では収入と見なされるため、保険料の自己負担が発生する可能性がある点には注意が必要です。
結論としては、一律に「貰ったら即アウト」というわけではないので、受給予定額を把握したうえで、保険者へ確認するのが確実です。
Q.パート・アルバイト再開後はどうなる?
失業保険の受給期間が終わり、パートやアルバイトで収入を得るようになった場合、再び「扶養に入れるかどうか」が気になるところです。
ここでも重要になるのは、「収入の金額」と「働き方の実態」です。
健康保険上の扶養では、年収130万円未満(条件によっては106万円未満)かつ、継続的な収入でないことが判断基準になります。
仮に月10万円程度の収入で、就労時間が少なく継続性がないと見なされれば、再び扶養に入れる可能性があります。
ただし、職場によっては勤務時間や雇用形態により、自分で社会保険へ加入することが義務付けられるケースもあります(週20時間以上勤務など)。
そのため、再就職の際は、雇用契約書や給与の見込み額を確認し、保険者に扶養の再判定を依頼することが重要です。
また、税制上の配偶者控除などにも影響するため、年末調整や確定申告の際にも要注意です。
「気づかないうちに扶養の条件をオーバーしていた」ということがないよう、働き方が変わるタイミングで、早めに確認を行いましょう。
Q.扶養に戻るにはどうすればいい?
失業保険の受給が終了した後や、パート・アルバイトの収入が基準を下回った場合、再び扶養に戻ることは可能です。
ただし、自動的に扶養へ復帰できるわけではなく、改めて手続きが必要になります。
まずは、健康保険上の扶養に戻るために、保険者(勤務先の健康保険組合や協会けんぽ)へ申請を行いましょう。
この際、以下のような書類の提出を求められることがあります。
- 雇用保険受給終了証明書(受給期間が終了したことを示す書類)
- パート・アルバイトの給与明細や雇用契約書(収入や就労時間の確認用)
- 扶養に戻る方の身分証や住民票などの基本的な提出書類
保険者が審査を行い、「収入が継続的でなく、かつ基準を下回っている」と判断されれば、扶養への再加入が認められます。
この判断には数週間かかることもあるため、勤務形態や収入に変動があった際には、できるだけ早めに申請を行うのがおすすめです。
また、税制上の配偶者控除などに関しても、その年の所得状況をもとに年末調整や確定申告で控除が適用されるかどうかが判断されます。
税と保険は別の制度で動いているため、それぞれ個別に確認・手続きが必要であることを覚えておきましょう。
制度に迷ったら専門家に相談を

失業保険と扶養の関係は、健康保険と税制の両面で異なるルールが絡むため、状況によって判断が大きく変わります。
「この場合は扶養を外れるの?」「今の働き方だと手続きは必要?」など、ネットだけでは解決しづらいケースも少なくありません。
特に次のような方は、一人で判断せず、専門家に相談するのが安心です。
- 失業保険を受給しながら短時間のアルバイトをしている
- 配偶者の会社の健康保険組合が独自ルールを設けている
- 年末調整や確定申告に不安がある
- 再就職や扶養の復帰を検討している
社会保険や税金は少しの違いで負担額が大きく変わることもあるため、不安を感じたら早めに行動することが大切です。
その上で、自分に合った制度の活用方法を見つけていきましょう。
扶養の判断は人それぞれ!不安があるなら早めに確認を
失業保険と扶養の関係は、「もらったら即アウト」「収入が○円ならセーフ」といった単純な基準だけで判断できない場合も多くあります。
健康保険と税制でルールが異なり、さらに各健康保険組合の独自ルールや個人の就労状況によっても扱いが変わるためです。
たとえば、同じ失業保険の受給でも…
- 失業前の勤務形態(正社員かパートか)
- 受給中の収入の有無や金額
- 世帯の年収構成や子どもの扶養状況
こうした条件の違いによって、「扶養のままでよい」とされる人もいれば、「外れてください」と言われる人もいます。
そのため、自分のケースに当てはめて考えることがとても大切です。
「これはどうなるんだろう?」「手続きが必要?」と少しでも迷ったら、勤務先の総務部や保険者、税務署、あるいはFP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家に確認を。
後回しにしてしまうと、不利益を被ったり手続きが煩雑になったりすることもあるので、早めの行動が安心につながります。
マネドアなら専門家に無料で何度も相談できる

失業保険と扶養の制度は複雑で、状況によって最適な選択肢が異なります。
「ネットで調べても結局よく分からない…」という声も少なくありません。
そんなとき頼りになるのが、お金の専門家と直接話せる「マネドア」です。
マネドアでは、ファイナンシャルプランナー(FP)との無料相談を何度でも受けることができ、扶養・保険・税金・家計の悩みまで幅広く対応しています。
「うちはどうなるの?」「扶養のままでいいのかな?」など、個別の不安や疑問をスッキリ解消したい方には特におすすめです。
不安なときこそ、信頼できる専門家の力を借りて、一歩ずつ前に進んでいきましょう。