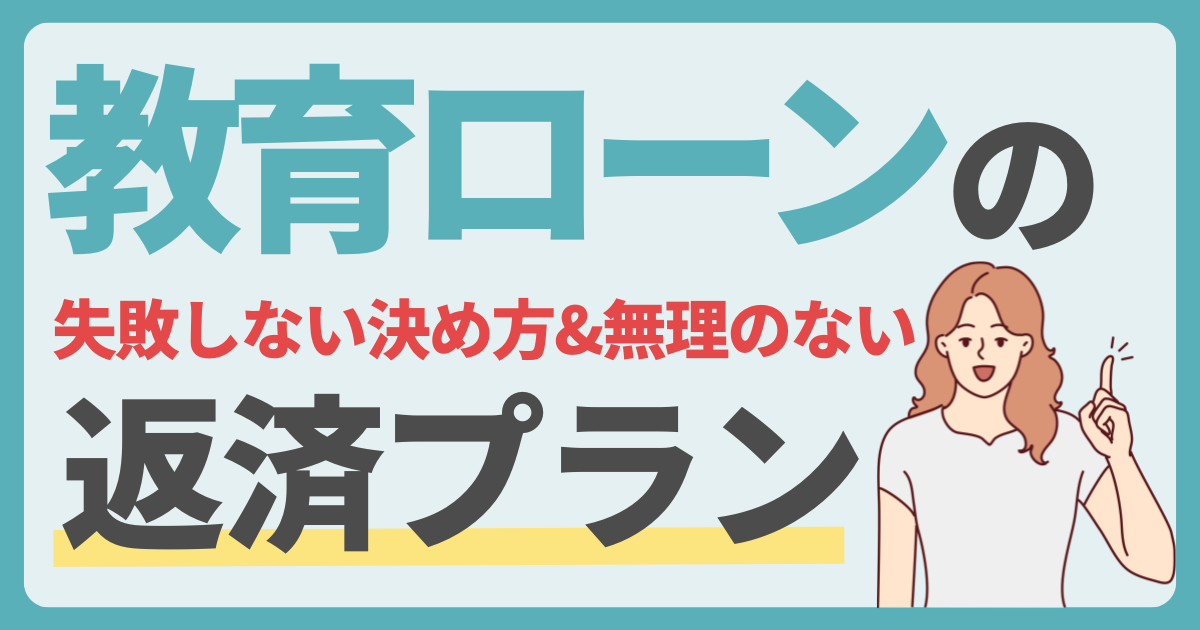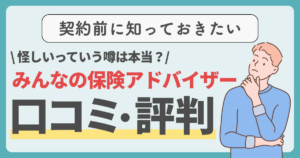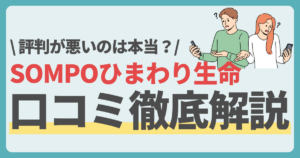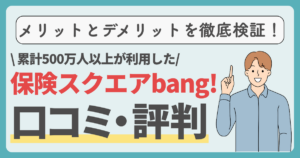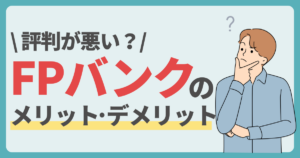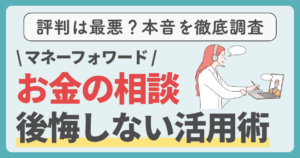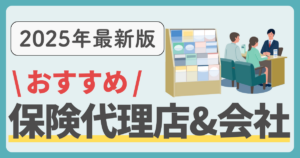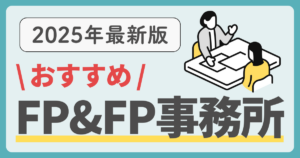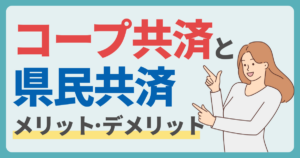教育ローンの返済期間は、短すぎても長すぎても家計に大きな影響を与える重要なポイントです。
「みんな何年で返してるの?」「自分の家庭に合った返済期間ってどう決めるの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
- 教育ローンの平均的な返済期間の実態
- 公的ローンと民間ローンの返済期間や特徴の違い
- 月々の返済額を無理なく抑えるための返済プランの立て方
- 返済期間の長短によって変わる総返済額や利息の差
- 専門家に相談して計画を立てるメリットと、相談先の選び方
「なんとなく」で返済期間を決めると、将来の家計に大きな負担がかかることも。
無理のない返済プランで、将来の生活にゆとりを持たせるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
【結論】教育ローンの平均返済期間は10年〜15年!ただし平均はあくまで参考値

教育ローンの返済期間は平均10〜15年とされていますが、この数字はあくまで全体的な目安です。
実際、200名を対象とした「比較メディアのスマートマネーライフが実施した学費・教育費のためのローン・奨学金利用に関するアンケート独自調査」でも、借入額や返済期間は家庭の状況によって様々であることが示されています。
たとえば、「国の教育ローン」として知られる日本政策金融公庫と、銀行や信用金庫などが提供する民間の教育ローンとでは、選べる返済年数に違いがあります。
また、金利や審査基準、返済開始のタイミングなども各ローンごとに特徴があります。
ここでは、公的ローンと民間ローン、それぞれの平均的な返済期間について詳しく見ていきましょう。
日本政策金融公庫(国のローン)と民間ローンの平均的な期間
教育ローンを提供する機関は大きく分けて、「公的ローン(日本政策金融公庫)」と「民間ローン(銀行や信用金庫など)」の2つに分類されます。
それぞれの返済期間には特徴と上限があり、利用者の選択にも影響します。
まず、日本政策金融公庫の教育ローンは、最長で15年まで返済可能です。
条件によっては、在学期間中の据置(元金据え置き)を含めて18年まで延ばすこともできます。※令和7年度予算成立に伴い、ご返済期間が最長18年から最長20年となります。(日本政策金融公庫 まるわかり本より)
この長期設定が可能な点は、公的ローンの大きなメリットのひとつです。
一方、民間の教育ローンは金融機関によって返済期間の上限が異なりますが、多くは最長10〜15年で設定されています。
なかには20年の返済期間を選べる商品もありますが、借入額や審査基準によって選べない場合もあるため注意が必要です。
公的ローンのほうが比較的柔軟で長めの返済期間を設定しやすい傾向がありますが、その分、申込時に世帯年収などの条件を満たす必要がある点も忘れてはいけません。
どちらを選ぶにしても、家庭の収支バランスやライフイベントを見据えたうえで、無理のない返済期間を選ぶことが大切です。
なぜ平均だけに頼ってはいけないのか?
「みんなが10〜15年で返しているなら、自分も同じで大丈夫だろう」
──そう考えて返済期間を決めてしまうのは、実はとても危険です。
平均値はあくまで“統計的な目安”であり、個々の家庭にとって適正かどうかはまったく別の話です。
たとえば、年収や他のローンの有無、子どもの人数や教育方針、将来のライフプランなどが異なれば、返済の余裕度や期間設定の最適解も当然変わってきます。
さらに、月々の返済額が高すぎると、途中で家計が苦しくなり、他の支出(生活費・老後資金・予備費など)を圧迫してしまう可能性も。
逆に返済期間を長くしすぎると、利息が増え、総返済額が膨らんでしまうデメリットがあります。
つまり、「平均に合わせる」のではなく、“自分たちの生活にフィットする返済プラン”を設計することが何より重要なのです。
まずは基本知識!「国の教育ローン」と「民間教育ローン」の違い

教育ローンを検討する際に、まず知っておきたいのが「どこから借りるか」という点です。
一口に教育ローンといっても、その提供元によって条件や特徴は大きく異なります。
なかでも代表的なのが、「日本政策金融公庫」が取り扱う国の教育ローン(公的ローン)と、都市銀行や信用金庫、ネット銀行などが提供する民間教育ローンの2種類です。
この2つは金利や返済条件、申込時の審査基準などに明確な違いがあり、どちらを選ぶかで家計への影響も大きく変わります。
ここからは、それぞれの特徴を比較しながら、選び方のポイントをわかりやすく解説していきます。
【国の教育ローン】金利が低いが上限額も低め/返済期間は最長18年
「国の教育ローン」は、日本政策金融公庫が提供する公的なローン制度で、全国どこに住んでいても利用できるのが特長です。
最大のメリットは、金利が低く固定されている点にあります。
また、所得制限はあるものの、比較的幅広い家庭で利用できるため、多くの保護者にとって心強い選択肢です。
一方で、借入の上限額は350万円(子ども1人あたり)までと、私立大学や留学などを含むケースでは資金が不足することも。
その場合は、別途奨学金や民間ローンの併用も検討する必要があります。
返済期間は最長15年(在学中は据え置き可能)ですが、条件を満たせば18年まで延長できるケースもあります。※令和7年度予算成立に伴い、ご返済期間が最長18年から最長20年となります
長期的な返済計画を立てたい人にとっては、柔軟な制度設計が魅力です。
ただし、申し込みには収入証明や進学予定校の資料提出が必要になるため、ある程度の準備期間も見込んでおきましょう。
【民間教育ローン】高額融資も可能/返済期間は10年前後が中心
銀行や信用金庫、ネット銀行などが提供する民間の教育ローンは、借入限度額が高めに設定されているのが特長です。
たとえば大手銀行の教育ローンでは、子ども一人あたり最大1,000万円前後まで借りられるケースもあります。
医歯薬系の進学や海外留学など、教育費がかさむ家庭にとっては、頼れる選択肢といえるでしょう。
ただし、金利は変動型が多く、公的ローンよりも高め(年2.5〜4.5%程度)になる傾向があります。
返済総額が大きくなりやすいため、借入前にはしっかりと試算しておくことが大切です。
返済期間は10年前後が中心ですが、金融機関によっては最長15年まで設定できることもあります。
また、申込から融資までが比較的スピーディーな点も民間ローンの魅力の一つ。入学直前などの緊急対応が必要な場合には重宝されます。
ただし、審査は勤務先・年収・他の借入状況などをもとに厳しくチェックされるため、通過には一定の信用力が求められます。
過去に延滞や債務整理の履歴がある場合は、別の手段を検討する必要があるかもしれません。
【比較表】金利・上限額・返済期間の違い一覧
ここまで「国の教育ローン」と「民間の教育ローン」について個別に解説してきましたが、特徴をより明確に理解するために、主要な項目を表にまとめて比較してみましょう。
| 国の教育ローン | 民間教育ローン | |
| 金利 | 年2.85%(固定金利)※2025年6月時点 | 年2.5〜4.5%(変動が多い) |
| 借入上限額 | 子ども1人あたり350万円まで | 最大1,000万円前後も可能 |
| 返済期間 | 最長15年(条件により18年) | 通常5〜10年、最長15年程度 |
| 審査基準 | 所得制限あり | 勤務先や信用情報を重視 |
奨学金との違い(返済義務は親か子か)
教育資金を準備する手段として、「教育ローン」と並んで検討されやすいのが「奨学金」です。
一見似たような制度に見えますが、最も大きな違いは「誰が返済の責任を負うか」という点にあります。
教育ローンの場合、契約者は原則として親(保護者)であり、返済義務も親にあります。
そのため、借入後は保護者が毎月返済していくことになり、子ども自身が返すことは基本的にありません。
一方で、奨学金(特に日本学生支援機構など)では、子ども本人が借り手となり、社会人になってから自分で返済していくのが一般的です。
このため、将来の収入状況やキャリア設計に影響を及ぼすことがあり、「返済が重く感じる」という声も少なくありません。
また、教育ローンは在学中から返済がスタートするケースも多いのに対し、奨学金は卒業後からの返済開始が一般的という違いもあります。
どちらを選ぶにしても、「返済の主体は誰か?」「どのタイミングで返済が始まるか?」を明確にした上で、家族で相談して決めることが大切です。
教育ローンの平均返済額と家計への影響

教育ローンを検討するうえで、「毎月いくら返済すればいいのか?」という点は、もっとも現実的で重要な判断材料になります。
無理な金額を設定してしまうと、家計を圧迫し、他の支出にしわ寄せがくることも。
では、平均的な借入額や返済期間をふまえた場合、どのくらいの金額が“妥当な返済額”と言えるのでしょうか?
次に、具体的なシミュレーションを通して目安を見ていきましょう。
教育ローンの毎月の返済額はどれくらいが妥当?
「返済額の目安」は家庭によって異なりますが、ひとつの基準として意識したいのは、家計に対するローン返済の割合です。
一般的に、教育ローンを含めた借入返済額が手取り月収の20%以内に収まることが、無理のない返済の目安とされています。
たとえば、世帯の手取り月収が30万円の場合、月々のローン返済額は6万円以下が望ましいとされています。
しかしこの中には住宅ローンや車のローンが含まれるケースも多いため、教育ローン単体では2万〜3万円前後を上限に考えるのが現実的でしょう。
実際に日本政策金融公庫の「国の教育ローン」で300万円を借りて10年返済した場合、毎月の返済額は約27,600円(年利2.0%で試算)となります。
15年返済に延ばせば月額は減りますが、支払う利息は増えるため、「月々いくらなら家計に無理がないか?」をあらかじめシミュレーションしておくことが重要です。
教育ローンは数年間にわたって継続的に返済していくもの。
奨学金や家族の収入状況などもふまえて、“返せる金額”から借りる”という視点を忘れずに計画を立てましょう。
世帯年収や子どもの人数別に見る返済負担
教育ローンの返済額は「平均」だけを参考にするのではなく、家庭の年収や子どもの人数に応じて柔軟に考えることが大切です。
同じ300万円を借りる場合でも、収入が多い家庭と少ない家庭では負担感が大きく異なります。
たとえば、年収500万円の家庭が月3万円の返済を10年間続ける場合、年間返済額は約36万円。
これは年収の約7.2%に相当し、他の支出とのバランス次第ではやや厳しく感じるかもしれません。
さらに子どもが2人、3人と増えていけば、教育費は複数年にわたって重なります。
たとえ返済を分散できたとしても、「第二子の進学タイミングで返済が二重になる」といったケースも少なくありません。
こうした状況を想定するには、ライフプラン全体を俯瞰したうえでの資金計画が必要です。
FP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家に相談して、将来の収支バランスを見える化するのも有効な方法です。
返済が厳しくなるケースとその対処法
どれだけ慎重に計画していても、予想外の出費や収入の減少により、教育ローンの返済が重荷に感じられることがあります。
特に子どもの人数が多い家庭や、収入に変動のある自営業世帯などでは、返済中の不安も少なくありません。
たとえば以下のようなケースでは、返済が厳しくなる傾向があります。
- 親の転職や病気による収入減
- きょうだいの進学が重なる時期
- 思った以上に学費や生活費がかかった場合
- その他のローン(住宅・自動車等)と時期が重なる
こうしたときに備えて、あらかじめ対策を講じておくことが重要です。
たとえば「ステップ返済型」や「元利据置型」のローンを選ぶことで、在学中の返済負担を軽くすることができます。
さらに、返済が困難になった場合には「返済期間の延長」「繰上げ返済の一時停止」「一部返済の調整」といった手続きが可能な金融機関もあります。
困ったときには早めに相談し、家計へのダメージを最小限に抑えることがポイントです。
教育ローン返済期間の決め方

教育ローンは「何年で返すか」によって、月々の返済額や総返済額、家計への影響が大きく変わります。
返済期間が短ければ利息負担は少なくなりますが、毎月の支出は増加。
一方、期間を長くすれば月々の負担は軽くなるものの、最終的な返済総額は増える傾向にあります。
つまり、教育ローンの返済期間をどう設定するかは、家計のゆとりと長期的なライフプランの両方を見据えたバランス感覚が問われる部分なのです。
ここでは、返済期間を決めるうえで押さえておきたい判断基準と、短期・長期の違いについて詳しく見ていきましょう。
金利・返済額・ライフプランのバランスを考える
教育ローンの返済期間を決める際は、「金利の影響」「毎月の返済額」「将来のライフイベント」の3点をバランスよく考えることが大切です。
まず、返済期間が短いほど利息の総額は抑えられます。
たとえば300万円を借りて10年返済する場合と15年返済する場合では、後者のほうが総支払額は数十万円多くなることもあります。
しかし、その分毎月の返済額は軽くなるため、目先の家計を楽にしたい人にとっては15年返済も現実的な選択肢です。
一方で、将来に住宅購入・転職・介護といった大きな支出を控えている場合、早めに完済しておきたいと考える家庭も多いでしょう。
また、子どもが複数人いる場合は「上の子の教育ローンを完済しないうちに、下の子の進学が始まる」といった重複リスクも出てきます。
そのため、金利の負担・月々の余裕・家族の将来像をすべて視野に入れて、無理なく返していける計画を立てることが成功のカギです。
教育ローンの繰り上げ返済は本当にお得?
ローンを借りたあと、「余裕ができたら早めに返してしまいたい」と考える方も多いのではないでしょうか。
確かに、繰り上げ返済をすれば元本が早く減るぶん、支払う利息を抑えることができます。
とくに金利が高めの民間ローンでは、繰り上げ返済の効果が大きく、返済総額を数万円〜十万円単位でカットできるケースもあります。
しかし、注意すべき点もあります。
たとえば、繰り上げ返済によって手元資金が減りすぎてしまうと、急な出費(医療費、修繕費、冠婚葬祭など)に対応できなくなるリスクがあります。
また、繰り上げ返済に「手数料」がかかるローン商品もあるため、返済メリットと費用をしっかり比較したうえで判断することが大切です。
「今すぐ繰り上げるか?」「数年後にまとめて返すか?」といった戦略を立てるためにも、家計全体のキャッシュフローを見直しながら、無理のないタイミングを見極めましょう。
途中で教育ローンの返済期間を見直すことはできる?
「毎月の返済が思ったより負担に感じる…」「もっと早く完済したい」など、借入後に返済期間の見直しを検討したくなることもあります。
そんなとき、教育ローンは途中で返済期間を変更できるのでしょうか?
実は多くの教育ローンでは、一定の条件を満たせば返済期間の延長・短縮が可能です。
たとえば、民間ローンでは返済状況や信用情報に問題がなければ、期間の見直しに応じてもらえるケースがあります。
また、日本政策金融公庫(国の教育ローン)でも、収入状況の変化などを理由に相談すれば、柔軟な対応がとられることもあります。
ただし、返済期間を延ばせば毎月の支払額は軽くなる一方で、利息が増えてトータルの返済額は大きくなる可能性があることにも注意が必要です。
逆に、短縮を申し出る場合は、安定した収入や貯蓄状況が確認されることもあります。
まずは借入先の金融機関に相談し、条件や必要書類、手続きの流れを確認することが第一歩です。
教育ローンで失敗しないための事前チェックリスト

教育ローンは、進学という一大イベントを支える大きな選択です。
しかし、「とりあえず借りてから考えよう」と安易に進めてしまうと、後になって返済に苦しんだり、家計がひっ迫したりするリスクがあります。
だからこそ、借りる前の準備が肝心。
ここでは、教育ローンで失敗しないために「申し込む前に確認すべきポイント」をわかりやすく整理しました。
進学の夢を支えるためにも、今一度しっかりチェックしておきましょう。
金利だけじゃない!総費用の比較がカギ
教育ローンを選ぶ際、多くの人が真っ先に注目するのが「金利」ですが、実はそれだけでは不十分です。
本当に比較すべきなのは、「返済が終わるまでにかかる総費用(=総返済額)」です。
たとえば、A社とB社のローンで金利が0.3%違っても、返済期間や保証料、手数料などの諸費用によっては、逆転するケースも珍しくありません。
また、「元利均等返済」と「元金均等返済」といった返済方式の違いでも、長期的な負担は大きく変わってきます。
重要なのは、金利だけに目を奪われず、返済期間・借入額・諸費用を含めたトータルコストをしっかり比較すること。
金融機関の公式サイトには返済シミュレーション機能がある場合も多いので、活用しながら慎重に見極めましょう。
教育ローン返済中に困らないためのシミュレーション方法
教育ローンを借りる前に、必ず行っておきたいのが「返済シミュレーション」です。
これを怠ると、「月々の支払いが想定より重くて生活が苦しい…」という事態にもなりかねません。
シミュレーションでは、借入金額・返済期間・金利を入力して、月々の返済額や総返済額を確認します。
民間の銀行サイトや、国の教育ローン(日本政策金融公庫)のページには、無料で使えるツールが用意されていることが多く便利です。
さらに、ただ金額を見積もるだけでなく、以下のような視点も加えると実践的です。
- 教育ローンの返済と、住宅ローン・車のローンなどのバランスは取れるか?
- もし収入が一時的に減った場合でも返済は可能か?
- 子どもが複数いる場合、次の進学時期と重ならないか?
「借りたあとに困らないため」のシミュレーションこそ、教育ローン計画の最重要ポイントといえるでしょう。
保証人・担保・団信などの制度もチェックしよう
教育ローンを借りる際には、返済条件だけでなく「契約に必要な制度や付随条件」もしっかり確認しておくことが大切です。
特に注意したいのが、保証人の有無・担保の必要性・団体信用生命保険(団信)の扱いなどです。
たとえば、国の教育ローン(日本政策金融公庫)では原則として連帯保証人が必要ですが、保証料を支払うことで不要にする制度もあります。
一方、民間の教育ローンでは、保証会社の審査によって保証人なしで契約できることもありますが、そのぶん保証料が金利に上乗せされる仕組みになっているケースが多く見られます。
また、ローン契約者に万が一のことがあったときに備える「団信」の加入が任意・強制かも、金融機関によって異なります。
加入していれば家族の負担を軽減できますが、保険料が別途かかる場合もあるため、費用対効果を考えて判断する必要があります。
こうした制度は見落とされがちですが、ローン選びの最終判断に大きく関わるポイントです。
申し込み前には各金融機関の条件をしっかり比較しておきましょう。
教育ローンに迷ったら専門家に相談という選択肢も

教育ローンの種類や返済期間、金利の違いを学んでも、いざ自分の家庭に合ったローンを選ぶとなると、不安が残る方も多いのではないでしょうか。
とくに家族構成や世帯年収、子どもの人数によって適切な借入額や返済期間は大きく変わります。
そんなときに頼れるのが、ファイナンシャルプランナーなどの専門家による家計相談です。
教育費の捻出方法や、他の支出と無理なく両立できる返済プランを、客観的にアドバイスしてもらえます。
家庭ごとのベストな教育ローン返済プランとは?
教育ローンの正解は一つではありません。
世帯年収や生活費、他のローンの有無、さらには「大学進学後の仕送りが必要かどうか」といった条件によって、最適な返済プランは大きく変わります。
たとえば、共働きで安定した収入がある家庭なら、多少返済額が高くても早めに完済する選択が有利な場合も。
一方で、子どもが複数いて将来的な支出が重なる家庭では、月々の負担を抑えて返済期間を長めに設定する方がリスク管理に有効なこともあります。
また、借入額の上限に頼るのではなく、「自分たちの家計でどこまでなら返せるのか」という視点を持つことが大切です。
教育ローンの返済が生活を圧迫してしまっては、本末転倒です。
マネドアなら何度でも無料で相談可能

教育ローンの借入額や返済期間に不安がある場合、第三者の専門家に相談することで解決の糸口が見えることがあります。
とはいえ、「相談は高額なのでは?」「営業されるのでは?」とためらう方も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめなのが、何度でも無料で相談できる家計相談サービス「マネドア」です。
マネドアでは、経験豊富なファイナンシャルプランナーが中立な立場で相談にのってくれるため、金融機関の都合に左右されず、本当に自分たちの家計に合った教育ローンの選び方や返済プランを提案してもらえます。
また、対面・オンラインの両方に対応しており、忙しいご家庭でも気軽に利用できるのが魅力です。
専門家に相談してわかった教育ローン借りすぎのリスク
教育ローンは、必要な進学費用をまかなえる心強い手段ですが、借りすぎることで後々の家計に大きな負担を残してしまうリスクもあります。
専門家への相談でよく指摘されるのが、「とりあえず借りておけば安心」という考えによる過剰な借入。
とくに子どもが複数いる場合は、1人目の進学時点で借入枠を使い切ってしまい、2人目以降の教育費に対応できなくなるケースも見られます。
また、借入額が大きくなると月々の返済額も膨らみ、住宅ローンや老後資金とのバランスが崩れることにもつながります。
その結果、「教育ローンの返済のために生活費を削る」「進学後の仕送りが難しくなる」といった事態に陥る家庭も少なくありません。
だからこそ、借入前に「本当に必要な金額か?」「返済に無理はないか?」を客観的に確認することが重要です。
マネドアのような専門家サービスを活用すれば、冷静な判断材料をもとに、自分たちにとって無理のない教育ローン計画を立てることができます。
教育ローンを借りる前にじっくり比較と相談を

教育ローンは、将来のための大切な投資である一方で、長期的に家計に影響を与える“負債”でもあります。
借入先や金利、返済期間の違いによって、最終的な返済総額は大きく変わってきます。
とくに「国の教育ローン」と「民間の教育ローン」では、金利・借入可能額・審査基準に違いがあり、家計や進学プランに合ったローンを選ぶことが重要です。
また、借入額の多寡に関わらず、無理のない返済スケジュールを立てることが、家計破綻を防ぐうえでのカギになります。
とはいえ、これらを自分たちだけで判断するのは簡単ではありません。
だからこそ、中立的な立場でアドバイスしてくれる専門家の存在が頼りになります。
教育資金やローン返済に不安がある方は、早い段階から無料相談サービスを活用し、納得のいく形で準備を進めていきましょう。
平均だけに頼らず「自分に合った返済期間」を見つけよう
教育ローンの平均返済期間が10年〜15年とされていても、それがすべての家庭にとって「正解」とは限りません。
たとえば、家計に余裕があり早期完済を目指せる家庭と、他のローンや支出との兼ね合いから長期返済が適している家庭では、選ぶべき返済期間がまったく異なります。
また、平均よりも短く設定して無理な返済を続けてしまうと、途中で家計が圧迫されるリスクが高まります。
逆に、長すぎる返済期間は利息負担の増加につながる可能性もあるため、慎重な検討が必要です。
大切なのは、「平均だから」「多くの人がそうしているから」といった理由ではなく、あなたの家庭の収支・ライフイベント・価値観に合った返済計画を立てることです。
悩んだら専門家と一緒に計画を立てるのが安心
教育資金やローンの返済計画に悩んだとき、信頼できる専門家に相談することで、不安を大きく軽減できます。
とくに初めて教育ローンを検討するご家庭では、「金利の違いがよく分からない」「繰り上げ返済すべきか迷う」など、さまざまな疑問が生まれるものです。
そんなときこそ、中立的な視点で家計全体を見渡しながらアドバイスをしてくれるファイナンシャルプランナーの存在が心強い味方になります。
マネドアのような無料相談サービスを活用すれば、何度でも気軽に相談でき、必要な知識や選択肢を整理しながら計画を立てられます。
教育ローンは、数年〜十数年にわたる長期的な家計の課題。だからこそ、最初の一歩を間違えないように、プロと一緒に考えるという選択肢を、ぜひ取り入れてみてください。