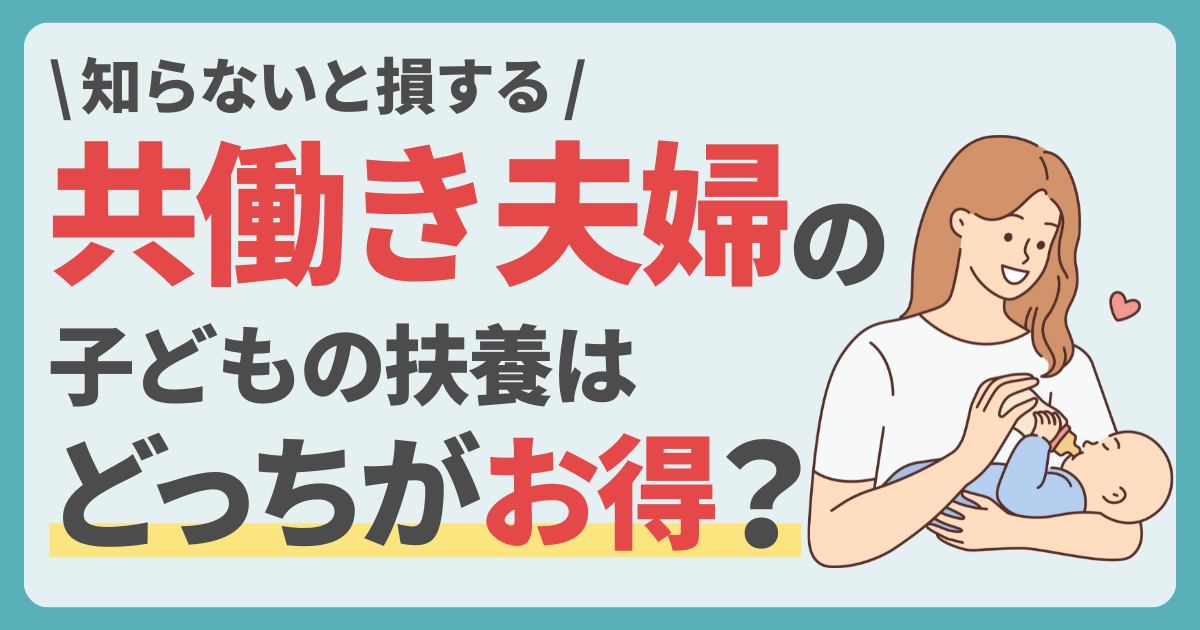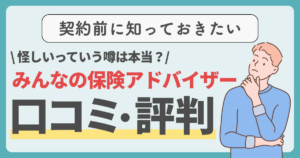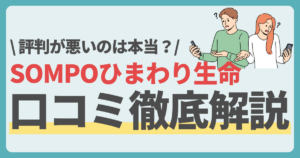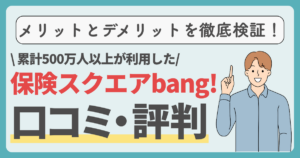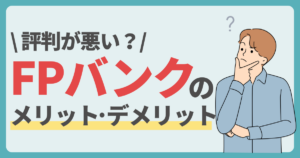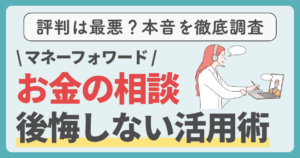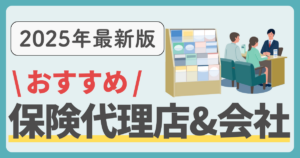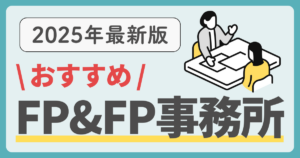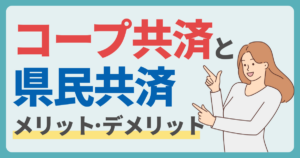「子どもが生まれたけれど、扶養は夫と妻、どちらにつけるのがお得なんだろう?」 「共働きで収入が同じくらいの場合、どうやって決めたらいいの?」
共働きが当たり前になった今、子どもの扶養を夫婦のどちらにするかは、多くの家庭が悩むポイントです。
なんとなく収入が多い方にしている、あるいは会社に言われるがままに手続きしてしまった、という方も少なくないかもしれません。
しかし、この選択一つで、手取り額に大きく関わる税金や、将来受け取る年金額にも影響が出る可能性があることをご存知でしょうか。
扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれの仕組みを正しく理解しないと、気づかないうちに損をしてしまうこともあります。
この記事では、共働き夫婦が子どもの扶養を選ぶ際に知っておくべき基本的なルールから、具体的なケース別の判断ポイント、節税効果を最大化するための考え方まで、専門用語を避けながらわかりやすく解説します。
- 共働き家庭における子どもの扶養の基本的な考え方
- 「税制上」と「社会保険上」の扶養制度の具体的な違い
- 夫婦の収入状況に応じた最適な扶養の選び方
- 扶養の変更手続きが必要になるタイミングと具体的な方法
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
【結論】共働きの子どもの扶養は「収入が多い方」が基本

早速結論からお伝えすると、共働き家庭において子どもの扶養は、原則として「夫婦のうち、収入が多い方」に入れるのが最も合理的で、多くの場合お得になります。
これは、私たちが支払う「税金」と、加入する「社会保険」の両方の制度設計が関係しています。まずは、なぜ高収入側が有利になるのか、基本的な考え方を理解しておきましょう。
共働きで扶養はどっち?税金・社会保険ともに収入が高い側が有利
子どもの扶養を考えるとき、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの側面から見る必要がありますが、いずれも収入が多い親が扶養する方がメリットが大きい、またはそのように定められているケースがほとんどです。
所得税は、収入が多いほど高い税率が課される「累進課税」が採用されています。
扶養控除は、所得から一定額を差し引くことで課税対象額を減らす制度のため、税率が高い人(=収入が多い人)が利用した方が、減税される金額が大きくなり、節税効果が高まります。
健康保険の扶養については、厚生労働省の通達により、夫婦が共同で子どもを扶養する場合、原則として年間収入の多い方の被扶養者とするという基準が示されています。
これは、保険制度の健全な運営と公平性を保つためのルールです。 多くの健康保険組合ではこの基準に沿って判断するため、個人の意思だけで収入が少ない方の扶養に入れることは基本的に認められません。(参照:夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について)
収入差が小さい場合は、手当や保障内容で判断するのもアリ
夫婦の収入がほぼ同じで、どちらの扶養に入れるか選択の余地がある場合は、少し違った視点で検討するのも一つの方法です。
特に確認したいのが、勤務先の会社が独自に設けている福利厚生です。
- 家族手当・扶養手当:会社によっては、扶養する子ども1人につき月額5,000円~10,000円といった手当を支給している場合があります。
この手当の有無や金額が夫婦の会社で異なるなら、手当が手厚い方の扶養に入れることで、世帯収入を増やすことができます。
- 健康保険の付加給付: 加入している健康保険組合によっては、法律で定められた保険給付に加えて、独自の「付加給付」を設けていることがあります。
例えば、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される「高額療養費制度」の自己負担限度額が、国の基準よりさらに低く設定されているなどです。万が一の病気やケガに備え、より保障が手厚い方の扶養に入るという考え方もあります。
これらの福利厚生は会社の規定や健康保険組合によって内容が大きく異なるため、夫婦それぞれの勤務先の担当部署に確認してみましょう。
例外ケース|自営業×会社員やパート勤務の場合の注意点
夫婦の一方が自営業やパートタイマーである場合は、判断基準が少し異なります。
自営業の親が加入する「国民健康保険」には、そもそも「扶養」という概念がありません。
家族も一人ひとりが被保険者として保険料を支払う仕組みです。
そのため、子どもの健康保険は、自動的に会社員の親の健康保険(協会けんぽや組合健保)の扶養に入ることになります。 一方で、税制上の扶養控除は収入に応じてどちらの親が受けるかを選択できます。
パートタイマーの親が、自身の勤務先で社会保険に加入している(被保険者である)場合は、収入に応じて子どもの扶養を検討します。
しかし、年収が基準額未満で、配偶者の社会保険の扶養に入っている場合は、子どもを自分の扶養に入れることはできません。
子どもを社会保険の扶養に入れることができるのは、社会保険の「被保険者」本人だけです。
共働き夫婦で迷う「扶養どっち?」2つの制度の違い

ここまで「税金」と「社会保険」という言葉が何度か出てきましたが、実は「扶養」にはこの2つの全く異なる制度が存在します。
「扶養に入れる」と一括りにされがちですが、それぞれの目的や条件は全くの別物です。
この違いを正しく理解することが、損をしない選択をするための第一歩となります。
税制上の扶養|配偶者控除・扶養控除による節税効果
まず「税制上の扶養」とは、所得税や住民税の負担を軽くするための制度です。
納税者に扶養している親族がいる場合、その人の所得から一定の金額を差し引く「所得控除」が受けられます。
代表的なものが、16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される「扶養控除」です。
課税対象となる所得金額が少なくなるため、結果として支払う税金が安くなる、という仕組みです。
例えば、課税所得500万円の人が38万円の扶養控除を受けると、課税所得は462万円として税額が計算されます。
所得税率が20%の場合、単純計算で7.6万円(38万円 × 20%)の節税につながります。
このため、所得税率が高い高収入の人ほど、節税効果は大きくなります。(参照:国税庁 No.1180 扶養控除)
社会保険上の扶養|保険料ゼロで保障を受けられる仕組み
一方の「社会保険上の扶養」は、主に健康保険に関する制度です。
会社員や公務員などが加入する健康保険では、被保険者(本人)に扶養されている家族は「被扶養者」として認定されます。
被扶養者になると、自身で健康保険料を納めることなく、被保険者本人と同様に保険証が交付され、医療機関を受診した際の自己負担が3割になるなどの保障を受けられます。
もし子どもをどちらの扶養にも入れない場合、子ども自身が国民健康保険に加入し、保険料を支払う義務が生じます。
社会保険の扶養制度は、こうした保険料負担をなくし、家族の医療を保障するための重要な仕組みです。(参考:全国健康保険協会 被扶養者とは?)
共働き夫婦は「税金」と「保険」の両方を見て決める必要がある
ここで重要なポイントは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」は、必ずしも一致させる必要はないということです。
例えば、子どもの健康保険は収入が多い夫の扶養に入れつつ、税金の扶養控除は妻が受ける、といった選択もルール上は可能です(ただし、会社の家族手当などが扶養を同一にすることを条件としている場合もあります)。
共働き夫婦が子どもの扶養を考える際は、この2つの制度を切り離して、「健康保険はどちらがお得か?」「税金の控除はどちらが受けると節税効果が高いか?」と、それぞれの側面から世帯全体で最もメリットのある組み合わせを検討する必要があります。
健康保険の扶養はどっち?共働き家庭の判断ポイント

まずは、日々の生活に直結する「健康保険」の扶養から考えていきましょう。
税金の扶養と違って、健康保険の扶養は「どちらがお得か」という選択の自由度が低く、国の定めたルールに沿って決めるのが基本です。
ここでは、具体的な判断ポイントを3つに絞って解説します。
原則は「年収が多い方」の健康保険に加入
社会保険の扶養で最も重要なルールは、夫婦の年間収入を比較し、多い方の扶養に子どもを入れるということです。
これは厚生労働省の通達で定められた公的な基準で、ほとんどの健康保険組合がこのルールに基づいて審査を行います。
ここで言う「年間収入」とは、過去の収入ではなく、扶養に入れる時点から将来1年間の見込み収入額を指します。
そのため、昇給や転職で収入に変動があった場合は、その変動後の金額で比較する必要があります。
夫婦間の収入差が明らかに大きい場合は、悩むことなく収入が高い方の扶養に入れることになります。
年収がほぼ同じなら「会社独自の手当・保障内容」で選ぶ
夫婦の年収が同程度で、どちらの扶養に入れるか判断が難しいケースもあります。
一般的に、収入差が1割以内である場合などは、総合的な状況で判断されることがあります。
このような場合は、夫婦それぞれの会社や健康保険組合が提供する福利厚生を比較検討するのがおすすめです。
- 家族手当・扶養手当: 勤務先の就業規則を確認し、子どもを扶養に入れることで支給される手当の有無や金額を比較します。
- 付加給付: 加入している健康保険組合独自の給付内容をチェックしましょう。
例えば、高額な医療費がかかった際の自己負担額が国の基準より低く設定されていたり、人間ドックの補助が手厚かったりする場合があります。
どちらの扶養に入れるか選択の余地がある場合は、より手厚いサポートを受けられる方を選ぶと良いでしょう。
自営業の親は対象外。共働きでも会社員側にしか入れられない
夫婦の一方が自営業やフリーランスで、もう一方が会社員という組み合わせの場合は、選択の余地はありません。
自営業者が加入する国民健康保険には「扶養」という制度が存在しないためです。
国民健康保険では、生まれた子どもも一人の加入者として保険料が発生します。
そのため、片方が会社員であれば、子どもは自動的に会社員の親が加入する健康保険の扶養に入ることになります。
これにより、子どもの分の保険料負担はなくなります。
税金面ではどっち?扶養控除による差をチェック

健康保険の扶養とは異なり、税金面の扶養(扶養控除)は、世帯の手取り収入を最大化するための戦略的な選択が可能です。
基本ルールと、少し応用的な考え方を知っておくだけで、年間の手取り額に差が生まれることもあります。
高所得の親が控除を受けた方が効果大
税制上の扶養における最も基本的な原則は、「所得が高い方の親が扶養控除を受ける」ことです。
その理由は、所得税が「累進課税制度」を採用しているためです。
累進課税とは、所得が高くなるほど、より高い税率が課される仕組みです。
扶養控除は課税対象の所得から一定額を差し引く制度なので、税率が高い人(=所得が高い人)が控除を使った方が、税金が安くなる金額(節税額)が大きくなります。
例えば、16歳の子ども1人(扶養控除額38万円)を扶養に入れる場合を考えてみましょう。
- 夫(所得税率20%)が扶養に入れた場合: 38万円 × 20% = 7.6万円 の節税
- 妻(所得税率10%)が扶養に入れた場合: 38万円 × 10% = 3.8万円 の節税
このケースでは、夫が扶養控除を受けることで、世帯として年間3.8万円多く手元にお金が残ることになります。(参考:国税庁 No.2260 所得税の税率)
あえて低所得側につけると住民税非課税世帯の条件を満たすことも
原則は高所得側が有利ですが、例外的にあえて所得が低い方の親の扶養に入れることでメリットが生まれるケースがあります。
それが「住民税非課税世帯」の条件を満たす場合です。
住民税非課税世帯になると、住民税が全額免除されるだけでなく、自治体によっては国民健康保険料の減額、高額療養費の自己負担限度額の引き下げ、臨時給付金の対象になるなど、様々な行政サービスの優遇を受けられる可能性があります。
この非課税の判定基準は、扶養親族の人数によって変動します。
そのため、所得がボーダーライン上にある場合、扶養控除を所得の低い配偶者につけることで、その配偶者の課税所得が基準以下になり、結果として世帯全体が住民税非課税の恩恵を受けられることがあるのです。
ただし、これは夫婦の所得額が特定の範囲内にある場合に限られるため、お住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。
16歳未満は扶養控除対象外だが、児童手当・非課税判定に影響することも
ここで一つ注意点があります。所得税の扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の子どもです。
これは、かつて存在した年少扶養控除が廃止され、「児童手当」に置き換わったためです。
そのため、子どもが中学生以下の場合は、扶養控除による直接的な所得税の節税効果はありません。
しかし、16歳未満の子どもであっても、年末調整や確定申告の際に「扶養親族」として申告することは非常に重要です。
なぜなら、この申告情報が以下の2点に影響するからです。
- 住民税の非課税判定: 先述した住民税非課税世帯に該当するかどうかの判定において、扶養親族の人数には16歳未満の子どもも含まれます。
- 児童手当の所得制限: 児童手当には所得制限が設けられており、その計算においても扶養親族の人数が影響します。
たとえ直接の節税にならなくても、子どもがいる場合は必ず扶養親族として申告するようにしましょう。(国税庁:No.1180 扶養控除)
共働き家庭で子どもが2人以上いる場合の「扶養の分け方」

お子様が2人以上いるご家庭では、「全員を夫の扶養に入れるべきか?」「一人ずつ分けるべきか?」といった新たな選択肢が生まれます。
扶養の分け方次第で、受けられる控除や手当の総額が変わってくるため、より戦略的な視点が必要になります。
扶養を夫婦で分ければ双方が控除を受けられる
子どもが2人いる場合、「長男は夫の扶養、次女は妻の扶養」というように、夫婦で一人ずつ扶養を分けることが制度上可能です。
税金面では、この「扶養の分散」が有効な場合があります。
例えば、夫婦ともに所得が高く所得税率が同じくらいの場合、一人ずつ扶養控除を受けることで、それぞれの税負担をバランスよく軽減できます。
健康保険については、原則通り「子どもは全員、収入の多い方の親の扶養にまとめる」のが基本です。
ただし、夫婦の収入が同程度の場合など、健康保険組合によっては子どもごとに扶養を分けることを認めるケースも稀にあります。これは組合の判断によるため、希望する場合は夫婦それぞれの勤務先に確認が必要です。
扶養手当が会社ごとに異なるので確認必須
扶養を分けるかどうかを考える上で、非常に重要なのが会社の「扶養手当(家族手当)」です。
これは法律で定められた制度ではなく、会社が独自に設けている福利厚生のため、支給条件や金額は会社によって全く異なります。
- 1人あたりの金額が違うケース
- 夫の会社:1人目 20,000円、2人目以降 10,000円
- 妻の会社:扶養人数にかかわらず1人 15,000円
- 支給条件が違うケース
- 「税制上・社会保険上の両方で扶養していること」を条件とする会社もある
例えば上記のケースで、夫が2人を扶養すれば手当は月30,000円ですが、夫婦で1人ずつ分けると、夫20,000円+妻15,000円=月35,000円となり、分けた方が有利です。
単純な税金の計算だけでなく、この扶養手当の総額が世帯として最大になる組み合わせを探すことが、手取りを増やす上で欠かせません。
夫婦それぞれの会社の就業規則を確認したり、人事・総務部に問い合わせたりして、正確な情報を把握しましょう。
共働き高所得世帯は「所得金額調整控除」の対象になることも
夫婦ともに収入が高い世帯(年収850万円超)の場合、「所得金額調整控除」という制度が関係してきます。これは、特定の条件を満たす高所得者の税負担を軽減するための控除です。
この控除の適用条件の一つに「本人が特別障害者である、または年齢23歳未満の扶養親族を有する」というものがあります。
もし夫婦ともに年収850万円を超えており、子どもが2人いる場合、扶養を1人ずつに分けることで、夫婦それぞれがこの控除の対象となり、2人分の控除を受けることができます。
もしどちらか一方が2人とも扶養していると、控除を受けられるのはその1人だけになってしまいます。
高所得の共働き夫婦にとって、扶養を分けるかどうかはこの所得金額調整控除の適用に直結する可能性があるため、非常に重要な判断ポイントと言えるでしょう。(参照:国税庁 No.1411 所得金額調整控除)
共働きで扶養で具体的にどれくらい差が出る?【シミュレーション例】

「理屈はわかったけれど、実際にどれくらい金額に差が出るの?」と感じる方も多いでしょう。
ここでは、具体的なモデルケースを用いて、扶養の選び方によって世帯の税負担がどう変わるのかをシミュレーションしてみます。
- 子どもは16歳(扶養控除の対象)
- 社会保険料は給与収入の15%、基礎控除は48万円と仮定
- 給与所得控除、所得税率、住民税率(10%と仮定)は国税庁等の定める計算式に基づき算出
- 計算を簡略化するため、復興特別所得税やその他の控除、会社の扶養手当は考慮しない
ケース①|夫500万・妻300万で扶養者を変えた場合の差
まずは夫婦の収入に差がある、一般的な共働き世帯のケースです。
| 比較項目 | A:収入が多い夫の扶養に入れる | B:収入が少ない妻の扶養に入れる |
| 夫の年間税額 | 約29.8万円 | 約36.9万円 |
| 妻の年間税額 | 約16.3万円 | 約11.2万円 |
| 世帯合計の年間税額 | 約46.1万円 | 約48.1万円 |
| 差額 | Bに比べて約2万円負担低 | Aに比べて約2万円負担増 |
このケースでは、やはり収入が多い夫が扶養控除を受けた方が、世帯全体での税負担が年間約2万円軽くなる結果となりました。
これは、夫に適用される所得税率の方が妻よりも高いため、同じ控除額でも、夫が使った方がより大きな節税効果(税金が安くなる効果)を得られるからです。
ケース②|夫婦とも600万で2人の子どもを分けた場合
次に、夫婦の収入が同程度で、16歳の子どもが2人いるケースを考えてみます。
| 比較項目 | A:夫が2人とも扶養に入れる | B:夫婦で1人ずつ扶養を分ける |
| 夫の年間税額 | 約48.5万円 | 約56.8万円 |
| 妻の年間税額 | 約65.1万円 | 約56.8万円 |
| 世帯合計の年間税額 | 約113.6万円 | 約113.6万円 |
| 差額 | 合計額は変わらない |
夫婦の収入(=所得税率)が同じ場合、扶養控除をどちらが使っても、また、どのように分けても、世帯全体で支払う税金の合計額は変わらないという結果になりました。
シミュレーションから見える「損しない扶養の選び方」
これらのシミュレーションから、損しない扶養の選び方の基本戦略が見えてきます。
- 夫婦の収入に差がある場合: 税金面だけを考えれば、収入が多い方が扶養控除を受けるのが鉄則です。
- 夫婦の収入が同程度の場合: 税金面での有利不利は発生しません。したがって、夫婦それぞれの会社の「扶養手当」の支給条件を比較し、世帯としての手当総額が最も多くなる方法を選ぶのが最も合理的と言えるでしょう。
まずは税金の原則を理解し、その上でご自身の家庭の状況に合わせて福利厚生などのプラスアルファ要素を比較検討することが、最適な選択につながります。
扶養を変更したいときの手続きと注意点

一度決めた扶養の状況も、夫婦の働き方や収入の変化によって見直すべきタイミングが訪れます。
扶養の変更はいつでも可能ですが、「健康保険」と「税金」で手続きの方法やタイミングが異なるため、注意が必要です。いざという時に慌てないよう、基本的な流れを理解しておきましょう。
タイミングは「昇給・転職・育休」など収入変動時
扶養の見直しを検討すべき最も代表的なタイミングは、夫婦の収入バランスが大きく変わった時です。
- 昇給・転職:夫婦のどちらかが昇給・転職し、収入が逆転した、あるいは収入差が大きくなった・小さくなった。
- 育休・復職:妻(または夫)が育児休業に入ると、給与の支払いが止まり、代わりに非課税の「育児休業給付金」が支給されます。
この期間は一時的に収入が大きく減少(またはゼロ)になるため、もう一方の配偶者の扶養に切り替えるのが一般的です。そして仕事に復職する際は、再び収入状況を確認し、必要であれば扶養を元に戻す手続きをします。
- 働き方の変更:どちらかが正社員からパート勤務に切り替えた、あるいはその逆など、雇用形態が変わった時も見直しのタイミングです。
基本的には、年末調整の時期などに年に一度、世帯の状況を確認する習慣をつけておくと良いでしょう。
健康保険の扶養変更は両方の保険組合で手続きが必要
健康保険の扶養変更は、税金の手続きに比べて少し手間がかかります。
基本的には「扶養から外す」手続きと、「扶養に入れる」手続きを、夫婦それぞれの会社を通じて行う必要があります。
- 現在の扶養者(Aさん)の会社での手続き
- Aさんは自分の会社の担当部署(人事・総務など)に、子どもを扶養から外したい旨を伝えます。
- 「被扶養者(異動)届」などを提出し、「資格喪失証明書」を発行してもらいます。
- 新たな扶養者(Bさん)の会社での手続き
- Bさんは自分の会社の担当部署に、子どもを扶養に入れたい旨を伝えます。
- Aさんの会社で発行された「資格喪失証明書」のほか、夫婦双方の収入証明書類などを添えて「被扶養者(異動)届」を提出します。
注意点として、手続きには期限が設けられていることが多く、収入変動の事実が発生してから5日以内など、速やかな対応が求められます。
手続きが遅れると、子どもの健康保険が一時的になくなってしまう期間が生まれる可能性もあるため、変更が必要になったらすぐに夫婦それぞれの会社に相談しましょう。
税制上の扶養は年末調整または確定申告で簡単に切り替え可能
税制上の扶養変更は、健康保険に比べて非常にシンプルです。
会社員の場合、毎年行われる「年末調整」のタイミングで、扶養者を変更できます。
具体的には、年末に会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類の記入内容を変えるだけです。
- 新たに扶養する親:申告書の「控除対象扶養親族」の欄に、子どもの氏名やマイナンバーなどを記入します。
- 扶養から外す親::申告書の該当欄を空欄にして提出します。
夫婦がそれぞれ自分の会社でこの申告を行うだけで、手続きは完了です。
健康保険のように、会社間で書類をやり取りする必要はありません。
自営業の方や、年末調整で手続きを忘れた場合は、確定申告で扶養の状況を申告することになります。
迷ったらプロに相談!共働き扶養の悩みは『マネドア』で解決

ここまで、共働き夫婦の子どもの扶養について、制度の違いやケース別の選び方を解説してきました。
しかし、「ルールはわかったけれど、自分の家庭に当てはめるとどうなるんだろう?」「扶養手当や他の控除も考えると、どちらが最適なのか確信が持てない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
税金や社会保険の制度は複雑で、ご家庭の収入状況や会社の福利厚生、今後のライフプランによって最適な選択は変わってきます。
一つの選択ミスで年間数万円の差が生まれる可能性を考えると、専門家の視点から客観的なアドバイスをもらうのが最も確実な方法です。
そんな時に頼りになるのが、お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)です。
無料FP相談サービス「マネドア」では、家計管理や資産形成のプロに、子どもの扶養の選び方といった具体的な悩みから、教育資金や住宅ローンといった将来のお金のことまで、幅広く相談できます。
オンラインでの相談も可能なので、忙しい共働き夫婦でも自宅から気軽に利用できるのが魅力です。
専門家と一緒にご家庭の状況を整理し、シミュレーションしてもらうことで、納得のいく最適な選択ができるでしょう。
扶養のことで少しでも迷いや不安があれば、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。