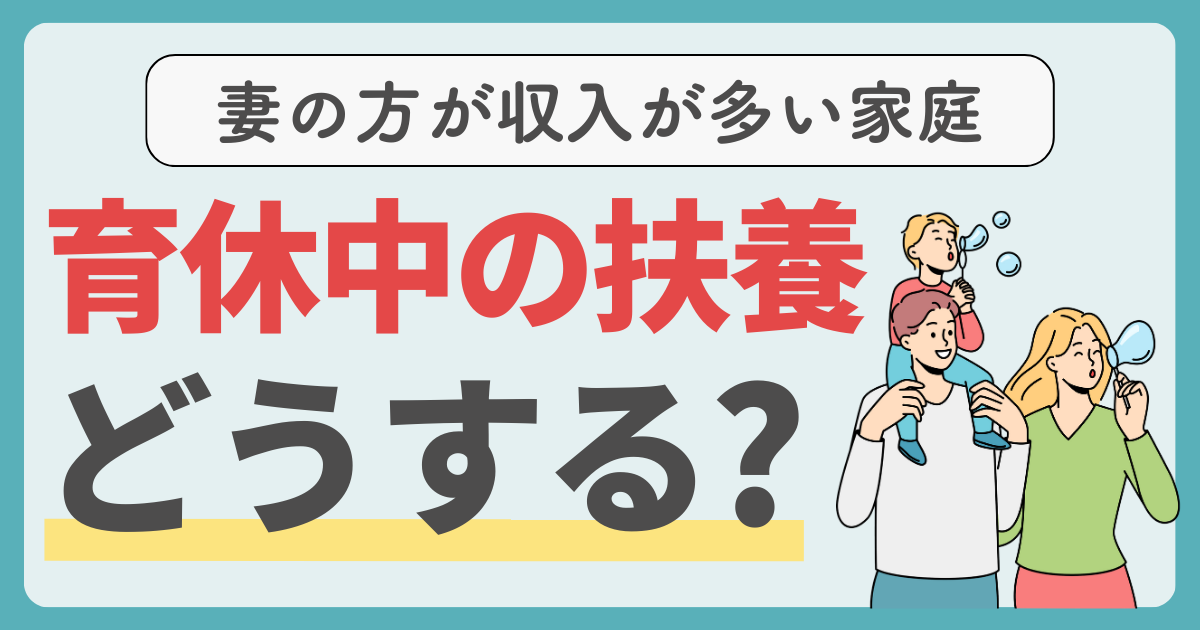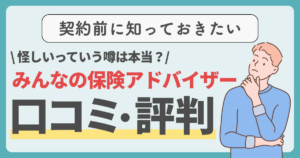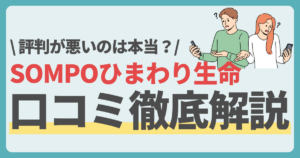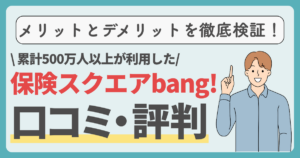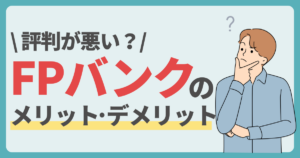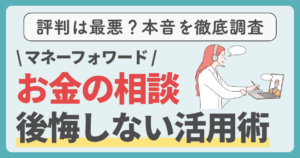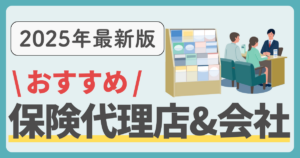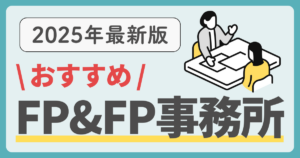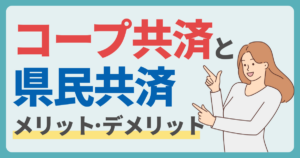「妻のほうが夫より収入が多い」という家庭は、今や珍しくありません。
しかし、妻の妊娠・出産を機に、多くの家庭が「扶養」という複雑な壁に直面します。
「子どもの扶養は、収入が多い方に入れるのが基本って聞くけど、育休中は収入が減るから夫の方に移すべき?」 「育休中、妻は夫の扶養に入れるの?メリットはある?」 「税金と社会保険で扶養のルールが違うみたいで、よくわからない…」
こうした悩みは、制度を正しく理解すれば解決できます。
手続きを間違えると、本来受けられるはずの控除が受けられず、世帯全体で損をしてしまう可能性も。
この記事では、妻の方が収入が多い家庭が育休期間を迎えるにあたり、最も損しない「扶養」の選択ができるよう、税金・社会保険の基本から、お子様や配偶者の扶養に関する具体的な手続きまで、分かりやすく解説します。
- 妻が高収入な家庭における「扶養」の基本的な考え方
- 「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の決定的な違い
- 育休中に子どもの扶養をどう判断すればよいか
- 妻が夫の扶養に入る条件と、税金がどれくらい軽くなるかの目安
- 必要な手続きと申請のタイミング
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
妻の方が収入が多い家庭で育休中に考えるべき扶養の基本

「扶養」と一言でいっても、実は「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれルールが異なります。
この違いを理解することが、損しない選択をするための第一歩です。
まずは、子どもの扶養と配偶者の扶養について、基本的な考え方を押さえておきましょう。
子どもの扶養は「収入が多い親」が原則
お子様が生まれた場合、健康保険の扶養は、原則として年間収入が多い方の親に入れることになります。
これは、夫婦どちらか一方の扶養にしか入れないためです。
多くの健康保険組合では、夫婦双方の収入を比較し、より収入が多い方の扶養に入れるよう指導しています。
これは、保険料の負担と保険給付のバランスを保ち、制度を公平に維持するためのルールです。
たとえば、全国健康保険協会(協会けんぽ)なども、この基準を基本としています。
そのため、普段から妻の収入が夫を上回っている家庭では、お子様は妻の健康保険の扶養に入れるのが基本となります。
妻の育休で収入が一時的に減っても扶養変更は不要
「育休中は妻の収入がなくなるから、子どもの扶養を夫の方に移した方がいいのでは?」と考える方も多いかもしれません。
しかし、結論から言うと、育休という一時的な収入減少を理由とした扶養の変更は、原則として不要です。
健康保険の扶養認定では、過去の収入や今後の収入見込みなどから、恒常的な収入状況を見て判断します。
育児休業はあくまで一時的なものであり、職場復帰後は元の収入に戻ることが前提です。
そのため、多くの健康保険組合では、育休期間中も復帰後の収入見込み(=育休前の収入)を基準に判断するため、扶養を移動させる必要はないと定めています。
自己判断で手続きを進める前に、まずは夫婦双方の会社の担当者や健康保険組合に確認しましょう。
「妻の方が収入が多い」場合の配偶者控除の考え方
子どもの社会保険とは別に、育休中の妻が、夫の「税法上の扶養」に入り、夫が配偶者控除を受けるという選択肢は非常に重要です。
通常、妻の収入が多い家庭では、妻の年収が所得の基準(合計所得金額48万円/給与収入103万円)を大きく超えているため、夫が配偶者控除を受けることはありません。
しかし、妻が育休を取得すると状況が変わります。
例えば、年の途中から産休・育休に入り、その年の給与収入が103万円以下に収まったとします。
このとき、産休中の「出産手当金」や育休中の「育児休業給付金」は非課税所得のため、税金の計算上は収入にカウントされません。
その結果、妻の合計所得金額が48万円以下となり、夫が「配偶者控除」の適用を受けられる可能性が出てきます。
これにより夫の所得税・住民税が軽減され、世帯全体の手取りを増やすことにつながります。(参考:国税庁No.1191 配偶者控除)
共働き夫婦の扶養は2種類|税制上と社会保険上の違い

「扶養」と一言でいっても、実は2つの全く異なる制度があります。
一つは所得税や住民税に関わる「税法上の扶養」、もう一つは健康保険や年金に関わる「社会保険上の扶養」です。
この2つの目的とルールをしっかり区別して理解することが、最適な選択をするためのカギとなります。
税法上の扶養|配偶者控除・扶養控除で節税できる
こちらは、納税者の税金の負担を軽くするための制度です。
扶養する家族がいる場合、納税者の所得から一定額を差し引く「所得控除」が適用され、課税対象の所得が減ることで節税につながります。
- 目的
- 所得税・住民税の負担軽減
- 所得税・住民税の負担軽減
- 主な控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者の所得額に応じて適用
- 扶養控除:16歳以上の子どもや親族などが対象
- 収入の壁
- 123万円の壁:扶養される人の給与収入が123万円以下(合計所得金額48万円以下)の場合、扶養する人は「配偶者控除」や「扶養控除」を満額受けられます。
- 201万円の壁:配偶者の給与収入が103万円を超えても、201万6千円未満までであれば、収入に応じて段階的に「配偶者特別控除」が適用されます。(参考:国税庁No.1191 配偶者控除)
- 123万円の壁:扶養される人の給与収入が123万円以下(合計所得金額48万円以下)の場合、扶養する人は「配偶者控除」や「扶養控除」を満額受けられます。
社会保険上の扶養|保険料を免除できる収入要件
こちらは、健康保険料や国民年金保険料の支払いが免除される制度です。
扶養に入ると、自分で保険料を納めなくても健康保険証を持つことができ、年金の加入期間にも算入されます(国民年金第3号被保険者)。
- 目的
- 健康保険料・国民年金保険料の本人負担をなくすこと
- メリット
- 保険料負担なしで健康保険に加入できる
- 将来の年金受給資格期間に算入される
- 収入の壁
- 130万円の壁:扶養される人の年間収入が130万円未満であることが基本です。これには給与だけでなく、交通費や各種手当も含まれます。
- 一時的な収入増への対応:政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、人手不足による残業などで一時的に収入が130万円を超えても、事業主がその旨を証明すれば、引き続き扶養に入り続けられる仕組みができています。(参考:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」)
- 130万円の壁:扶養される人の年間収入が130万円未満であることが基本です。これには給与だけでなく、交通費や各種手当も含まれます。
「妻が多く稼ぐ家庭」ならどちらを優先すべき?
2つの制度をふまえ、妻の収入が多い家庭では「社会保険のルールを最優先し、その上で税金のメリットを考える」のが正解です。
- 社会保険はルールを遵守
子どもの健康保険は、原則として収入の多い親(=妻)の扶養に入れるというルールに従います。これは個人の意思で選べるものではないため、まずはこのルールを守ることが大前提です。
- 税金は戦略的に選択
税法上の扶養は、その年の所得が固まった時点で、世帯として最も有利な方法を選べます。
例えば、「子どもの健康保険は妻の扶養に入れたまま、育休で所得が減った妻自身と子どもの”税法上の扶養”は夫の控除対象にする」という組み合わせが可能です。
これにより、社会保険のルールを守りつつ、世帯全体での節税効果を最大化できます。
妻が育休中に「子どもの扶養」をどうする?

妻の育休期間中、世帯の収入状況が大きく変わるため「生まれた子どもの健康保険は、夫と妻どちらに入れるべき?」と悩むのは当然です。
ここでは、子どもの扶養に関するルールと、具体的な手続きについて詳しく解説します。
年収が高い親の健康保険に加入させるのが原則
共働き家庭において、生まれた子どもを健康保険の扶養に入れる場合、原則として年間収入が多い方の親に入れると定められています。
これは、夫婦がそれぞれ別の健康保険に加入している場合、どちらか一方の扶養にしか入れないためです。
この「年間収入」とは、過去の収入や将来の見込みなどから算出される「恒常的な収入」を指します。
健康保険組合はこの基準をもとに判断するため、基本的には「普段、多く稼いでいる親」の扶養に入れることになります。
育休中の収入減少で扶養を切り替える必要はある?
「育休中は妻の収入がゼロになるから、夫の扶養に切り替えるべき?」という疑問が最も多いですが、結論から言うとその必要はありません。
2021年8月の厚生労働省の通達により、育児休業中の収入減少は「一時的なもの」と見なされることになりました。
被扶養者(子ども)の地位を安定させる観点から、育休前の収入状況を基準に判断するため、育休を理由に扶養を親から親へ移動させる手続きは原則不要とされています。
収入逆転したときの扶養切り替え手続き(必要書類・時期)
育休中の一時的な収入減ではなく、妻の職場復帰後に働き方が変わり、恒常的に夫の収入が妻を上回るなど、夫婦の収入状況が永続的に逆転した場合は、扶養の切り替え手続きが必要です。
その際は、収入が少なくなった親(妻)が自分の会社で子どもの扶養を外す手続き(資格喪失手続き)を行い、それと同時に、収入が多くなった親(夫)が自分の会社に子どもの扶養に入れる手続き(資格取得手続き)を行います。
- 提出書類
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 収入状況が逆転したことを証明する書類(妻の直近の給与明細の写しや、所得証明書など、健保組合の指示に従う)
- 提出時期
- 収入逆転の事実が発生してから、速やかに行います(原則5日以内)。
新生児を扶養に入れるときの申請フロー
子どもが生まれたら、以下の流れで健康保険の加入手続きを進めましょう。収入が多い方の親の会社を通じて行います。
- 役所へ出生届を提出する
- 生まれた日を含めて14日以内に、お住まいの市区町村役場に「出生届」を提出します。
- 生まれた日を含めて14日以内に、お住まいの市区町村役場に「出生届」を提出します。
- 赤ちゃんのマイナンバーを確認する
- 出生届が受理されると、赤ちゃんの住民票が作成されます。役所で「住民票の写し」を取得すれば、そこに記載されているマイナンバー(個人番号)を確認できます。
- 出生届が受理されると、赤ちゃんの住民票が作成されます。役所で「住民票の写し」を取得すれば、そこに記載されているマイナンバー(個人番号)を確認できます。
- 勤務先に「被扶養者(異動)届」を提出する
- 収入が多い方の親が、勤務先の担当部署から「健康保険 被扶養者(異動)届」をもらいます。
- 必要事項と赤ちゃんのマイナンバーを記入し、原則として出生から5日以内に勤務先に提出します。
- 万が一、手続きが遅れても、出生日にさかのぼって保険が適用されるのが一般的なので、焦らず正確に手続きを進めましょう。提出後、1〜2週間ほどで赤ちゃんの健康保険証が交付されます。
妻を夫の扶養に入れるメリットは?育休中の配偶者控除を解説
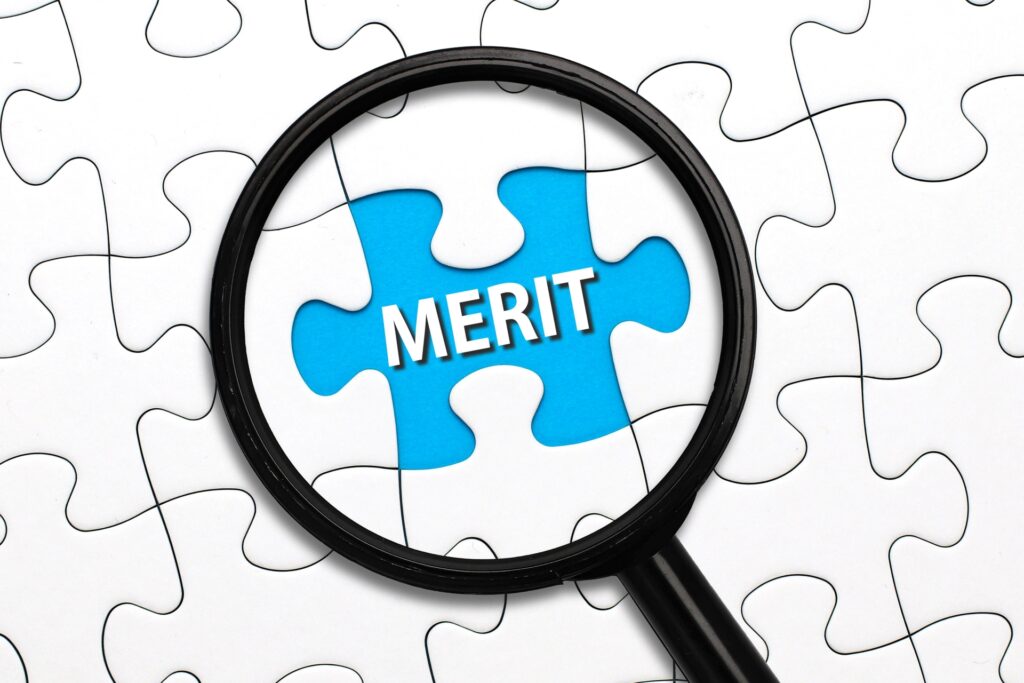
子どもの扶養とは別に、育休で収入が減少した妻自身が夫の「税法上の扶養」に入ることで、世帯全体の税負担を大きく軽減できる可能性があります。
これは育休期間中にぜひ活用したい制度です。ここでは、その条件やメリット、具体的な手続きについて解説します。
妻の年収が201万6千円以下なら配偶者控除・特別控除の対象
夫が妻を扶養に入れて税金の控除を受けるためには、妻の年間の給与収入が一定額以下である必要があります。控除には2種類あります。
- 配偶者控除
- 妻の年間の給与収入が123万円以下の場合に適用されます。夫は最大で38万円の所得控除を受けられます。(※夫の合計所得金額が900万円以下の場合)
- 妻の年間の給与収入が123万円以下の場合に適用されます。夫は最大で38万円の所得控除を受けられます。(※夫の合計所得金額が900万円以下の場合)
- 配偶者特別控除
- 妻の年間の給与収入が123万円を超えても201万6千円未満の場合に適用されます。妻の収入額に応じて、夫が受けられる控除額が段階的に変動します。(参考:国税庁 No.1195 配偶者特別控除)
育休に入るタイミングによっては、妻のその年の給与収入がこの基準内に収まるケースは少なくありません。
出産手当金・育休給付金は非課税!扶養判定に含めなくてOK
ここで最も重要なポイントは、健康保険から支給される「出産手当金」や、雇用保険から支給される「育児休業給付金」は、税金の計算上、収入として扱われない(非課税所得)という点です。
例えば、その年の妻の給与収入が80万円で、それとは別に育児休業給付金を100万円受け取ったとします。
この場合、税法上の扶養を判定する際の妻の収入は「80万円」と見なされます。
そのため、給付金をいくら受け取っていても、給与収入が123万円以下であれば、夫は「配偶者控除」を満額受けることができるのです。(参考:国税庁 No.1400 給与所得)
妻を夫の扶養に入れると夫婦の税負担はいくら減る?
実際に配偶者控除を適用すると、どのくらい税金が安くなるのでしょうか。シミュレーションしてみましょう。
- 【前提条件】
- 夫の課税所得:500万円(所得税率20%)
- 妻のその年の給与収入:70万円(配偶者控除38万円の対象)
- 住民税率:一律10%
- 【軽減される税額の計算】
- 所得税の軽減額:38万円 (控除額) × 20% (所得税率) = 76,000円
- 住民税の軽減額:33万円 (住民税の控除額) × 10% (住民税率) = 33,000円
- 合計軽減額:76,000円 + 33,000円 = 109,000円
このケースでは、年間で約11万円、世帯の税負担が軽くなります。これは家計にとって非常に大きなメリットです。
年末調整や確定申告での手続き方法
配偶者控除を受けるための手続きは、夫の会社で行う「年末調整」が最も簡単です。
秋頃に会社から配布される「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類に、妻の名前やマイナンバー、その年の見込みの所得金額を記入して提出します。
育休により妻の給与収入が基準額以下になる見込みであれば、忘れずに申告しましょう。
もし年末調整で申請を忘れてしまっても、翌年に夫自身が「確定申告」をすることで、払い過ぎた税金を取り戻す(還付を受ける)ことが可能です。
妻の方が収入が多い家庭は「育休中の扶養」を正しく選んで損しないように

妻の収入が夫を上回る家庭にとって、育休中の「扶養」の選択は、家計に大きく影響する重要なポイントです。
制度が複雑で難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば、最適な判断ができます。
これまでの内容を振り返り、損をしないための考え方を整理しましょう。
扶養の判断は「誰が多く稼ぐか」だけでなく制度の違いも重要
この記事で繰り返しお伝えしてきた通り、「扶養」には税金に関わるものと社会保険に関わるものの2種類が存在します。
- 社会保険の扶養(子どもの健康保険): これは「原則、収入が多い親に入れる」というルールです。育休による一時的な収入減では変更不要、という点をしっかり覚えておきましょう。
- 税法上の扶養(配偶者控除など): こちらは、その年の所得状況に応じて、世帯で最も節税効果が高くなるように選択できる「戦略」です。
この2つを明確に区別することが、最初のステップです。
税金・保険料・子どもの保険をトータルで最適化する視点を
最終的に目指すべきは、世帯全体で見たときの最適化です。
妻が高収入の家庭が育休を取得した場合のベストな組み合わせは、多くの場合以下のようになります。
- 子どもの健康保険 → ルール通り妻の扶養に入れる
- 妻自身の社会保険 → 育休中の保険料免除制度を活用する
- 税法上の扶養 → 育休で所得が減った妻と子を、夫の扶養に入れる(夫が配偶者控除・扶養控除を受ける)
この形をとることで、社会保険のルールを守りつつ、税金の負担を合法的に最大限軽くすることが可能です。
家計の不安は専門家に相談!無料FP相談サービス『マネドア』で早めに解決

この記事では扶養の基本を解説しましたが、「うちの場合は、具体的にいくら節税できるの?」「出産を機に、今後の教育費や保険も見直したい」など、個別の悩みや不安も出てくるかと思います。
そんな時は、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのがおすすめです。
無料FP相談サービス「マネドア」なら、家計や保険、資産運用など、お金に関する幅広い悩みを専門家に無料で何度も相談できます。
今回の扶養の話はもちろん、これからかかる教育費の準備や、家族に合った保険の見直しなど、あなたの家庭に合わせた具体的なアドバイスをもらえます。
オンラインでの相談も可能なので、育児の合間でも気軽に利用できるのが魅力です。
少しでも不安があれば、早めに専門家の力を借りて、安心の家計プランを立てましょう。