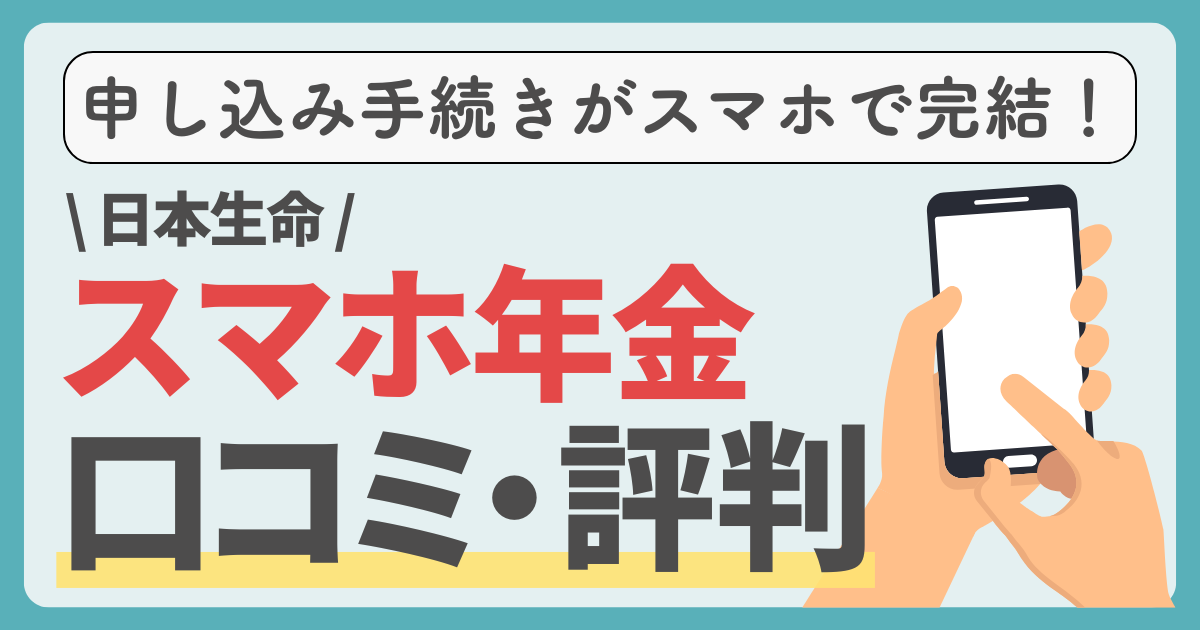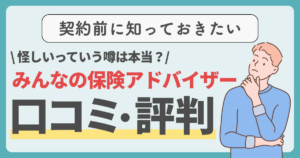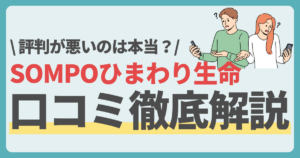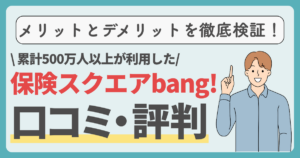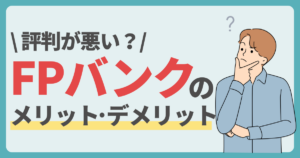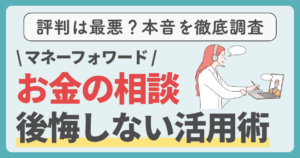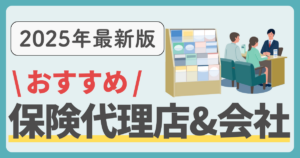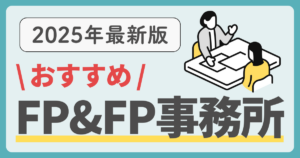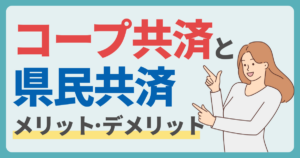「老後2,000万円問題」という言葉に、将来のお金について漠然とした不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
特に20代・30代の方にとって、老後はまだ遠い未来の話に感じられ、何から手をつけて良いか分からないかもしれません。
そんな中、大手保険会社である日本生命が提供を開始したのが、スマホひとつで申し込みから管理まで完結する「スマホ年金」です。
月々5,000円からという手軽さで、これまで保険や年金にハードルを感じていた若い世代でも始めやすいと注目を集めています。
しかし、「本当にスマホだけで大丈夫?」「デメリットはないの?」といった疑問も浮かびますよね。
この記事では、日本生命の「スマホ年金」の仕組みから、実際の利用者の口コミ・評判、そしてどんな人におすすめなのかまで、分かりやすく徹底解説します。
- 日本生命「スマホ年金」の基本的な仕組みと特徴
- スマホで手軽に始められる具体的なメリット
- 加入前に知っておきたいデメリットや注意点
- 実際に利用した人のリアルな口コミ・評判
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
そもそも日本生命「スマホ年金」とは?

日本生命の「スマホ年金」は、正式名称を「ニッセイみらいのカタチ 年金保険(スマホ年金)」といい、その名の通り、申し込み手続きのすべてがスマートフォンで完結する、新しい形の個人年金保険です。
対面での相談や複雑な書類のやり取りといった、従来の保険加入のイメージを覆す手軽さが最大の特徴で、デジタルに慣れ親しんだ世代のライフスタイルに合わせて設計されています。
まずは、この「スマホ年金」が具体的にどのような商品なのか、その仕組みから見ていきましょう。
スマホ操作だけで加入完了!若年層でも始めやすい商品設計
「スマホ年金」の最大の特徴は、保険の申し込みから契約内容の確認、住所変更などの各種手続きまで、そのすべてがスマートフォン上で完結する点にあります。
従来、保険に加入する際は、担当者と対面で話したり、分厚いパンフレットや契約書類を郵送でやり取りしたりする必要がありました。
しかし「スマホ年金」では、そうした手間は一切かかりません。公式サイトから必要情報を入力し、スマホのカメラで本人確認書類を撮影・アップロードするだけで手続きが完了します。
また、加入時の健康状態に関する告知も、3つの質問に「はい/いいえ」で答えるだけ。
このシンプルな設計は、保険の専門知識がまだ少ない20代・30代の方や、仕事や家事で忙しく、ゆっくり時間を取れない方でも、自分のペースで気軽に老後への備えをスタートできるよう工夫されています。
月5,000円〜OK!シンプルな保障と返戻率の仕組み
「スマホ年金」が若年層に支持される理由の一つが、そのシンプルさと始めやすさです。
ここでは、具体的な保険料と、お金がどのように増えていくのかという「返戻率」の仕組みについて解説します。
貯蓄が目的のシンプルな保障
個人年金保険は、亡くなった時の保障(死亡保障)よりも、着実に老後資金を準備すること(貯蓄)を目的とした商品です。
「スマホ年金」の保障も非常にシンプルで、保険料の払込期間中に万が一亡くなられた場合は、それまでに払い込んだ保険料の総額に相当する金額が死亡給付金としてご遺族に支払われます。
掛け捨てではないため、万が一のことがあっても支払った保険料が無駄にならないという安心感があります。
返戻率と配当金の仕組み
返戻率(へんれいりつ)とは、「支払う保険料の総額に対して、将来受け取れる年金の総額がどれくらいの割合か」を示す数値です。
例えば、返戻率が105%なら、支払った保険料の1.05倍の金額が年金として戻ってくる計算になります。
日本生命の公式サイトによると、「スマホ年金」は将来の楽しみの一つとして、会社の収益状況に応じて分配される「配当金」が上乗せされる仕組みになっています。
この配当金を含めた返戻率は、契約条件によって異なりますが、ひとつのモデルケースが示されています。
ただし、この配当金は運用実績によって変動し、将来の支払いが保証されているものではないという点は、理解しておくべき重要なポイントです。
従来の「みらいのカタチ」との違いはここ
「スマホ年金」の正式名称は「ニッセイみらいのカタチ 年金保険」であり、保険の基本的な仕組みは対面で加入する従来の商品と同一です。
しかし、スマートフォンから手軽に申し込めるように、加入できるプランがあらかじめ限定されている点が大きな違いです。
具体的には、申し込み方法や選択できるプランの内容が異なります。
従来のニッセイ みらいのカタチ 年金保険は加入できる年齢が7歳から65歳に対し、スマホ年金は18歳から55歳となっています。
「スマホ年金」は保険料や年金の受け取り方といったプランの選択肢を絞ることで、利用者が迷わずスピーディに手続きできるように設計されています。
一方、従来の対面での申し込みでは、専門の担当者と相談しながら、より自分のライフプランに合わせた細かな設計が可能です。
どちらが良いというわけではなく、「手軽さと分かりやすさを重視するか」「専門家のアドバイスを受けながら、より柔軟な設計をしたいか」というニーズによって、最適な申し込み方法が異なると言えるでしょう。
日本生命スマホ年金が選ばれる4つのメリット

手軽さが魅力の「スマホ年金」ですが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。多くの人に選ばれる理由は、単に「スマホで完結するから」だけではありません。
ここでは、時間的な制約、金銭的なハードル、そして将来への備えといった様々な観点から、スマホ年金が持つ4つの大きなメリットを掘り下げていきます。
メリット①|面倒な手続きゼロ。スマホだけで完結できる安心感
最大のメリットは、やはり「徹底した手続きの簡略化」にあります。
保険の加入を検討する際、多くの人がハードルに感じるのが「平日の昼間に相談窓口へ行く時間がない」「担当者と対面で話すのは少し緊張する」「大量の書類に目を通して署名・捺印するのが面倒」といった点です。
「スマホ年金」は、これらの障壁をすべて取り払いました。自分の好きなタイミングで申し込みができ、誰にも気兼ねすることなく、納得いくまで自分のペースで検討を進められます。
手続きをスムーズに進めるために、あらかじめ以下の3点を準備しておきましょう。
- 金融機関の口座情報
- 保険料の引き落とし口座として登録します。
- 保険料の引き落とし口座として登録します。
- クレジットカード
- 初回保険料の支払いに使用できます。
- 必ず契約者本人名義のものを用意してください(旧姓の名義は利用不可)。
(参考:年金受給者でも借りれるカードローンの審査に通るには?年金のみでも借入ok・即日融資・低金利のおすすめカードローンも紹介|カードローンSELECTION)
- 本人確認書類(顔写真付き)
- 運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書のいずれか。
- 書類に記載の住所と現住所が一致している必要があります。
メリット②|少額スタートで“保険っぽくない”感覚で老後資金づくり
「将来のために何か始めたいけれど、保険や投資はまとまったお金が必要そうで手が出せない…」と感じている方は少なくないでしょう。
実際に、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、20代の単身世帯のうち39.5%は金融資産を保有していない(預貯金等を除く)というデータもあります。
実際に、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、20代の単身世帯のうち39.5%は金融資産を保有していない(預貯金等を除く)というデータもあります。(参考:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年))
「スマホ年金」は、こうした資産形成の第一歩を踏み出せないでいる方の背中を、そっと押してくれる商品設計になっています。
月々5,000円からという保険料は、例えば「毎月のカフェ代を少し節約する」「使っていないサブスクを一つ解約する」といった、日々の生活の延長線上で捻出できる金額です。
この手軽さは、従来の「保険に加入する」という重々しい決断とは一線を画します。
まるで毎月自動で引き落とされる習い事の月謝や、お気に入りのサービスに課金するような“保険っぽくない”ライトな感覚で、将来のための貯蓄を始められるのです。
「NISAやiDeCoはまだ少し難しそう」と感じる方でも、「これなら自分にもできそう」と思える心理的なハードルの低さが、大きなメリットと言えます。
メリット③|個人年金保険料控除で節税効果も期待できる
ただお金を貯めるだけでなく、払い込んだ保険料に応じて税金の負担を軽くできる「個人年金保険料控除」が利用できるのも、大きなメリットです。
これは、一定の条件を満たす個人年金保険で利用できる制度で、年間の払込保険料に応じて所得から一定額が控除され、結果的に所得税や住民税が安くなる仕組みです。「スマホ年金」も、この制度の対象となります。
具体的にどれくらい節税になるのか、詳細なモデルケースを見てみましょう。
- モデルケース
- 年収500万円の給与所得者(25歳・独身)
- 年間80,000円の保険料を65歳まで40年間払い続ける場合
この条件の場合、1年間で軽減される税金の額は以下のようになります。
- 所得税の軽減額: 4,100円
- 住民税の軽減額: 2,800円
- 合計:年間 6,900円の節税
そして、この節税効果が40年間続くと…
6,900円 × 40年 = 総額 276,000円
これだけの税負担が軽くなる計算です。
銀行預金にはない、個人年金保険ならではの大きな強みであり、この節税効果を加味すると、実質的な返戻率(リターン)はさらに高まると言えるでしょう。
※上記の例は、40年間年収500万円(独身)であり続け、税率や生命保険料控除制度が変わらないと仮定した場合の計算です。 ※個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合に限ります。(日本生命保険相互会社「ニッセイ みらいのカタチ 年金保険」)
メリット④|返戻率が改善!より堅実になった利回り水準
老後資金を準備する上で、安全性はもちろん、お金が着実に増える「利回り」も重要です。
日本生命は2025年1月2日以降の契約から保険料率を改定し、これまで以上に有利な条件で老後資金を準備できるようになりました。
具体的には、将来の運用実績によって変動する配当金を除いた、確定利回り部分の返戻率が向上しています。
公式サイトに掲載されている改定前後の比較例を見てみましょう。
- 契約例:25歳男性が月払保険料9,998円を65歳まで払い込み、10年確定年金として受け取る場合
- 改定前(~2025/1/1):返戻率 約106.4%
- 改定後(2025/1/2~):返戻率 約111.4%
この例では、払込保険料の総額が約480万円であるのに対し、受け取れる年金総額は約535万円となり、配当金なしでも約55万円増える計算です。
現在の日本の銀行の定期預金金利が年0.002%~0.3%程度であることを考えると、元本保証の安心感を持ちながらこの返戻率を実現できるのは、非常に大きな魅力です。
さらに、この111.4%という数値に、将来の運用実績に応じた「配当金」が上乗せされる可能性があります。
配当金は確定ではありませんが、ベースとなる返戻率が引き上げられたことで、より堅実に、そして安心して老後資金を育てていける商品になったと言えるでしょう。(参考:日本生命保険相互会社「ニッセイ みらいのカタチ 年金保険」)
日本生命スマホ年金のデメリットと注意点
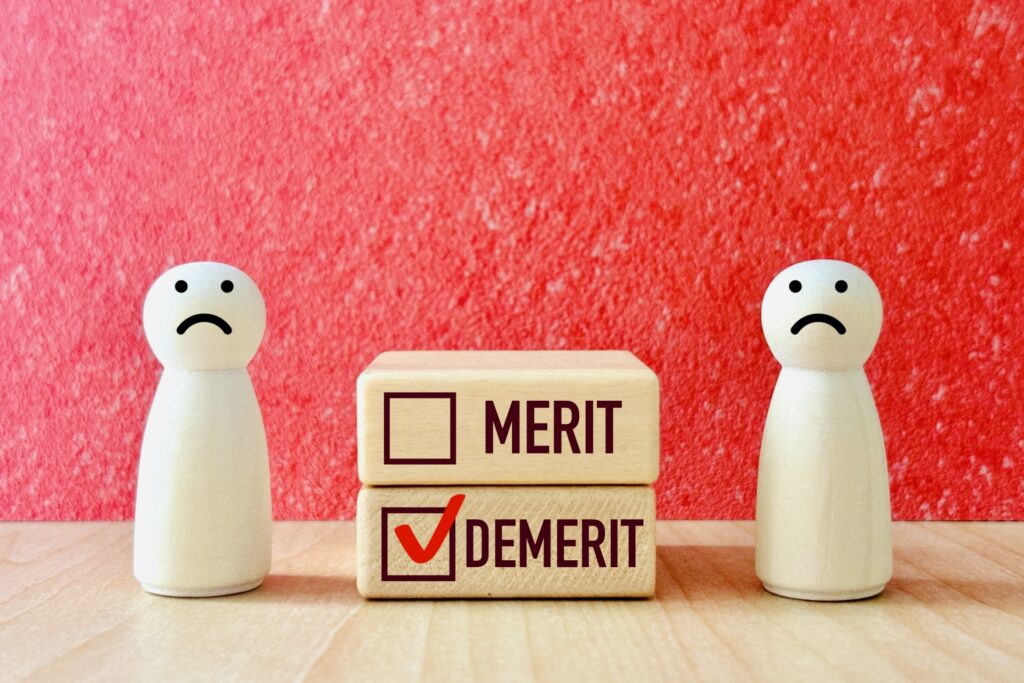
スマホで手軽に始められ、節税効果や堅実な利回りも期待できるなど、多くのメリットがある「スマホ年金」。しかし、どんな金融商品にも必ず注意すべき点や、人によってはデメリットと感じる側面が存在します。
加入してから「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、事前にデメリットと注意点をしっかりと理解しておくことが何よりも重要です。ここでは、特に確認しておきたい3つのポイントを解説します。
デメリット①|選択式の保険料で、柔軟性に欠ける面も
メリット②で「少額から始められる」点をご紹介しましたが、その保険料の設定方法には注意が必要です。
「スマホ年金」の月払保険料は、「5,000円」「10,000円」「15,000円」「20,000円」程度の4パターンの中から選ぶ仕組みになっています。1,000円単位などで自由に金額を設定することはできません。
そのため、「月々7,000円で始めたい」「ボーナス月に合わせて12,000円にしたい」といった、家計に合わせた細かな金額調整ができない点はデメリットと言えます。
また、支払い方法はクレジットカードのみであることもデメリットかもしれません。
これは、プランをシンプルにすることで「分かりやすさ」と「手続きの速さ」を優先した設計になっているためです。
もし、より柔軟に、ご自身のライフプランに合わせて細かく保険料を設定したい場合は、対面で相談しながら加入する従来のプランの方が適しているかもしれません。
デメリット②|配当金は確定ではなく、実質ゼロの年もある
メリットの章で「返戻率」に触れた際にも少し解説しましたが、日本生命のような相互会社が販売する保険商品の特徴である「配当金」の性質は、加入前に必ず理解しておくべき最重要ポイントです。
配当金とは、保険会社が1年間の事業運営を行った結果、予測していたよりも多くの利益(剰余金)が出た場合に、その一部を契約者に還元する仕組みです。
この利益は、主に以下の3つから生まれます。
- 利差益(りさえき):予定していた利率よりも、実際の資産運用がうまくいった場合の利益。
- 死差益(しさえき):予定していた死亡者数よりも、実際の死亡者数が少なかった場合の利益。
- 費差益(ひさえき):予定していた事業経費よりも、実際の経費が少なく済んだ場合の利益。
特に個人年金保険の配当金は、資産運用の成績による「利差益」の影響を大きく受けます。
つまり、配当金は景気や市場の動向に左右され、将来の支払いが約束されたものではないのです。
公式サイトの注意書きにも明記されている通り、運用実績が振るわなかった年度は配当金がゼロになる可能性も十分にあります。
したがって、シミュレーションで示される「配当込み」の高い返戻率は、あくまで「うまくいった場合の参考値」として捉えるべきです。
計画を立てる際は、配当金を含まないベースの返戻率を基準に考え、配当金は「もらえたらラッキー」というくらいの心づもりでいるのが賢明でしょう。
デメリット③|10年未満の解約は元本割れリスクが大きい
「スマホ年金」を検討する上で、最大の注意点と言えるのが「短期解約における元本割れのリスク」です。
元本割れとは、途中で解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)が、それまでに支払った保険料の総額を下回ってしまう状態を指します。
「スマホ年金」を含む多くの個人年金保険は、長期的な資産形成を目的として設計されています。
そのため、保険料の一部は契約の締結・維持にかかる経費にも充てられており、特に加入から年数が浅い段階で解約すると、解約返戻金が払込保険料を大幅に下回ってしまいます。
一般的に、この元本割れのリスクがなくなる(解約返戻金が払込保険料を上回る)までには、少なくとも10年程度の期間が必要とされています。
そのため、「スマホ年金」は「10年以上は使う予定のない、余剰資金で始める」ことが大前提となります。
「数年後にはマイホームの頭金にしたい」「子どもの教育費が必要になるかもしれない」といった、短期~中期で使う可能性のあるお金の預け先としては絶対に向いていません。
必ず、ご自身のライフプランと照らし合わせ、長期で継続できる無理のない金額で始めるようにしましょう。
日本生命スマホ年金を実際に利用した方の口コミ・評判

ここまで「スマホ年金」のメリット・デメリットを解説してきましたが、実際に利用している人はどのように感じているのでしょうか。
保険商品は性質上、家電や食品のように多くの口コミが集まるわけではありませんが、SNSや口コミサイトなどを調査すると、いくつかの共通した評判が見えてきました。良い点・悪い点の両方を見ていきましょう。
良い口コミ・評判
良い口コミとして特に目立ったのは、やはりその「手軽さ」と「安心感」に関する声でした。
- とにかく手続きが簡単でスピーディー
「保険のイメージが変わった」「思い立った時にすぐ申し込めた」といった、手続きの簡便さを評価する声が最も多く見られました。対面でのやり取りが苦手な方や、日中忙しくて時間が取れない方にとって、スマホだけで完結する点は大きな魅力に映っているようです。
- 少額から始められるので心理的なハードルが低い
「月々5,000円なら無理なく始められる」「お試し感覚でスタートできた」など、少額設定であることが、資産形成の第一歩を踏み出すきっかけになっている様子がうかがえます。
- 大手の日本生命だから安心できる
長期間にわたってお金を預けることになるため、「やはり安心感が第一」「聞いたことのない会社は不安」といった理由で、国内最大手である日本生命のブランド力を評価する声も挙がっていました。
悪い口コミ・評判
一方で、悪い口コミや注意喚起としては、これまでに解説してきたデメリットと直結する内容が多く見られました。
- 保険料の変更など、柔軟性に欠ける
「5,000円の次は10,000円というのが不便」「もう少し細かく金額設定したい」といった、プランの柔軟性に関する不満の声です。シンプルさの裏返しとも言えるデメリットが、利用者からも指摘されています。
- NISAやiDeCo(イデコ)と比較すると、リターンは期待できない
「もっと積極的に増やしたいなら投資信託の方が良い」「これは貯蓄に近い商品」といった意見です。これは商品の特性を正しく理解した上での声であり、「スマホ年金」は高いリターンを狙う投資商品ではなく、あくまで元本割れリスクを抑えた「貯蓄性の保険」であることを認識しておく必要があります。
- やはり早期解約時の元本割れが怖い
「急にお金が必要になったらどうしよう」「10年は引き出せないのがネック」など、資金の流動性の低さに関する懸念です。長期的な拘束をデメリットと感じる声は、やはり一定数見られました。
結論|日本生命スマホ年金はこんな人におすすめ

ここまで日本生命の「スマホ年金」について、メリット・デメリット、そして実際の評判を詳しく見てきました。
「スマホで完結する手軽さ」や「節税効果」といった大きなメリットがある一方で、「柔軟性の低さ」や「投資商品と比べた際のリターンの低さ」といった側面も持ち合わせています。
これらの特徴を踏まえると、「スマホ年金」は万人におすすめできる商品というよりは、特定のニーズやライフスタイルを持つ方にこそ、ぴったりの選択肢と言えるでしょう。
忙しくて保険相談に行く時間がない人
平日は仕事で忙しく、休日はプライベートの時間を大切にしたい。
そんな「保険の相談に行く時間も手間も惜しい」と感じている方に、「スマホ年金」は最適です。
店舗へ出向いたり、担当者と日程を調整したりする必要は一切ありません。
通勤中の電車の中や、寝る前の少しの時間を使って、自分のペースで申し込みを完結させることができます。
時間を効率的に使いたい現代人にとって、この上ない利便性を提供してくれます。※申込み手続ご利用時間は月〜土曜日 8:00〜24:00、日曜日/祝日 8:00〜23:30
老後資金づくりを“できることから始めたい”人
「将来は不安だけど、NISAやiDeCoはなんだか難しそう…」と感じて、資産形成の第一歩を踏み出せずにいる方にも「スマホ年金」はおすすめです。
月々5,000円という、まるでサブスクに登録するような感覚で始められる手軽さは、「投資」という言葉に感じるハードルをぐっと下げてくれます。
まずは「将来のために、毎月決まった額を自動で貯めていく」という習慣を身につけることが大切です。
「スマホ年金」は、その最初のステップとして非常に優れたツールと言えます。
節税しながら堅実に貯めたい人
「株価の変動などにハラハラしたくない」「リスクを取るより、着実に、でも銀行預金よりは有利にお金を貯めたい」と考える、安定志向の方にも適しています。
元本割れのリスクを抑えつつ、銀行預金を上回るリターンが期待でき、さらに毎年着実に税金の負担を軽くできる「個人年金保険料控除」というメリットも享受できます。
攻めの投資ではなく、“守り”を重視しながら賢く資産形成をしたいというニーズに、しっかりと応えてくれる商品です。
迷ったらプロに相談もアリ|中立な視点で「自分に合うか」確認しよう

この記事を読んで、「スマホ年金」の魅力や注意点について、理解は深まったけれど、それでも「本当に自分に合っているのかな?」「他の商品とも比べてみたい…」と迷いが残っている方もいるかもしれません。
自分で情報を集めて判断することは非常に大切ですが、時には専門家の客観的な意見を聞いてみることも、後悔のない選択をするための有効な手段です。
保険選びは“比較検討”が命。自分で判断しきれないときは?
老後の資産形成の方法には、「スマホ年金」以外にも、他の保険会社の個人年金保険、iDeCo(個人型確定拠出年金)、つみたてNISAなど、様々な選択肢があります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、どの方法が最適かは、その人の年齢や収入、家族構成、そして将来の目標によって大きく異なります。
一人で全ての選択肢を比較検討し、ベストな答えを導き出すのは至難の業です。そんな時は、お金の専門家であるファイナンシャル・プランナー(FP)に相談してみるのがおすすめです。
中立的な立場から、あなたの状況をヒアリングし、幅広い選択肢の中から最適なプランを提案してくれます。
マネドアなら営業なしで相談OK

「でも、専門家に相談すると、しつこく営業されそう…」と不安に感じる方もいるかもしれません。
そのような方におすすめなのが、オンラインで完結する無料の金融相談サービス「マネドア」です。
「マネドア」は、特定の金融機関に所属しない中立なFPと利用者をマッチングしてくれるプラットフォームで、以下のような特徴があります。
- 相談は何度でも無料
- オンラインで自宅から気軽に相談できる
- 無理な営業や勧誘は一切なしと明記
「スマホ年金に加入しようと思うが、専門家の意見も聞いてみたい」「自分の場合、iDeCoとどっちが良いのか知りたい」といった具体的な相談が可能です。
自分一人で悩み続けるよりも、一度プロの視点を取り入れることで、安心して未来への一歩を踏み出すことができるでしょう。