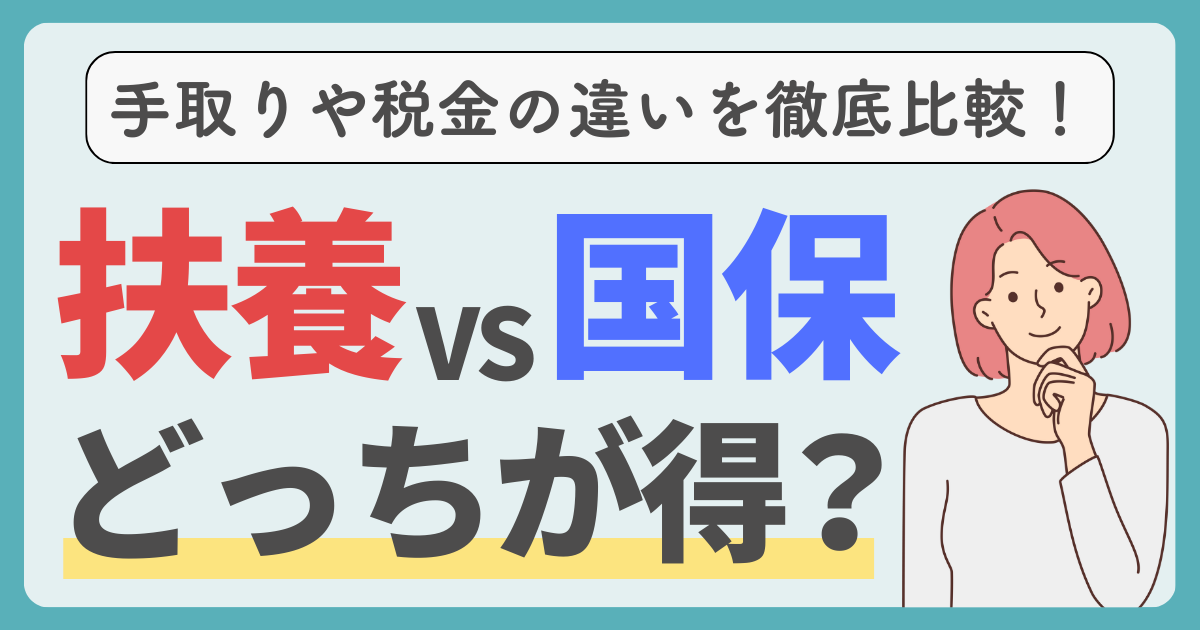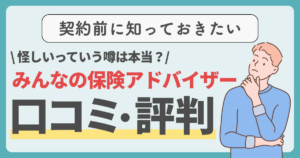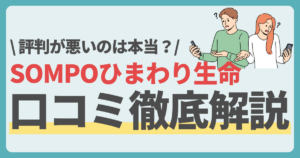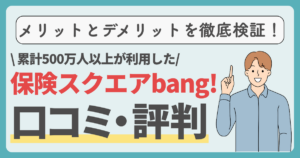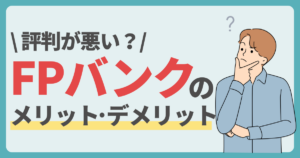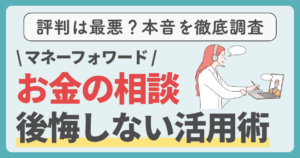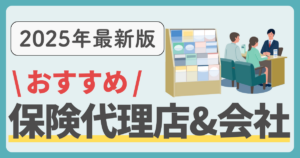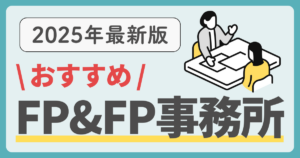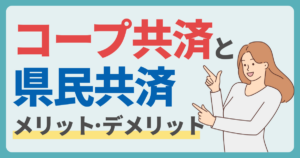パートやアルバイトとして働く際に、「扶養内で働く」のと「扶養から外れて国民健康保険に加入する」のとでは、どちらが本当にお得なのでしょうか。
「扶養に入っていれば保険料の負担がなくて楽」と感じる一方で、「収入の上限を気にして働くのはストレス」と感じる方も少なくありません。
働き方によって手取り額や将来の年金額が大きく変わるため、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身のライフプランに合った選択をすることが重要です。
この記事では、扶養と国民健康保険の基本的な違いから、年収の壁を超えた場合の手取り額の変動、具体的なシミュレーションまで、分かりやすく解説します。
- 扶養と国民健康保険の制度上の根本的な違い
- 「103万円の壁」「130万円の壁」など、年収の壁の意味と超えた場合の影響
- 扶養内で働く場合と扶養から外れた場合、それぞれの保険料や税金の負担額
- ご自身の状況に合わせて最適な働き方を選ぶための判断ポイント
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
そもそも「扶養」と「国民健康保険」の違いとは?

「扶養」と「国民健康保険」、どちらも公的な医療保険制度に関連する言葉ですが、その仕組みや私たちの生活に与える影響は大きく異なります。
働き方を考える上で、この二つの違いを正確に理解しておくことは非常に重要です。
この章では、まず「扶養」とは具体的にどのような状態を指すのか、そして「国民健康保険」は誰がどのような条件で加入するものなのか、それぞれの基本的な定義と仕組みを解説します。
あわせて、働き方を左右する「年収の壁」についても触れていきます。
扶養に入っているとどうなる?
一般的に「扶養に入る」という場合、実は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」という2つの異なる意味合いがあります。
この2つは全く別の制度であり、基準となる年収(いわゆる「壁」)も異なるため、混同しないように注意が必要です。
- 税法上の扶養:これは、納税者である配偶者(扶養者)の税金負担を軽くするための制度です。
あなたの年収が一定額以下の場合、配偶者は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることができ、その結果、所得税や住民税が安くなります。
例えば、あなたのパート年収が103万円以下であれば、配偶者は最大の控除(配偶者控除)を受けられます。(参考:国税庁 No.1191 配偶者控除)
- 社会保険上の扶養:こちらは、健康保険や年金に関する制度です。
配偶者(扶養者)が会社の健康保険(協会けんぽ、組合健保など)や厚生年金に加入している場合、あなたの年収が一定の基準(原則として130万円未満)を満たせば、その被扶養者として認定されます。
被扶養者になると、あなた自身が国民健康保険料や国民年金保険料を個別に支払う必要なく、健康保険の給付を受けられます。
これが、扶養内で働くことの大きなメリットの一つです。(参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは?)
国民健康保険とは?対象者や加入条件の基本
国民健康保険(通称「国保」)は、職場の健康保険(社会保険)に加入していない、日本に住むすべての人を対象とした公的な医療保険制度です。
運営しているのは、お住まいの市区町村です。
社会保険が会社員とその扶養家族を対象としているのに対し、国民健康保険はそれ以外の方々の医療を支える重要な役割を担っています。
- 自営業者、フリーランスの方
- 農業や漁業に従事している方
- 退職して職場の健康保険を脱退した方
- パートやアルバイトをしていて、勤務先の社会保険の加入条件を満たさない方
つまり、配偶者の社会保険の扶養から外れた場合で、かつ、ご自身の勤務先で社会保険に加入しない(できない)場合は、原則としてこの国民健康保険に自分で加入することになります。
加入手続きは、お住まいの市区町村の役所で行います。保険料は前年の所得などに基づいて世帯ごとに計算され、世帯主が納付義務者となります。(参考:厚生労働省 我が国の医療保険について)
年収制限と「〇〇万円の壁」の基礎知識
扶養内で働くことを考える際に、必ず耳にするのが「〇〇万円の壁」という言葉です。
これは、年収が一定の金額を超えると、税金や社会保険料の負担が発生・増加する基準となる年収額を指します。壁の種類によって影響が異なるため、それぞれの意味を正しく理解しておくことが重要です。
あなたの年収が103万円を超えると、あなた自身に所得税がかかり始めます。
また、配偶者が受けられる「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に切り替わり、配偶者の税負担が少しずつ増え始める分岐点でもあります。(参考:国税庁 No.2260 所得税の税率)
年収130万円未満であっても、以下の条件をすべて満たす場合は、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。
これを「106万円の壁」と呼びます。加入すると、給与から社会保険料が天引きされるため、手取り額が減ることになります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員数が51人以上の企業に勤務(※2024年10月以降)
上記の106万円の壁の条件に当てはまらない場合でも、年収が130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れなければなりません。
扶養から外れた後は、ご自身の勤務先の社会保険に加入するか、それができない場合は国民健康保険と国民年金に自分で加入し、保険料を全額自己負担する必要があります。
手取り額への影響が最も大きい、非常に重要な壁です。(参考:厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ)
あなたの年収が150万円を超えると、配偶者が受けている「配偶者特別控除」の額が段階的に減り始めます。
これにより、配偶者の税負担が徐々に増えていくことになります。
控除額はあなたの年収が201.6万円になるまで続きますが、150万円が満額控除を受けられる上限です。(参考:国税庁 No.1195 配偶者特別控除)
保険料・年金・税金の違いを比較
扶養内で働くか、扶養から外れて国民健康保険などに加入するかによって、ご自身と世帯全体の金銭的な負担は大きく変わります。
ここでは、健康保険料、年金、税金という3つの観点から、具体的な違いを一覧表で比較してみましょう。
| 扶養内(年収130万円未満※)の場合 | 扶養外(年収130万円以上)の場合 | |
| 健康保険料 | 支払う必要なし。(配偶者の会社の健康保険に被扶養者として加入。) | 全額自己負担。(勤務先の社会保険に加入、国民健康保険に加入のいずれかで保険料を支払う。) |
| 年金保険料 | 支払う必要なし。(「第3号被保険者」として国民年金に加入している扱いになり、将来年金を受け取れる。) | 全額自己負担。(勤務先の厚生年金に加入、国民年金に第1号被保険者として加入のいずれかで保険料を支払う。) |
| 税金(本人) | 所得税:年収103万円以下は非課税。住民税:年収約100万円以下は非課税(自治体による)。 | 年収に応じて所得税・住民税を自分で納める。 |
| 税金(配偶者) | 税負担が軽くなる。(配偶者控除または配偶者特別控除が適用され、配偶者の所得税・住民税が安くなる。) | 税負担が重くなる。配偶者控除・配偶者特別控除が適用されなくなり、配偶者の税負担が増える。 |
※年収106万円の壁に該当しない場合
補足:国民年金の保険料について 扶養から外れてご自身で国民年金に加入する場合(第1号被保険者)、定額の保険料を毎月納付する必要があります。参考として、令和7年度の国民年金保険料は月額17,510円です。(参考:日本年金機構:国民年金保険料)
このように、扶養内は保険料の自己負担がない点が最大のメリットですが、扶養から外れるとそれらをすべて自分で支払う義務が生じます。
この負担増を上回る収入を得られるかどうかが、働き方を考える上での一つのポイントになります。
健康保険料と年金保険料の負担比較

扶養内で働くか、それとも扶養から外れるかを選ぶ際、最も気になるのが「結局、手取り額はどう変わるのか?」という点でしょう。前の章で解説した保険料や税金の有無が、世帯全体の手取り収入に直接影響します。
この章では、扶養に入ることによる税金の優遇措置や、扶養から外れた場合に配偶者(扶養者)の負担がどのように変化するのかを、より具体的に掘り下げていきます。
扶養内の場合の税金優遇
扶養内で働くことの金銭的なメリットは、ご自身の保険料負担がないことに加え、配偶者(扶養者)の税金が安くなるという大きな優遇措置がある点です。
これは「配偶者控除」および「配偶者特別控除」という制度によるものです。
あなたの年間合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)である場合に、配偶者の所得から一定額が控除され、税金の負担が軽減されます。
控除額は最大で38万円(所得税の場合)で、これにより配偶者の所得税や住民税が安くなります。 (参考:国税庁 No.1191 配偶者控除)
あなたの年収が103万円を超えて配偶者控除の対象から外れても、すぐに優遇がなくなるわけではありません。
年収が150万円までであれば、配偶者控除と同額(最大38万円)の「配偶者特別控除」が適用されます。
年収150万円を超えると、控除額はあなたの収入に応じて段階的に減っていき、年収201.6万円でゼロになります。(参考:国税庁 No.1195 配偶者特別控除)
このように、扶養内で働くことは、配偶者の税負担を軽くすることで、世帯全体の手取り収入を増やす効果があるのです。
扶養から外れた場合の配偶者(扶養者)の負担変化
ご自身が扶養から外れると、保険料や税金の負担が自分に発生するだけでなく、配偶者(扶養者)の金銭的な負担も増えることになります。
主に、以下の2つの変化が起こります。
あなたの年収が150万円を超えると配偶者特別控除の額が減り始め、201.6万円を超えると控除額はゼロになります。
控除が受けられなくなると、その分配偶者の課税対象となる所得が増えるため、結果として所得税・住民税の納税額が上がります。
例えば、所得税率10%の配偶者が38万円の控除を失った場合、単純計算で所得税が約38,000円、住民税が約38,000円、合計で年間約76,000円の負担増につながる可能性があります。
会社によっては、扶養している家族がいる従業員に対して「家族手当」や「扶養手当」を支給している場合があります。
この手当の支給条件は会社の規定によりますが、多くの場合「社会保険の扶養に入っていること(年収130万円未満)」が基準となっています。
そのため、あなたが年収130万円を超えて扶養から外れると、配偶者が会社から受け取っていた手当が支給されなくなる可能性があります。
月1万円の手当でも年間で12万円になるため、世帯収入への影響は決して小さくありません。ご自身の働き方を考える際には、必ず配偶者の勤務先の就業規則などを確認しておくことが重要です。
このように、扶養から外れる選択は、ご自身の収入が増える一方で、配偶者の税金や手当に影響を及ぼし、世帯全体で見たときに必ずしも手取りが増えるとは限らない点を理解しておく必要があります。
扶養内で働くメリット・デメリット
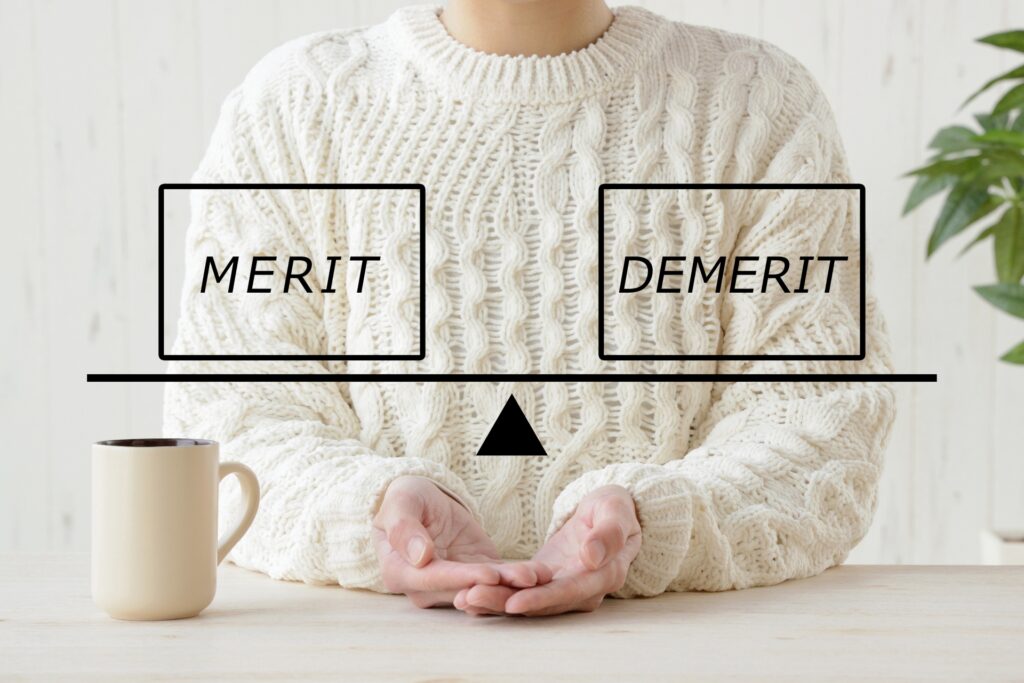
ここまで扶養の制度について詳しく見てきましたが、実際に扶養内で働き続けることには、どのような良い点と注意点があるのでしょうか。
メリットとデメリットの両方を具体的に把握することで、ご自身のライフプランに合った働き方を選びやすくなります。
この章では、扶養内で働くことの金銭的なメリットと、キャリアを考えた際のデメリットをそれぞれ解説します。
メリット|保険料がかからず手取りが多い
扶養内で働く最大のメリットは、社会保険料(健康保険料・年金保険料)の自己負担がないことです。
年収130万円の壁(または106万円の壁)を超えない限り、配偶者の社会保険の被扶養者でいられるため、ご自身で保険料を納める必要がありません。
また、年収103万円以下であれば所得税もかからず、稼いだ金額のほとんどがそのまま手取り収入となります。
例えば、年収125万円で働いた場合、社会保険料の負担がないため、税金を差し引いても手取り額は120万円以上になることがほとんどです。
一方で、年収131万円に増えた途端、社会保険の扶養から外れて国民健康保険と国民年金に加入すると、年間約30万円以上の保険料負担が発生し、結果的に手取りが100万円程度に減ってしまう「働き損」と呼ばれる逆転現象が起こります。
このように、一定の収入までは、扶養内にいる方が効率的に手取り額を確保できるのが大きな魅力です。
デメリット|収入の上限がネックになる
扶養内で働くことは手取り面で効率的ですが、常に収入の上限を気にしなければならないというデメリットも存在します。
この「年収の壁」が、働き方の自由度や将来のキャリア形成に影響を与える可能性があります。
- 働き方の制限と精神的な負担
年収の壁を超えないように、年末になるとシフトを減らしたり、残業を断ったりといった「就業調整」が必要になるケースは少なくありません。「もっと働きたいのに働けない」という状況は、収入機会の損失であると同時に、精神的なストレスにもつながります。
- キャリアアップの機会損失
常に労働時間を制限していると、責任のある仕事を任されにくくなったり、スキルアップの機会を逃してしまったりする可能性があります。長期的に見ると、キャリアが停滞してしまい、将来的に収入を大きく増やすためのステップアップが難しくなることも考えられます。 - 将来受け取る年金額が少なくなる
扶養に入っている期間(国民年金の第3号被保険者)は、保険料を納付しなくても将来、老齢基礎年金を受け取ることができます。
しかし、これはあくまで国民年金の基礎部分のみです。
もし扶養から外れて厚生年金に加入すれば、この老齢基礎年金に加えて、収入に応じた「老齢厚生年金」が上乗せされます。扶養内で働き続けることは、将来の年金受給額を増やす機会を逃している、と捉えることもできるのです。 (参考:日本年金機構 公的年金制度の種類と仕組み)
「〇〇万円の壁」を超えると何が起こる?
「壁」を超えるという言葉は、具体的にあなたの税金や社会保険の加入義務が切り替わるタイミングを指します。
どの壁を越えるかによって、起こる変化は異なります。ここでは、それぞれの壁を越えた際に何が起こるのかを改めて整理します。
あなた自身に所得税の納税義務が発生します。
また、配偶者が受けていた「配偶者控除」が「配偶者特別控除」へと切り替わります。
勤務先の従業員数や労働時間などの条件を満たした場合、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必須となります。
給与から社会保険料が天引きされるため手取り額は減りますが、将来の年金が手厚くなるというメリットもあります。
会社の規模などに関わらず、配偶者の社会保険の扶養から外れます。
その後は、ご自身の勤務先の社会保険に加入するか、それができない場合はお住まいの市区町村で国民健康保険と国民年金に自ら加入し、保険料を全額自己負担しなければなりません。
金銭的な負担が最も大きく変わるポイントです。
配偶者が受けている「配偶者特別控除」の控除額が、あなたの収入の増加に応じて段階的に減り始めます。
これにより、配偶者の税負担が徐々に増えていきます。
扶養を抜けて国保に加入するメリット・デメリット

扶養内で働くことのメリット・デメリットを見てきましたが、反対に、扶養から外れて国民健康保険(または会社の社会保険)に加入する働き方にはどのような特徴があるのでしょうか。
保険料などの負担は増えますが、それを上回るメリットも存在します。
ここでは、扶養を抜けることの利点と注意点を解説し、どのくらいの収入があれば「損」にならないのかをシミュレーションで見ていきます。
メリット|収入制限を気にせず働ける
扶養を抜けて自分で保険料を納めることの最大のメリットは、「年収の壁」という上限を一切気にすることなく、自分の裁量で自由に働けるようになる点です。
これまでのように「年収が130万円を超えそうだから」とシフトを調整したり、残業を断ったりする必要がなくなります。
働きたいときに働きたいだけ働くことができるため、収入を大幅に増やすことが可能です。
もちろん、扶養から外れた直後は保険料負担によって一時的に手取りが減る「働き損」の状態になりやすいですが、そこからさらに収入を伸ばせば、世帯全体の収入は着実に増えていきます。
収入の天井がなくなることで、より責任のある仕事に挑戦したり、スキルアップを目指したりと、長期的な視点でのキャリア形成も可能になります。
これは、将来の経済的な自立に向けた大きな一歩と言えるでしょう。
デメリット|保険料・年金をすべて自分で負担
扶養から外れることの最も大きなデメリットは、これまで免除されていた社会保険料を全額自分で支払う義務が生じることです。
この負担は、家計に直接影響を与えるため、事前にどのくらいの金額になるのかを把握しておく必要があります。
主に負担することになるのは、以下の2つです。
- 国民健康保険料
お住まいの市区町村に納める保険料です。
金額は前年の所得や世帯の加入者数などによって決まります。所得に応じて保険料が変動するため、収入が増えれば増えるほど負担も大きくなります。支払い義務は世帯主にあるため、世帯主宛に請求が届きます。
(参考:保険料の計算方法は市区町村によって異なります。例えば、東京都新宿区 保険料の計算方法について のように、多くの自治体がウェブサイトで計算方法を提供しています。)
- 国民年金保険料 所得にかかわらず、毎月定額の保険料を納める必要があります。令和7年度の保険料は月額17,510円で、年間で約21万円の負担となります。 (参考:日本年金機構 国民年金保険料)
これらを合計すると、年収によっては年間で30万円〜40万円以上の負担になることも珍しくありません。
扶養を抜けて収入を増やす場合は、この大きな固定費が発生することを念頭に置き、負担分を十分に上回る収入を得られるかどうかを慎重に判断する必要があります。
シミュレーションで見る「どのくらい稼げば損しない?」
扶養から外れる際に最も気になるのが、「年収がいくらを超えれば、保険料負担を上回って世帯の手取りが増えるのか?」という点です。
この「働き損」がなくなる分岐点は、お住まいの地域や配偶者の年収によって異なりますが、ここでは一つのモデルケースで試算してみましょう。
- 本人: 40代・パート勤務(給与収入のみ)・東京都世田谷区在住
- 配偶者: 40代・会社員・年収500万円
- 保険料: 令和7年度の国民年金保険料(月額17,510円)と世田谷区の国民健康保険料率で計算
- その他、会社の家族手当などはないものとします。
| 本人の年収 | 本人の手取り額(概算) | 配偶者の手取り額(概算) | 世帯の手取り額(概算) |
|---|---|---|---|
| 129万円(扶養内) | 約125万円 | 約391万円 | 約516万円 |
| 131万円(扶養を抜ける) | 約101万円 | 約391万円 | 約492万円 |
| 170万円(扶養を抜ける) | 約132万円 | 約385万円※ | 約517万円 |
※本人の年収が150万円を超えるため、配偶者特別控除が減少し、配偶者の手取りが減少します。上記は概算値です。実際の手取り額は、各種控除やお住まいの自治体の保険料率によって異なります。
このケースでは、年収129万円の時と比べて、年収131万円になると世帯の手取りが年間約24万円も減少するという「働き損」が発生しています。
これは、年間約21万円の国民年金保険料と、約8万円の国民健康保険料の負担が新たに発生するためです。
そして、この手取りの減少分を取り戻し、扶養内だった頃の世帯手取りを超えるには、年収170万円あたりまで稼ぐ必要があることがわかります。
もちろん、これはあくまで一例です。
しかし、扶養から外れて国民健康保険に加入する場合、一般的に年収160万〜170万円が一つの大きな分岐点になると考えておくと良いでしょう。
どちらを選ぶべき?判断のポイント

ここまで、扶養内で働く場合と扶養から外れて働く場合のメリット・デメリットを様々な角度から見てきました。
結局のところ、どちらの働き方が「得」なのかは、個人の価値観やライフプランによって変わるため、唯一の正解はありません。
大切なのは、ご自身が何を最も優先したいかを明確にすることです。
この章では、あなたの状況に合った選択をするための3つの判断ポイントを提案します。
ポイント①|手取り優先:収入が少ないうちは扶養内にとどまる選択
「まずは目先の世帯収入を最大限に確保したい」
もしあなたがこのように考えているのであれば、扶養内で働くことを選択するのが合理的です。
前述のシミュレーションで見たように、年収が130万円を少し超えた程度では、社会保険料の負担が重くのしかかり、かえって世帯の手取りが減ってしまう「働き損」に陥ってしまいます。
- 子育て中で働く時間に制約がある
- 現在の仕事では、年収170万円以上を目指すのが難しい
- 世帯のキャッシュフローを最優先したい
このような状況では、無理に収入を増やそうとするよりも、年収130万円の壁を意識して就業調整を行い、扶養内で効率よく働く方が、金銭的なメリットは大きくなります。
まずは扶養内で働きながら、将来的に収入を増やせる見込みが立ったときに、改めて働き方を見直すという考え方が良いでしょう。
ポイント②|将来の保障優先:収入増が見込めるなら国保加入や社保加入を検討
「目先の手取りが減っても、将来の安心やキャリアを重視したい」
もしあなたがこのように考えており、年収170万円以上など、保険料負担を十分にカバーできる収入増が見込めるのであれば、扶養から外れることを積極的に検討すべきです。
扶養から外れて自分で社会保険(会社の健康保険・厚生年金)に加入することには、将来に向けた大きなメリットがあります。
厚生年金に加入すると、国民年金のみの場合に比べて、将来受け取れる年金額が「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階建てになり、手厚い保障を準備できます。
これは、ご自身の老後の生活の安定に直結する非常に重要なポイントです。(参考:日本年金機構 年金制度・手続き)
会社の健康保険に加入していると、業務外の病気やケガで連続して4日以上仕事を休んだ場合に、給与の約3分の2が支給される「傷病手当金」という制度を利用できます。
扶養に入っている場合や国民健康保険には原則ない、万が一のときの心強いセーフティネットです。(参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき)
収入の上限を気にする必要がなくなるため、スキルアップや昇進に積極的に挑戦でき、ご自身のキャリアと収入の可能性を大きく広げることができます。
短期的な手取り額だけでなく、こうした長期的な視点でのメリットも踏まえて、扶養から外れるという選択肢を考えてみましょう。
ポイント③|家庭全体で最適解を考える:配偶者の勤務状況や家族構成も考慮
扶養をどうするかは、あなた一人の問題ではなく、家計を共にするパートナーと話し合って決めるべき重要なテーマです。
最終的な判断は、家庭全体の状況を総合的に見て行う必要があります。
特に、以下の点は必ず確認・相談しておきましょう。
扶養から外れることで、配偶者が会社から受け取っている「家族手当」や「扶養手当」がなくなる可能性があります。
これは世帯収入に直接影響するため、事前に配偶者の会社の就業規則を確認することが不可欠です。
配偶者の収入は、扶養から外れた際の税負担の変化に影響します。
また、将来的に配偶者が転職や独立を考えている場合、あなたが安定した収入と社会保険の基盤を築いておくことが、家庭全体のリスク分散につながるかもしれません。
「子どもが小さいうちは扶養内で働き、小学校に入学したら扶養を外れて本格的に働く」といった、ライフステージに合わせた柔軟な働き方も選択肢の一つです。
住宅ローンの返済や教育費のピークなど、将来必要になるお金から逆算して、今の働き方を決めるという視点も大切です。
個人の希望だけでなく、家庭全体の将来像をパートナーと共有し、お互いにとって最も納得のいく「最適解」を見つけ出すようにしましょう。
国民健康保険と扶養に関するよくある質問

ここまで制度の比較や判断のポイントを解説してきましたが、個別のケースで迷うことも多いかと思います。
この章では、扶養と国民健康保険に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
Q1. 退職後、配偶者の扶養に入るのと国保に加入するのはどちらが得?
A. 年収などの加入条件を満たせるのであれば、一般的に配偶者の扶養に入る方が金銭的な負担は圧倒的に軽くなります。
理由は以下の通りです。
- 扶養の場合: 配偶者の社会保険の被扶養者になれば、ご自身が支払う健康保険料・年金保険料は0円です。
- 国保の場合: 国民健康保険に加入すると、保険料を自分で納める必要があります。特に注意が必要なのは、国民健康保険料は前年の所得を基に計算される点です。
そのため、退職した翌年は、退職前の高い所得を基準に保険料が計算され、予想以上に高額な請求が来るケースが少なくありません。
ただし、配偶者の扶養に入るには「退職後の年間収入見込みが130万円未満である」などの条件を満たす必要があります。
失業手当も収入とみなされるため、受給額によっては扶養に入れない場合があります。
まずはご自身が扶養の加入条件を満たしているかを確認し、条件を満たすのであれば、扶養に入る手続きを進めるのが最も経済的な選択と言えるでしょう。
Q2. 扶養から外れると家族の税金負担は増える?
A. はい、増える可能性が高いです。
あなたが扶養から外れると、主に2つの理由で世帯全体の税金や社会保険料の負担が増加します。
扶養から外れることで、あなた自身が国民健康保険料・国民年金保険料(または会社の社会保険料)を支払うことになります。
また、年収103万円を超えれば所得税、約100万円を超えれば住民税の納税義務も生じます。
あなたの年収が一定額(201.6万円)を超えると、配偶者が受けていた「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用対象外となります。
これにより配偶者の課税所得が増え、結果として所得税や住民税が高くなります。
このように、扶養から外れると、あなた自身の負担と配偶者の負担が同時に増えるため、世帯全体で見たときの影響は小さくありません。(参考:国税庁 No.1195 配偶者特別控除)
Q3. 国保と会社の健康保険で医療の保障内容に違いはある?
A. 病院窓口での自己負担割合など基本的な部分は同じですが、万が一の際の所得保障に関連する手当に大きな違いがあります。
- 医療費の自己負担割合: 年齢に応じて、かかった医療費の1割〜3割を自己負担する点はどちらも同じです。
- 高額療養費制度: 1ヶ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度はどちらにもあります。
一番の違いは、病気や出産で働けなくなった際の所得を補う手当の有無です。
会社の健康保険(社保)は、医療費の保障だけでなく、被保険者の所得保障までカバーしている点で、国民健康保険(国保)よりも手厚い制度になっています。
扶養から外れて働く場合は、こうした保障の違いも理解しておくと良いでしょう。(参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 健康保険ガイド)
Q4. 保険料の負担が少ないのは国保と社保どちら?
A. 同じ収入であれば、一般的に会社の健康保険(社保)の方が本人の金銭的な負担は少なくなります。
理由は大きく2つあります。
会社の健康保険(社保)の最大のメリットは、保険料の半額を勤務先の会社が負担してくれることです。
一方、国民健康保険(国保)は加入者が全額を自己負担しなければなりません。この「労使折半」の仕組みがあるため、社保の自己負担額は国保に比べて大きく抑えられます。
会社の健康保険(社保)は、被保険者本人の給与を基に保険料が決まります。
そのため、扶養する家族(配偶者や子)が何人増えても、本人が支払う保険料は変わりません。
一方、国民健康保険(国保)は加入する人数に応じて保険料(均等割額)が増える仕組みのため、家族が多ければその分負担が重くなります。
このような理由から、保障内容が手厚いだけでなく、保険料の自己負担額の観点からも、会社の健康保険(社保)の方が有利であると言えます。(参考:全国健康保険協会 協会けんぽ 保険料額表)
迷ったらプロに相談してみよう!マネドアで無料相談

「扶養」と「国民健康保険」、どちらを選ぶべきか。
この記事では様々な判断ポイントを解説してきましたが、「自分の場合は具体的にどうなんだろう?」と、個別のシミュレーションや将来設計について、さらに詳しく知りたくなった方も多いのではないでしょうか。
家庭の状況はそれぞれ異なり、税制や社会保険制度は複雑です。
一人で悩んでいても、最適な答えを見つけるのは難しいかもしれません。
そんな時は、お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談してみるのがおすすめです。
「マネドア」は、保険の見直しやNISAの相談、教育費や老後資金のシミュレーションなど、家計に関するあらゆる悩みを専門のFPに無料で相談できるサービスです。
あなたの世帯収入や家族構成、将来のライフプランを基に、扶養内で働くべきか、それとも扶養から外れて収入を増やしていくべきか、専門的な視点から具体的なシミュレーションを交えてアドバイスをもらえます。
複雑なお金の問題を一人で抱え込まず、まずはプロの力を借りて、ご家庭にとっての最適解を見つけてみてはいかがでしょうか。