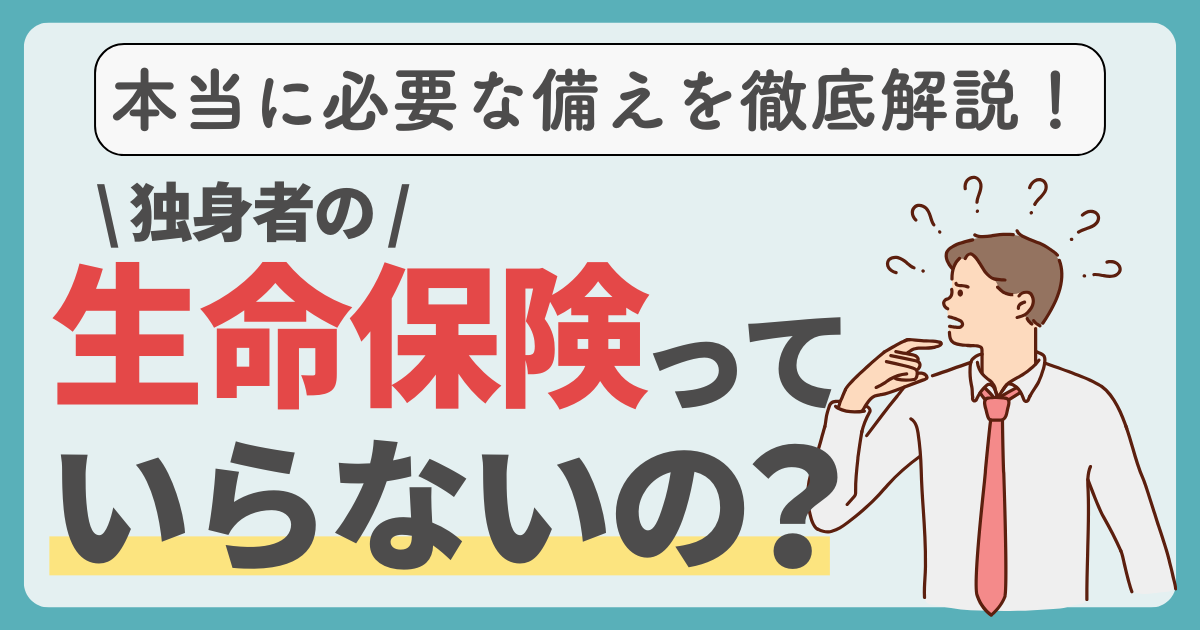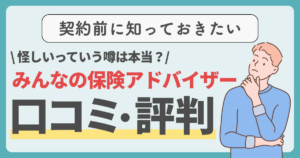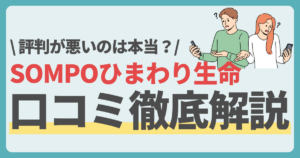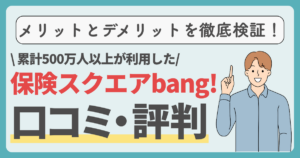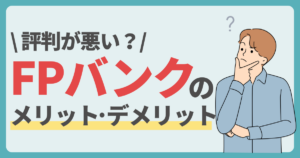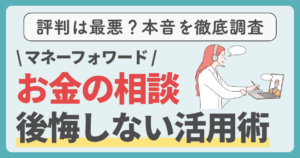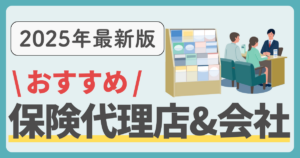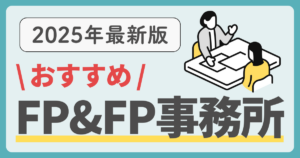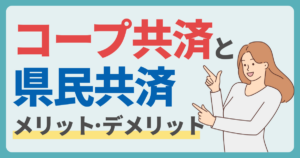「独身だから、生命保険は必要ないかな?」
このように考える方は少なくありません。扶養する家族がいないため、死亡保障の必要性を感じにくいのが主な理由でしょう。
しかし、本当に「いらない」と断言してしまって大丈夫なのでしょうか。
ライフスタイルが多様化する現代において、独身の方が直面するリスクは、万が一の死亡時だけではありません。
病気やケガで働けなくなったときの収入減少、将来の介護費用、そしてご自身の葬儀費用など、自分自身で備えなければならない事柄は意外と多いものです。
この記事では、独身の方にとって生命保険が「いらない」と言われる理由を紐解きながら、公的制度でカバーできる範囲と、本当に備えておくべきリスクについて詳しく解説します。
ご自身の状況に合った、最適な備えを見つけるためのヒントが満載です。
- 独身者でも生命保険の必要性を一概に否定できない理由
- 健康保険や年金など、独身者が活用できる公的制度の範囲
- 独身者が本当に備えるべき3つのリスク
- 生命保険以外にもある、現実的な備えの選択肢
💸「教育費や老後資金、どれくらい必要なのか不安…」
😨「つみたてNISAや保険、ちゃんと選べているか自信がない…」
😭「プロに相談したいけど、営業されそうでこわい…」
お金の悩みって、誰に聞けばいいか分からないもの。
「相談=保険の営業」と思いがちで、なかなか一歩が踏み出せないという方の気持ちもよくわかります。
ただ、時間が経つほど選択肢は狭まり、理想の未来は遠のいてしまいます…
そんな悩み、お金のプロに相談してみませんか?
マネドアは、家計の悩みをFP資格保持率100%の専門家に完全無料で何度でも相談できるサービスです。

今なら、無料相談後にミスタードーナツ ギフトチケット1,000円分をプレゼント中!🎁
無料相談の予約は1分で簡単予約!
お金の不安を抱えたまま過ごす時間を、安心できる時間に変えてみませんか?
\ 知識ゼロでOK!準備不要!1分で簡単予約/
【結論】独身でも生命保険は必要?「いらない」と言い切れない理由とは
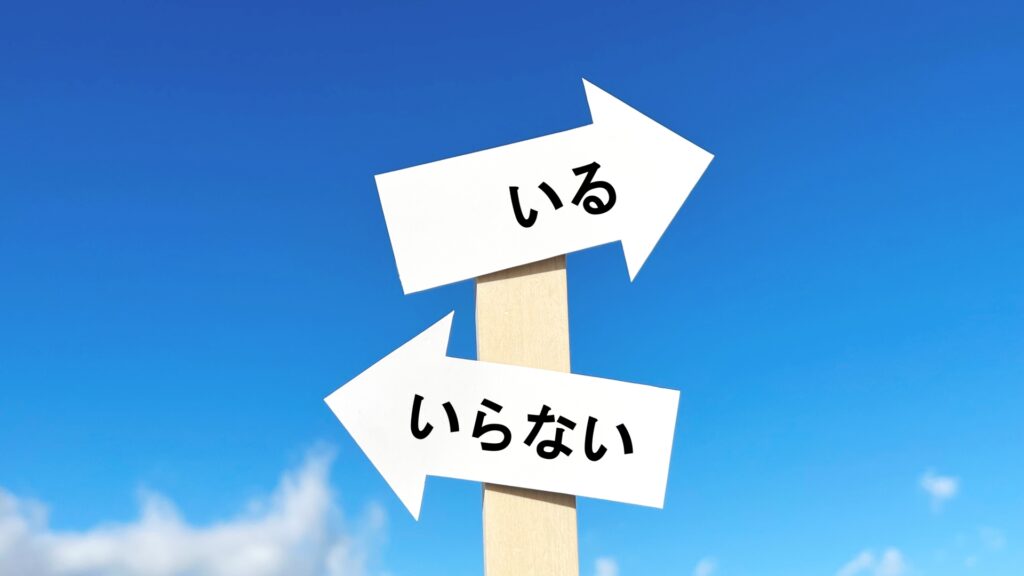
結論から言うと、独身者であっても生命保険が「絶対に不要」とは言い切れません。
「扶養家族がいないから、高額な死亡保障は必要ない」という考えは確かに一理あります。しかし、生命保険の役割は、万が一の死亡時に遺族にお金を残すことだけではありません。
自分自身の生活を守るため、あるいは残された家族に迷惑をかけないために、保険が大きな助けとなる場面があります。
ここでは、独身者と生命保険の関係を考える上で重要な2つの視点について解説します。
「扶養なし=不要」では片づけられない現実
「扶養家族がいない」という言葉だけで、備えが不要だと判断するのは早計かもしれません。
例えば、ご両親が高齢で、将来的にあなたが経済的な支えとなる可能性がある場合や、万が一の際に葬儀費用などで負担をかけたくないと考えている方もいるでしょう。
また、ご兄弟に障害があり、生活をサポートしている場合など、法律上の扶養関係はなくても、実質的にあなたが経済的な支えとなっているケースも考えられます。
このように、ご自身の状況を広く見渡してみると、あなたに万が一のことがあった場合に経済的に困る人がいないか、改めて考える必要があります。
“いざという時”に困るのは自分自身
独身の方にとって、最も現実的で大きなリスクは「自分が生きている間に、病気やケガで経済的に困窮してしまうこと」です。
会社員や公務員であれば、ある程度の公的保障がありますが、治療が長引いたり、後遺症で以前のように働けなくなったりした場合、収入が大幅に減少する可能性があります。
頼れるパートナーがいない分、治療費や生活費のすべてを自分一人で賄わなければなりません。
十分な貯蓄があれば問題ないかもしれませんが、急な出費で貯蓄が底をついてしまう事態も想定されます。
生命保険は、こうした「自分自身が生きるためのリスク」に備える上でも、有効な選択肢の一つとなるのです。
独身者がカバーできるリスクは?まずは公的制度を確認しよう

民間の生命保険を検討する前に、私たちがすでに加入している「公的制度」で、どのようなリスクがどの程度カバーされるのかを正しく理解しておくことが非常に重要です。
この土台となる保障を知ることで、自分にとって本当に不足している部分だけを民間の保険で効率的に補うことができ、保険料の払い過ぎを防ぐことにつながります。
医療費は健康保険、高齢期は年金でカバーできる部分も
日本は国民皆保険制度を採用しており、誰もが何らかの公的医療保険に加入しています。これにより、医療機関での自己負担は原則として3割に抑えられます。
さらに、医療費の自己負担額が著しく高額になるのを防ぐための「高額療養費制度」があります。
これは、1か月の医療費の自己負担額に上限が設けられており、上限を超えた分は払い戻される仕組みです。
例えば、年収約370~約770万円の方の場合、自己負担の上限額は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」となり、ひと月の負担が10万円弱で済むケースが多くなっています。(参考:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
)
また、会社員や公務員の方が加入する健康保険には、病気やケガで連続して4日以上仕事を休んだ場合に、給与の約3分の2が最長1年6か月にわたって支給される「傷病手当金」という制度もあります。(参考:全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金))
老後の生活については、基盤となる「公的年金(老齢年金)」があります。
また、現役時代に重い障害を負った場合には「障害年金」、万が一死亡した場合には一定の条件を満たす遺族に「遺族年金」が支給されるなど、国によるセーフティーネットは私たちが考える以上に手厚いものとなっています。
扶養家族がいないなら「死亡保険」は本当に必要?
扶養家族がいない独身者の場合、遺族の生活を守るための高額な死亡保障(死亡保険)の必要性は低いと言えます。
あなたに万が一のことがあっても、経済的に困窮する家族がいないのであれば、死亡保険の最も重要な役割が当てはまらないためです。
ただし、「全く必要ない」と断言する前に、少し考えておきたい点があります。それは、ご自身の「お葬式代や身辺整理の費用」です。
株式会社鎌倉新書が2024年に実施した調査によると、葬儀費用の平均総額は約118.5万円となっています。
こうした費用を、残された親や兄弟に負担させたくないという思いから、葬儀代相当額として200~300万円程度の死亡保険に加入する、という考え方は非常に現実的です。(参考:第6回お葬式に関する全国調査(2024))
高額な保障は必要なくとも、「残された人に金銭的な迷惑をかけない」という目的を明確にした上で、必要最低限の死亡保険を準備しておくことは、合理的な選択肢の一つと言えるでしょう。
それでも備えておきたい3つのリスクとは

手厚い公的制度があるとはいえ、それだけではカバーしきれない、あるいは不十分なリスクも確かに存在します。
特に、頼れる家族がいないことが多い独身者だからこそ、自分自身でしっかりと向き合い、備えておくべきリスクがあります。
ここでは、独身者が特に意識しておきたい3つのリスクについて解説します。
病気やケガで働けなくなったとき、収入がゼロに
独身者の家計は、ご自身の収入一本で成り立っています。もし、病気やケガが原因で長期間働けなくなってしまったら、その影響は計り知れません。
会社員の方には給与の約3分の2が最長1年6か月支給される「傷病手当金」がありますが、それ以降も復職できない場合は公的な支援が途絶える可能性があります。
また、特に注意が必要なのは、自営業者やフリーランスの方々です。国民健康保険には傷病手当金の制度がないため、働けなくなった瞬間から収入がゼロになるリスクに直面します。
治療費は高額療養費制度で抑えられても、家賃や食費、水道光熱費といった生活費は毎月かかり続けます。収入が途絶えた中で貯蓄を取り崩す生活は、精神的にも大きな負担となるでしょう。
老後の生活・介護費…年金だけでは不安な将来
現役時代にどれだけ備えられるかは、老後の生活の質に直結します。総務省の家計調査報告(2023年)によると、65歳以上の単身無職世帯の家計は、平均で毎月21,738円の赤字(実収入114,690円に対し、消費支出が136,428円)となっています。(参考:総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要)
これは、公的年金だけを頼りに生活していくことの厳しさを示すデータです。
さらに深刻なのが「介護」の問題です。
生命保険文化センターの調査(2021年度)では、介護にかかる費用は、住宅改修や介護用ベッドの購入など一時的な費用の合計が平均で74万円、月々の費用が平均で8.3万円と報告されています。(参考:公益財団法人 生命保険文化センター「2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」)
葬儀や身辺整理の費用は“自分で準備”が原則
自分に万が一のことがあった場合、残された家族に金銭的な負担をかけたくないと考えるのは自然なことです。
前述の通り、葬儀費用だけでも平均で100万円以上かかるのが実情です。
これに加えて、お墓の費用、賃貸物件の原状回復や遺品整理の費用、未払いの医療費や税金の支払いなど、死後に必要となるお金は決して少なくありません。
これらの費用を自分の預貯金から支払ってもらえれば良いですが、手続きが煩雑だったり、そもそも十分な預貯金がなかったりするケースも考えられます。
「立つ鳥跡を濁さず」ではありませんが、人生の最期に必要となる費用を自分自身で準備しておくことは、残される人への最後の思いやりと言えるでしょう。
この目的のために、少額の死亡保険を活用するのは非常に合理的な方法です。
「独身だから生命保険はいらない」と言われる理由

ここまで独身者が備えるべきリスクについて解説してきましたが、世の中で「独身に生命保険はいらない」という声が上がるのには、もちろん合理的な理由があります。
保険の必要性は、その人の経済状況や価値観によって大きく変わるため、全ての人に同じ答えが当てはまるわけではありません。
なぜ「いらない」という意見が出てくるのか、その背景にある2つの大きな理由を見ていきましょう。
ご自身の状況と照らし合わせることで、保険との適切な距離感が掴めるはずです。
貯蓄や公的保障で足りる人もいる
生命保険は、万が一の経済的リスクに備えるための一つの「手段」に過ぎません。
もし、そのリスクをご自身の貯蓄で十分にカバーできるのであれば、毎月保険料を支払ってまで保険に加入する必要性は低くなります。
例えば、
- 病気やケガで1〜2年働けなくなっても生活に困らないだけの預貯金がある
- 葬儀費用や身辺整理費用として、現金で300万円以上を常に準備できている
- 老後資金や介護費用も、すでに計画的に準備できている
といった方は、まさに保険が「不要」な人に当てはまる可能性があります。
公的保障という土台があり、さらにご自身の資産でリスクに対応できるのであれば、保険料を支払うよりも、その分を貯蓄や投資に回す方が合理的と考えることもできます。
保険料のムダ遣いを避けるには「目的と金額の見極め」が鍵
「独身だから生命保険はいらない」と言われる最大の理由は、「目的が曖昧なまま加入すると、保険料が大きなムダ遣いになる」からです。
「なんとなく将来が不安だから」「営業担当者に勧められるがままに」といった理由で、自分に合っていない高額な保険に加入してしまうと、毎月の保険料が家計を圧迫し、かえって生活を苦しくする原因になりかねません。
特に、扶養家族がいない独身者にとって、過剰な死亡保障は典型的なムダ遣いの例です。
保険を検討する際は、
- 何のために(目的): 働けなくなった時の生活費? がんの治療費? 葬儀代?
- いくら必要か(金額): 公的保障で足りない分はいくらか?
- いつまで必要か(期間): 60歳まで? 一生涯?
この3点を明確にすることが不可欠です。
「いらない」という意見は、この見極めをしないまま保険に加入することへの警鐘と捉えることができるでしょう。
独身でも生命保険が“必要”になるのはこんなとき

ここまでの内容を踏まえ、「自分には貯蓄もあまりないし、公的保障だけでは少し不安かもしれない」と感じた方もいるでしょう。
ここでは、どのような方が生命保険の必要性が高いのか、具体的な3つのケースに分けて解説します。ご自身が当てはまるかどうか、チェックしてみてください。
自営業・フリーランスで国の保障だけでは不安な人
会社員や公務員と比較して、自営業者やフリーランスの方は、公的な保障が手薄になる傾向があります。最も大きな違いは、病気やケガで働けなくなった際の「傷病手当金」がないことです。
これは、収入が途絶えても公的な所得補償がないことを意味し、独身者にとっては死活問題になりかねません。
また、将来受け取る公的年金も、会社員が加入する厚生年金がない「国民年金」のみとなるため、受給額が少なくなる傾向があります。
昭和31年4月2日以後生まれの方の場合の年金の月額は、厚生年金が約232,784円(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)であるのに対し、国民年金は69,308円(老齢基礎年金(満額))となっています。(参考:令和7年4月分からの年金額等について)
このように、医療・就業不能・老後のすべての面で、会社員以上に「自助努力」が求められるため、民間の保険で不足分を補う必要性は非常に高いと言えるでしょう。
親・兄弟など、扶養している相手がいる人
法律上の扶養家族でなくても、実質的にあなたが経済的な支えとなっている方がいる場合、生命保険(特に死亡保険)の必要性は格段に上がります。
例えば、
- 高齢の親に毎月仕送りをしている
- 障害のある兄弟や姉妹の生活を援助している
- 甥や姪の学費を援助している
といったケースです。
もしあなたに万が一のことがあれば、その方々の生活が成り立たなくなる恐れがあります。
このような場合は、「残された家族の生活を守る」という生命保険本来の役割が当てはまります。
誰に、いつまで、いくらくらいの援助を続けたいのかを具体的に考えることで、あなたにとって必要な保障額が見えてきます。
貯金ゼロ・備えゼロなら保険が「貯金代わり」になる
「貯蓄が苦手で、なかなかお金が貯まらない」という方にとっても、保険は有効な選択肢です。
十分な貯蓄がない場合、急な病気やケガによる入院・手術費といった突発的な出費に対応することができません。
このような場合に備えて、最低限の医療保険やがん保険に加入しておけば、少ない保険料負担で、いざという時にまとまった給付金を受け取ることができます。
これは、万が一の際に「貯金がなくても医療費を払える」という大きな安心につながります。
また、解約した際に返戻金がある「貯蓄型」の保険であれば、毎月の保険料が半ば強制的な貯蓄の役割を果たします。
ただし、掛け捨て型に比べて保険料は割高になり、早期に解約すると元本割れするリスクもあるため、あくまで「保障を準備しながら、貯蓄もできる選択肢」の一つとして慎重に検討することが大切です。
生命保険以外の手段も検討を!独身者の現実的な備え方

ここまで主に生命保険の必要性について解説してきましたが、独身者の備えは保険だけがすべてではありません。
むしろ、ご自身の目的やライフプランに合わせて、保険や貯蓄、投資といった手段を賢く組み合わせることが、より効率的で現実的な備えにつながります。
ここでは、独身者が検討すべき具体的な備えの方法を3つの視点からご紹介します。
医療・がん保険は最低限の保障でOK
独身者の医療保障は、手厚すぎる必要はありません。
なぜなら、日本には高額療養費制度があり、一個人の医療費負担には上限が設けられているからです。
そのため、民間の医療保険は、この公的保障でカバーできない部分を補う「脇役」として捉えましょう。
具体的には、
- 入院日額: 5,000円〜10,000円程度
- 保障内容: 先進医療特約など、本当に必要なものに絞る
といったシンプルな内容で十分なケースがほとんどです。
高額な個室に入りたい場合の「差額ベッド代」や、当面の生活費の足しにしたい、という明確な目的がある場合に上乗せを検討するのが良いでしょう。
がんについては、治療の長期化や、公的保険が適用されない先進医療・自由診療の可能性に備え、診断された際にまとまった一時金が受け取れる「がん保険」を別に検討するのも有効です。
就業不能保険で「働けないリスク」に備える
独身者にとって、死亡のリスクよりも「病気やケガで長期間働けなくなるリスク」の方が、より現実的で深刻かもしれません。このリスクに直接備えられるのが「就業不能保険」です。
これは、所定の就業不能状態になった場合に、毎月お給料のように一定額(例:10万円、15万円など)が受け取れる保険です。
特に、傷病手当金のない自営業・フリーランスの方にとっては、最優先で検討すべき保険と言えます。
会社員の方でも、傷病手当金の支給が終了する「1年6ヶ月後」から給付が開始されるタイプを選ぶと保険料を抑えられます。
ご自身の毎月の生活費を算出し、公的保障だけでは不足する分を補う形で備えておくと、万が一の際の大きな安心材料になります。
老後資金は保険以外(NISA・年金保険)も選択肢
老後の資金準備は、長期的な視点が求められるため、保険以外の選択肢も積極的に活用したい分野です。
保険料として毎月コツコツ積み立てることで、将来確実に年金を受け取れる商品です。
生命保険料控除による税制上のメリットもありますが、現在の低金利下では大きく増えることは期待しにくい側面もあります。
2024年から新制度がスタートし、注目を集めている制度です。
投資で得た利益が非課税になるという大きなメリットがあり、個人年金保険よりも高いリターンが期待できます。ただし、元本保証はなく価格変動のリスクが伴います。
「着実に貯めたい」「税金の優遇を受けたい」なら個人年金保険、「リスクをとってでも積極的にお金を育てたい」ならNISAというように、ご自身の考え方やリスク許容度に合わせて選ぶことが大切です。
もちろん、両方を組み合わせて準備を進めるのも賢い方法です。
独身者の生命保険選び、プロに相談するのがおすすめ

ここまで、独身の方に必要な備えについて、公的制度から保険、NISAまで幅広く解説してきました。
ご自身の状況と照らし合わせ、「何から手をつければいいのか」「自分に最適なプランはどれだろう」と、かえって悩んでしまった方もいらっしゃるかもしれません。
- 自分にとって本当に必要な保障額はいくらなのか?
- 保険とNISA、どちらを優先すべき? どんなバランスが理想?
- 数えきれないほどある金融商品の中から、どれを選べばいいの?
これらの問いに、専門知識なしで完璧な答えを出すのは至難の業です。
そんな時こそ、お金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談することをおすすめします。
FPは、あなたの現在の家計状況や将来の夢、価値観などを丁寧にヒアリングし、数ある選択肢の中からあなたに合ったプランを中立的な立場で提案してくれます。
「マネドア」では、経験豊富なFPによる無料オンライン相談を実施しています。

マネドアでは、独身の方のライフプランニングに関するご相談も数多く承っており、漠然としたお金の不安を解消するお手伝いをしています。
「まずは話だけ聞いてみたい」「ちょっとした疑問を質問したい」といった動機でも全く問題ありません。
無理な勧誘は一切なく、ご自宅からリラックスしてご相談いただけます。
一人で悩まず、まずはプロの視点を取り入れて、あなたの未来に向けた最適な備えを一緒に考えてみませんか?
それが、漠然とした不安を「具体的な安心」に変えるための、最も確実な第一歩になるはずです。